うつ病とは?症状や診断、治療や回復過程についてリアルな体験談をもとにまとめました

「うつ病とは」「うつ病 症状」などで検索をかけると、出てくるのは医療機関の情報ばかり。
「経験した人にしかわからないリアルな情報を知りたいのにな~」と思ったことはありませんか?
私も、うつ病になった当初はそう思っていました。経験者にしかわからない葛藤や苦悩もたくさんありますからね。
そこで本記事では、初期症状や治療方法などの基本情報について、4年前にうつ病を患った私の体験談をまとめてみました。
記事の後半では、発症から4年が経った現在の様子や、病状回復のきっかけになった出来事なども詳しく綴っています。
うつ病の症状や経緯などを知りたい方々は、ぜひ読んでいただけると嬉しいです。
発症から休養まで
この章では、うつ病初期(症状が出始めてから休養期間を取るまで)の体験談を紹介します。
病気になった原因や症状が変化していく過程、薬物療法やカウンセリングなど、当事者ならではのリアルを綴っています。
原因は「心のダム」の決壊
うつ病は、対人関係や環境の変化など、何かしらのストレスがきっかけとなって発症するケースが多いと言われています。
私の場合もまさにそうで「人間関係のもつれによるストレスの増加」を機にさまざまな症状が出始めました。
しかし、人間関係のもつれは、あくまでもきっかけのひとつに過ぎなかったように思います。
その根っこには「今まで頑なに蓋をし続けていた人生の課題」が大きな影響を与えていたような気がします。

私は小さな頃から絵に描いたような不器用人間で、中高時代には不登校やひきこもりも経験しました。
不登校やひきこもりになった理由は「数えきれないほどの膨大なストレス・モヤモヤ」です。
家族仲が不安定だったり、心地よい友人関係が築けなかったり、上手な感情表現の仕方がわからなかったり……。
いろいろなストレス・モヤモヤがあったのですが、私はそれらを放置したまま、不登校・ひきこもり期間を終えることになりました。
「このままではいけない」と思いつつ、自分の弱さと向き合う勇気を持てなくて、頑なに「見て見ぬふり」をしていたのです。
クールに淡々と日常生活を送っているその裏で、今にもあふれ出しそうな“心のダム”を必死にせき止めている
たとえて言うなら、そんな状態でした。
しかし、うつ病発症のきっかけとなった人間関係のもつれは、私にとって人生を揺るがすほどの大きな衝撃がありました。
そのため、これまで何とかせき止められていた心のダムも、ついに決壊を余儀なくされてしまったのです。
これが、私の考える「うつ病を患った本当の理由」です。

時期によって異なる初期症状
初期の頃の症状は、時期によって若干の違いがありました。
あくまでも一個人の体験談となりますが、時期別に詳しく紹介したいと思います。
上記のまとめは、うつ病発症のきっかけとなった出来事(人間関係のもつれ)が起きた1か月後~3か月後の症状です。
私の場合は「光」に敏感になったので、暗い部屋に閉じこもって布団の中で過ごすことも少なくありませんでした。
不登校時代に患ったパニック障害が再発し、電車やバスでの移動が苦しくなり始めたのもこの頃です。
しかし当時は「時間が経てば治るだろう」と思っていたため、医療機関の受診や休養はせず、普通の日常生活を送っていました。
上記のまとめは、人間関係のもつれが起きてから3か月後~5か月後の症状です。
このあたりから一気に症状が増え始め、今まで通りの日常生活を送ることが難しくなりました。
特に私は「眠気」と「体のダル重さ」がひどかったので、1日のほとんどをベッドで過ごしていた記憶があります。
当時の私は大学院生でしたが、体調が優れず授業を欠席することも多くなりました。
このあたりでようやく危機感を抱き、心療内科の受診を決意※①。
「私、もしかしてうつ病かも……?」という実感が湧き始めました。
上記のまとめは、人間関係のもつれが起きてから5か月後~6か月後の症状です。
行動能力がみるみる衰え、必要最低限の外出すらできなくなり、大学院も休学を余儀なくされました。
どこにも行けず、何もできず、普通の日常生活すら送れず、とても苦しくて辛い日々でした。
しかし、定期的に通える心療内科やカウンセリング施設が見つかり、少しだけ気持ちがラクになったのをよく覚えています。
そうして私は「休養期間」に入り、服薬やカウンセリングをはじめとした本格的な治療に取り組むことになったのです。

※①:詳しくは「医療機関を受診するタイミング」の項目をご覧ください。
明るく振舞う「微笑みうつ病」
さまざまな症状に苦しめられている間も、周囲の人に対してはいつもと同じように接することを心がけていました。
「周囲の人を心配させたくない・迷惑をかけたくない」という思いが強かったので、無理やり笑顔を作り、“元気な自分”を演じていたのです。
たとえうつ病を患っていない状態でも、偽りの自分を演じることは、心身に膨大なストレスがかかります。
そのため、自宅に帰るとスイッチが切れたかのように体がフリーズし、床の上で全く動けなくなることもしばしばありました。
今振り返ると、これは典型的な「微笑みうつ病」の症状だったように思います。
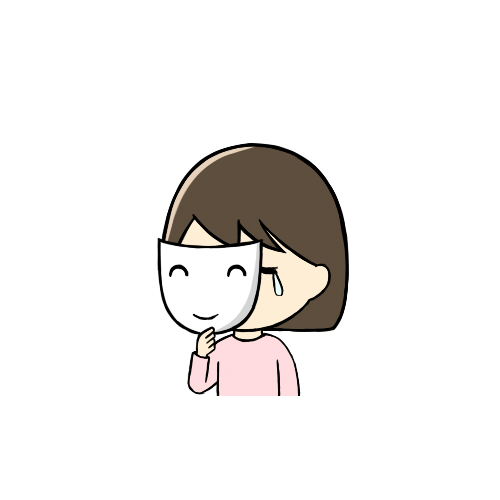
微笑みうつ病とは、人前では気丈に明るく振舞う反面、一人になるとスイッチが切れたかのように落ち込んでしまう状態のことです。
真面目で几帳面な性格の方に多く見られると言われており、その完璧主義的な性格は、うつ病の発症とも関連があるとされています。
周囲を心配させくない気持ちや、笑顔を大切にする気持ちは、とても素敵だと思います。
しかし、辛い時に無理やり笑顔を作ることは、自分の心に嘘をついていることと同意義です。
心のストレスがあふれるまえに、しんどい気持ちを素直に認め、表現できる自分でいたいものです。

医療機関を受診するタイミング
講演やお話会などで質疑応答を受け付けると、ほぼ必ず「医療機関の受診はどのタイミングが良いか?」ということを聞かれます。
受診のタイミング、悩みますよね。過去の私もそうでした。
私がうつ病の件で医療機関を初めて受診したのは、「初期症状の変化過程」の項目に書いたとおり、症状が出始めてから4か月ほど経った頃でした。
その理由は、体と心に大きな変化を感じ、今まで通りの日常生活を送ることが難しくなったためです。
個人的にはこれが、医療機関の受診を考える上での大きな指標になるのではないかと思っています。
- 今まで普通にできていた行動・生活ができない
- 上記の状態が長く持続していて、なかなか良くならない
上記のような状態でお悩みの場合は、一度近くの医療機関に問い合わせてみることをおすすめします。

ここでひとつお伝えてしておきたいことは、医療機関に問い合わせても、すぐに受診できるとは限らないということです。
近年は、うつ病をはじめとした精神疾患を患う方が増加傾向にあります。
そのため、初診が数か月待ちだったり、そもそも初診受付をおこなっていなかったりする心療内科も少なくありません。
私もいろんなクリニックに問い合わせましたが、何度も受診を断られましたし、やっと予約が取れたと思ったら1か月以上先ですごく焦りました。
そのため、ようやく予約日を迎えた頃には、電車利用はもちろん車の運転すらできず、タクシーを使わないと診察に行けないような状態になっていました。
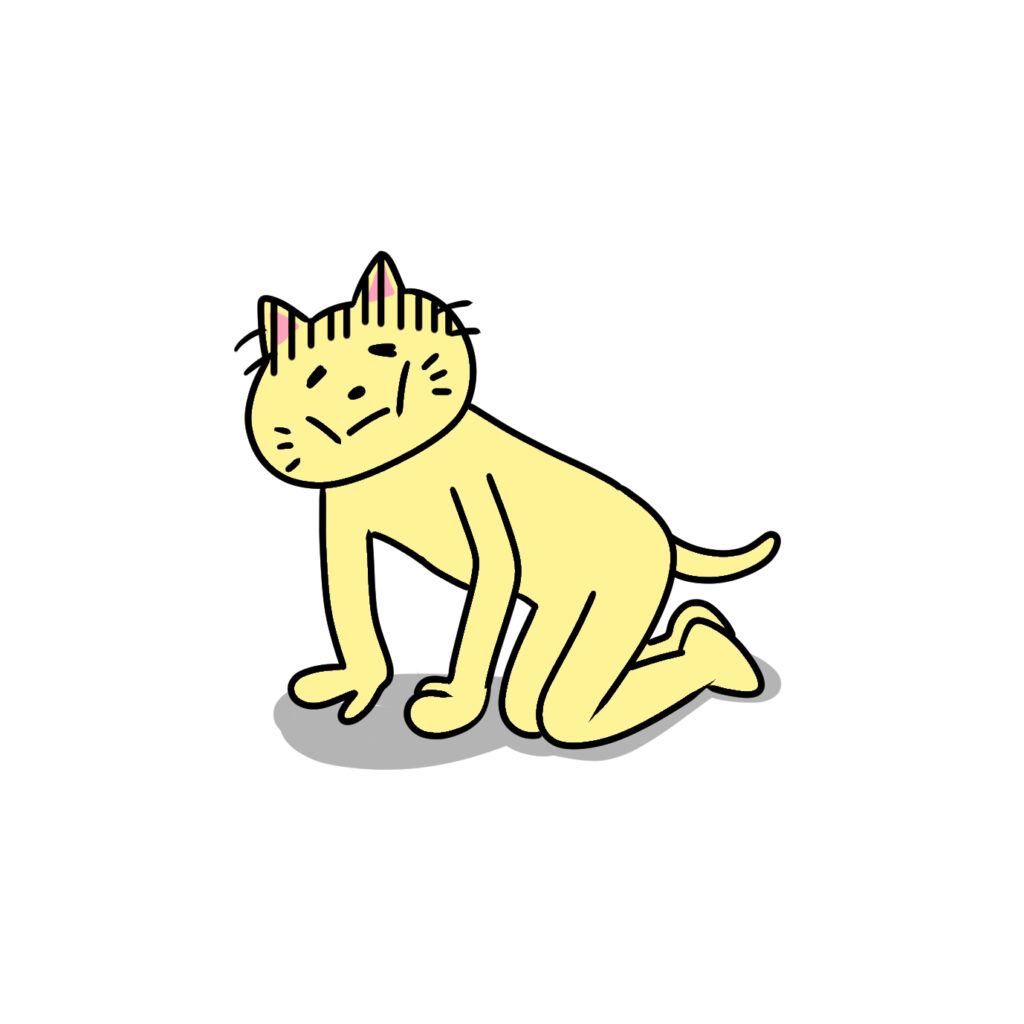
「自分に合いそうなクリニックを探し、受診の可否を問い合わせて予約日まで待つ」。
その一連の行為は、うつ病患者さんにとって想像を絶するほどの大きな負担がかかります。
「ちょっとおかしいかも?」と感じたら、なるべく早めにアクションを起こすことをおすすめします。

医師による診断の違い
うつ病の診断は、本人からの問診を中心におこなわれます。
精神障害は症状が目に見えづらく、検査をして状態を数値化・可視化することが難しいためです。
問診の際によく用いられるのが「DSM₋5」という、アメリカ精神医学会が作成した診断基準です。
「DSM₋5」は「抑うつ気分」や「興味の喪失」など、うつ病によく見られる症状が9つ記されています。
その9つの症状のうち5つ以上が2週間以上持続していると、「うつ病」と診断されるケースが多いそう。
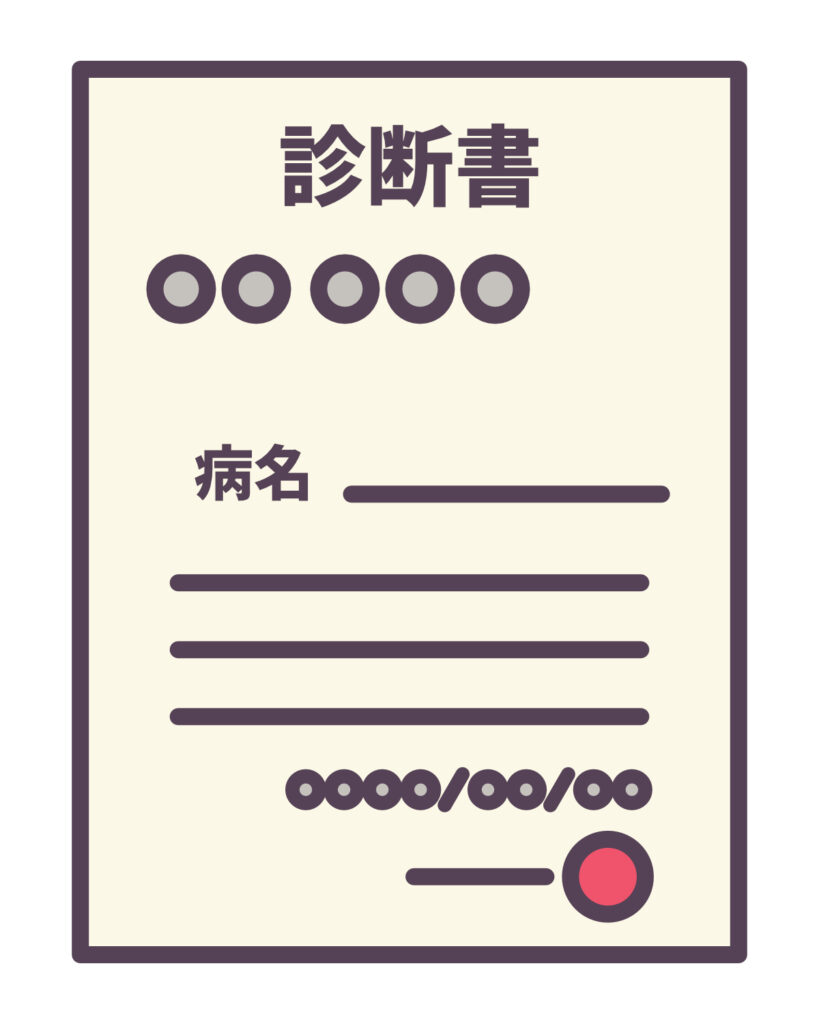
ただし、うつ病経験者として言わせていただくと、うつ病の詳しい判断・診断については、医師によってかなりの違いがあるように感じます。
私はうつ病の症状が出始めてから5つのクリニックを回りましたが、症状に対する医師の見解・診断は、すべて異なっていました※②。
同じような質問をされ、同じような回答をおこなっても、その受け取り方は医師によって千差万別です。
診断に納得できない場合や違和感を抱いた場合は、私のようにセカンドオピニオンの受診を検討してみても良いと思います。
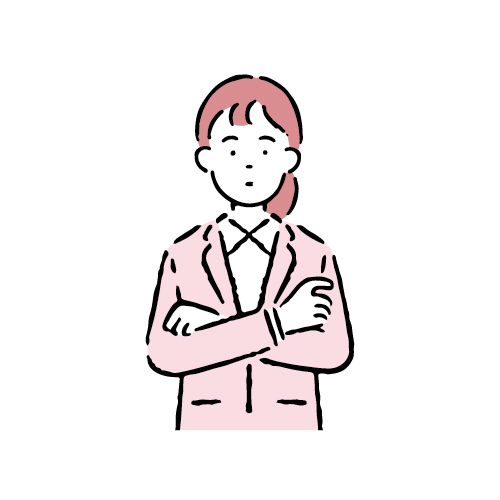
※②:「非定型うつ病のなりかけ」→「ただの情緒不安定」→「社交不安障害」→「軽症うつ病」→「うつ病」という診断・見解でした。
仕事や学校はどうするべき?
「学校や仕事をどうするべきなのか」という問題は、うつ病患者さんのほぼ全員がぶつかる壁だと思います。
私の場合は、症状が悪化して診断が下りたタイミングで、当時通っていた大学院を休学することに決めました。
最初は半年休学のつもりでしたが、あまり症状が回復しなかったため、トータルで1年間の休学期間を設けました。
休学・休職の有無や復帰のタイミングに正解はありませんし、人それぞれ違っていいと思います。
ただ、経験者としてお伝えしたいのは「ご自身が無理なく、心地よく過ごせる選択をするのが一番」だということです。
仕事や学業が大切なのは間違いないですが、何よりも大事にすべきなのは、あなたの体と心です。
周囲の反応や世間体に左右されず、心身ともに安心できる生活・選択を大事にしてほしいと思います。

休養期間
この章では、「大学院の休学」という形で休養期間を得ることになった私の体験談を紹介します。
服薬やカウンセリングの体験談や、休養期間中にやっていたことなど、経験者にしか語れない情報が盛りだくさんです!
休養中にやっていたこと
休養期間中にやっていたことは、これと言って特にありません。
過眠と疲労感の症状があまりにも重すぎて、ほとんど自宅のベッドから出ることができなかったからです。
基本的な外出は、2週間に一度の通院とカウンセリングのみ。
どちらも自宅から車で15分ほどの距離でしたが、それすらも負担が大きく、毎回ヒーヒー言いながら通っていました。
おそらく、もっと遠い場所だったら通うことができなかったと思います。

そんな私ですが、ごく稀に、通院やカウンセリング以外の用事をこなせた日もありました。
その時にやっていた行動・作業を、以下にまとめました。
- 友人とLINEしたり、電話したりする
- 読書をする
- ヨガやストレッチをする
- 簡単なご飯を1品だけ作る
- メイクやファッションの研究をする
- 車で小一時間ほどドライブする
- 30分ほど散歩をする
基本的には、自宅にいながらできる自分の好きなこと・気分が前向きになることをやっていました。
よっぽど体調が良い日はドライブや散歩をすることもありましたが、1時間以上の外出は難しかった記憶があります。
今振り返ると「休むのは良くない、何かしなければ」という危機感が強すぎて、少し無理をして動いていた部分もありました。
しかし、何かの作業・行動に取り組んでいる間は、心のモヤモヤや雑念を忘れて穏やかな時間を過ごせました。
体や心がしんどい時に、無理に行動する必要はありません。
けれど、少しでも「これをやってみようかな」という作業があれば、できる範囲で実践しても良いのではないかなと思います。

休養がもたらした変化
「休養期間」に入ってクリニックとカウンセリングに通い始めてからは、休養前のように重い症状は出なくなりました。
もちろん症状がゼロになったわけではありませんが、「100あったものが60~70くらいになった」ような感覚がありました。
服薬やカウンセリングが良い影響をもたらした部分もあったと思います。
けれど、個人的には、大学院を休学して体と心をゆっくり休められたのが良かったのではないかのと感じます。
おそらく、引き続き大学院に通っていたら、もろもろのしんどさは100のままだった(もしくは140くらいに増えていた)と思います。

休養し始めた最初の頃、私は大学院を休学して「休養する」という選択をすることに対し、大きな後ろめたさや不安感を抱いていました。
卒業が1年遅れてしまう焦り。大学仲間や両親への申し訳なさ。思うように頑張れない自分への嫌悪感。「休んで良くなる見込みはあるのか?」という不安……。
いろんなネガティブ感情が渦巻き、休養しなければいけない自分を認めることができなかったのです。
しかし途中で、考え方を変えました。

焦ったり、不安になったりしたところで、症状回復が早まるわけではない。
どうせなら“休学という名のバカンスを楽しむ”くらいの気持ちで、マイペースに過ごしてみようかな。
そのようにして考え方を変え、心のゆとりが生まれてからは、より症状が軽減されました。
仕事や学校をお休みする方は、自分に罪悪感を抱いたり、いろんな不安を感じたりしやすいと思います。
でも、少しだけ勇気を出して自分を許し、認めてあげることも大切ではないでしょうか。
その勇気はきっと、あなたの心と体を穏やかに、そしてラクにしてくれるはずです。

他者への相談は慎重に
うつ病を発症した初期の頃、私は病気の相談を誰にもしていませんでした。
症状が出るきっかけとなった出来事を他人に知られたくない気持ちが強く、ずっと一人で抱え込んでいたのです。
しかし、日ごとに症状が悪化して日常生活が送れなくなってきたため、今の状態や思いを身近な人に話してみることにしました。
その時に言われたのが、以下の言葉でした。

そんなことでメンタルやられるとかやばすぎ~!!(笑)
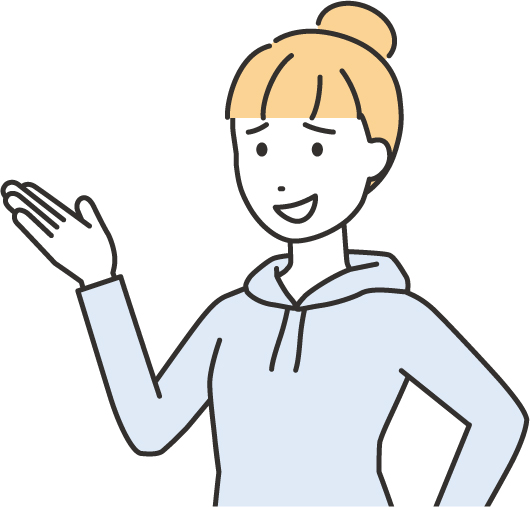
なんでもっと相手のことを考えて行動できないの?おかしいんじゃない?

え?うつ病?ただの情緒不安定やん(笑)
これらの言葉たちがきっかけで、ずっと抱え続けていた“自責の念”や“自己否定感”はそれまで以上に大きくなりました。
症状も輪をかけてひどくなり、「相談なんてしなければ良かった……」と、いろんな人に話をしたことを後悔したほどです。
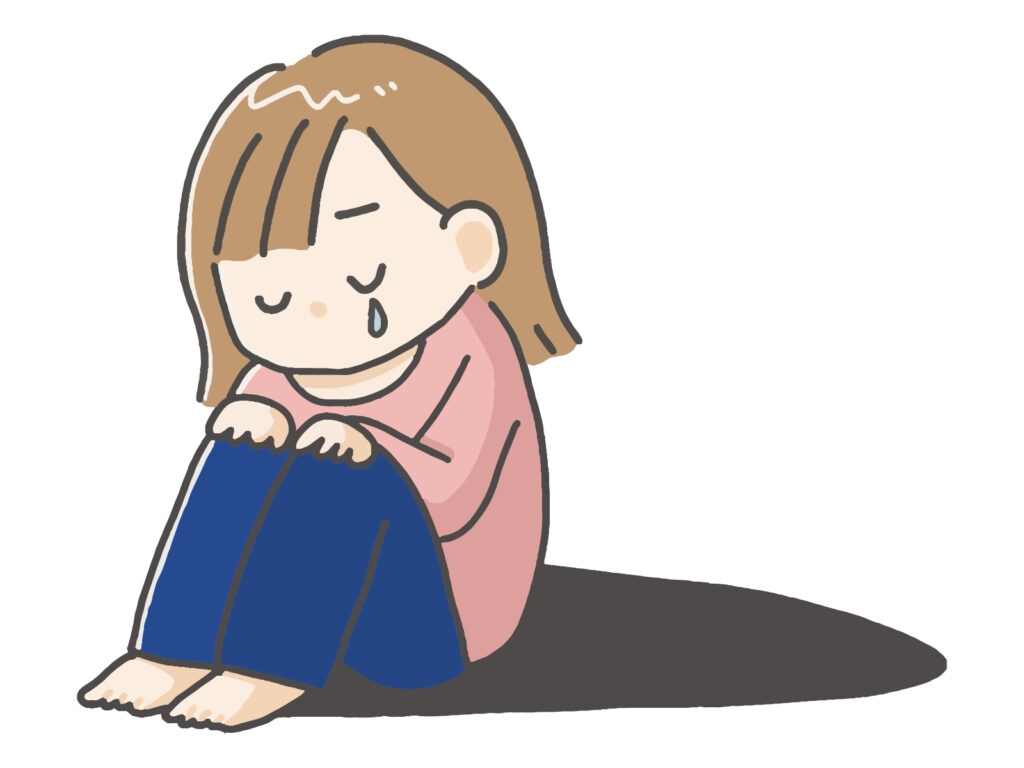
うつ病患者さんは年々増加傾向にありますが、メンタル疾患に対する社会的偏見は、未だに強く残っていると感じます。
たとえ専門知識がある方でも、心無い言葉を平気で発する方も多いです※③。
他者と話すことで心が軽くなったり、悩み解決への糸口を見出したりできる場合も多くあるのは事実です。
しかし、相手の出方次第では、余計に心が辛くなってしまう可能性もゼロではないということは、頭の片隅に入れておくべきだと思います。
誰かに相談を持ちかける場合は、相談相手やタイミング、話す内容などを慎重に見極めた上でおこなうようにすることをおすすめします。
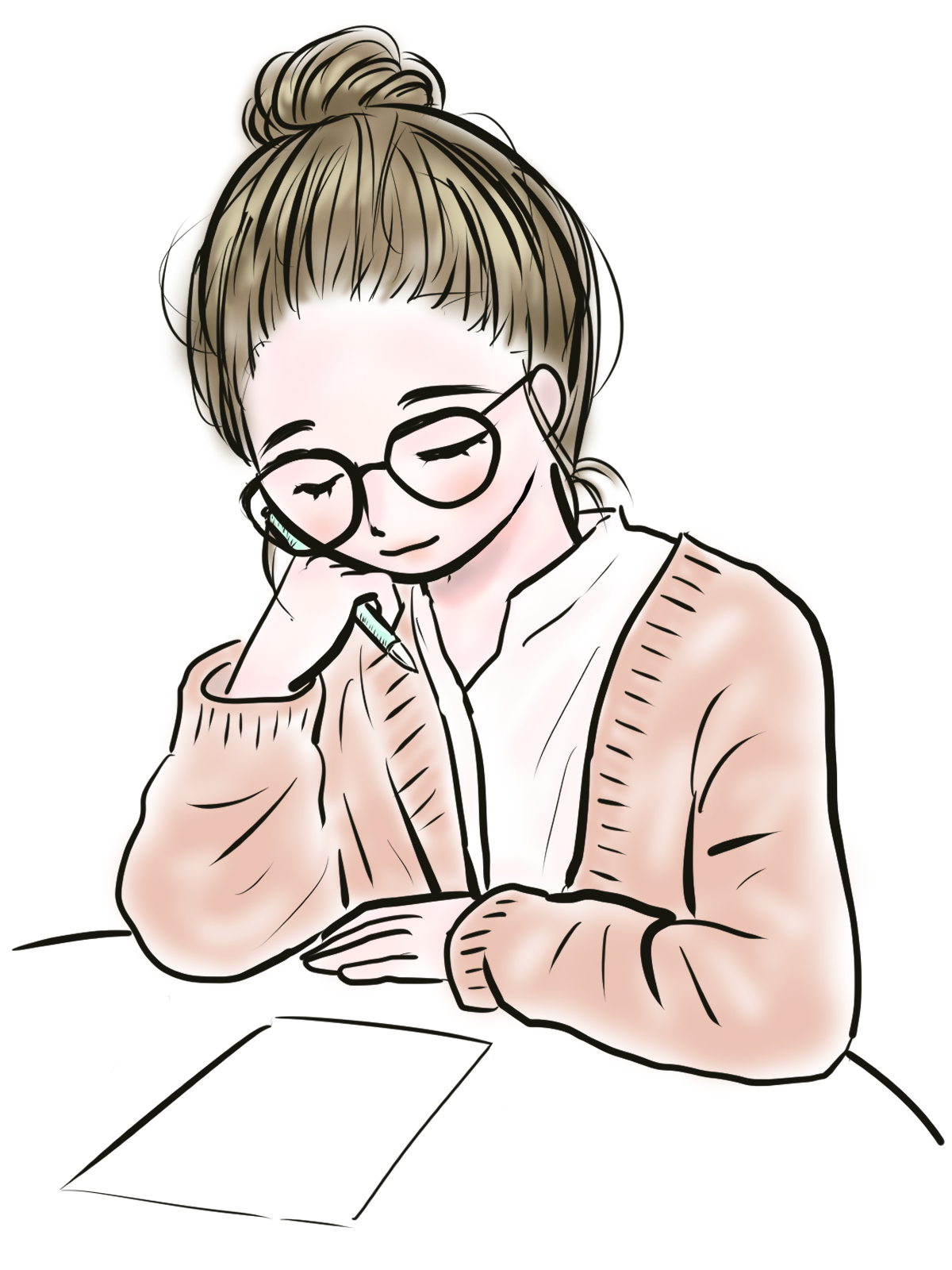
※③:上記の言葉は、心療内科医、カウンセラー、福祉関係の仕事をしている方に言われた言葉でした。
クリニックの診察は短い
心療内科への通院経験がある方はご存知だと思いますが、メンタルクリニックの診察は、基本的にかなり短時間です。
初診は詳しい症状や状態を知る必要があるため、どのクリニックも15分から30分ほどの時間を割いてくれます。
しかし、2回目以降の診察は、よほどのことがない限り5分から10分くらいで終わります。
- 最近のコンディション
- 前回の診察からの変化
- お薬の服用状況
- 睡眠・食事の状況
基本的には、上記の情報を患者から聞き出し、お薬や次回の受診日を調整するのみです。
今までいろいろなクリニックに行きましたが、どのクリニックもこのパターンでした。

クリニックは「患者さんから聞いた症状や状態をもとに診断を下し、お薬を出す場所」です。
そもそも全体的な患者数が多いこともあり、時間をかけて話を聞いてくれる医師は、あまり多くありません※④。
私も最初、このような診察スタイルが主流だとは知らなかったので、あまりの短さと簡潔さに少し戸惑いを覚えました。
「専門知識がある人にゆっくりと話を聞いてもらいたい・相談したい」という方は、カウンセリング機関を訪れるようにしましょう。

※④:とはいえ、私が現在通院しているクリニックは、最低10分は診察時間を確保して話を聞いてくれるので、医師のスタンスによって例外はあると思います。
受けて良かったカウンセリング
うつ病治療において、薬の服用と同じくらい欠かせないのが「カウンセリング」です。
カウンセリングを通じて思考や行動の癖を見直すことで、円滑な対人関係の構築やメンタルの安定・回復を目指し、うつ病の再発を防ぎます。
私は大学院を休学以降、約1年間カウンセリングに通いました。
そして、思考の癖や物事の捉え方、過去の出来事などと向き合い整理する作業(いわゆる“認知行動療法”というものです)をおこないました。
その結果、私はカウンセリングを通じて、自身の人生をかなり前向きに捉えられるようになったように思います。
家族関係の改善や自己肯定感の向上にもつながりましたし、それまで以上に軽やかな毎日を過ごせるようになった気がします。
カウンセラーや施設職員の方との意思疎通がうまくいかず、嫌な思いをしたこともありましたが、カウンセリングそのものはとても価値ある経験だったと思います。

自身の癖や弱点、過去の辛い経験と向き合う作業は、決して容易なものではありません。
いろんなことを考察・分析しなければいけないので、かなりの労力を使いますし、それ相応の心の痛みや苦しみも伴います。
しかし、時間と労力をかけた分だけ、今後の人生はより明るいものになると思います。
カウンセリングに通う元気がなかったり、自宅近くに良い機関がなかったりする場合は、ネット情報や書籍を参考に自分で認知行動療法をおこなうこともできます。
何かをする心の余裕が出てきた方は、ぜひ挑戦してみてほしいです。
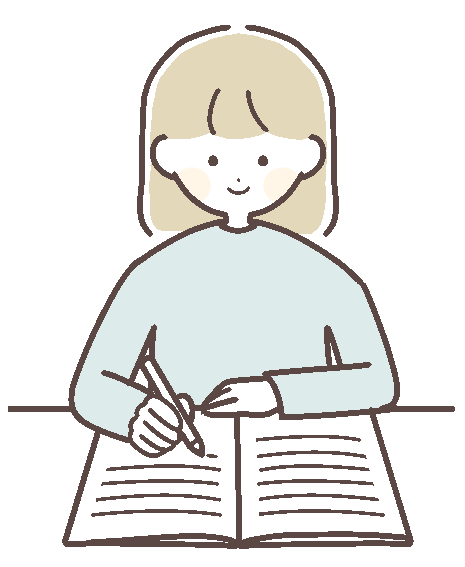
寛解した現在
この章では、うつ病発症から4年が経ち、ある程度症状が回復して「ほぼ寛解」となった現在の様子を紹介します。
症状や通院・服薬のことはもちろん、発症から4年経った今だからこそ語れる「うつ病の方におすすめしたい生き方」も紹介しています!
症状の種類・程度
うつ病発症から4年が経った現在(2025年)は、症状がかなり改善しました。
「自分がうつ病である」という事実を忘れて過ごす日もあるくらいで、一時期のことを思うと、心も体もかなり楽です。
もちろん人間なので、生きることがしんどくなる時や、やる気が出なくなる時もあります。
けれどそれは、うつ病の影響ではなく、ごく一般的なメンタル不調かなと思います。

ただし、疲れやすさや過眠傾向などの一部の症状は、4年が経った今でも根強く残っています。
私の場合、うつ病を発症する前から複数の精神疾患や生きづらさを抱えていたため、その影響がとても強いのだと思います。
メンタルが落ち気味の時は、いろんな症状が出てしまうことに嫌気がさしたり、自己否定をしてしまったりすることも少なくありません。
けれど、そんな私も「大切な私の一面」ですし、いろんなしんどさがあるからこそ学べること、得られるものもたくさんあるなと感じます。
ネガティブな部分よりもポジティブな部分に目を向けながら、これからも上手にうつ病と付き合っていきたいなと思っています。

症状が軽くなったきっかけ
先ほどの章で「外出が増えてきた(症状が軽くなって少しずつ前向きになれた)のは大学院の休学から4~5か月が経った頃」だというお話をしました。
そのタイミングで症状を軽くできた大きな理由は「症状回復に対する執着を手放したから」だと思っています。
大学院を休学し始めた頃は「1日でも早く症状を軽くしなければ!元気にならなければ!」という気持ちが強く、常に不安や焦りと闘っているような状況でした。
しかし、ある時「もうどうでもいいや」と、良い意味で執着を手放すことができたのです。

ゆっくり休みながら今できることを粛々とこなしていれば、それでいいんじゃない?
そのように考え方を変えてみたら、少しずつ症状が軽くなり、徐々に意欲やヤル気が湧いてきたのです。
焦ったり、不安になったり、1日も早い回復を願ったりする気持ちはよくわかります。
けれど、焦ったところで回復が早まるわけではありませんし、回復を早めようと頑張りすぎてしまうことが、症状の悪化につながる可能性もあります。
肩の力を抜いて「頑張りすぎないことを頑張る」ことが大切かなと思います。

回復を実感した出来事
「ひとつ大きな峠を越したかも?」と実感できたのは、うつ病の診断が下りてから1年半が経った頃でした。
なぜそのタイミングだったかと言うと、うつ病を患ってからはじめて宿泊旅行に挑戦できたのがその頃だったからです。
私はもともと旅行好きだったので、ある程度症状が回復してからは「もう一度旅行に行きたい」という思いが強くなりました。
けれど、体調面の不安が大きく、行動を起こす勇気がなかなか持てなかったのです。
その不安を克服して「ちょっと頑張ってみようかな」と一歩を踏み出せたのが、発症から1年半後のタイミングでした。
その旅行は、家族の付き添いもあって問題なく楽しむことができ、心身のリフレッシュにもつながりました。
「ついにここまで回復できたんだ!」という喜びも大きく、今まで以上に自信を持てるようになった気がします。
それから徐々に行動範囲が広がり、いろいろなことに挑戦できるようになったので、私にとってはこれがひとつの転機になったかなと思います。

医療機関への通院状況
うつ病発症から4年が経ち、症状も随分と軽くなりましたが、心療内科通いは今も続けています。
とはいえ、最初の頃のように月に1~2回通うことはほぼなくなり、2~3か月に一度の診察で問題なく過ごせるようになりました。
ただ、うつ病の症状自体はかなり改善されていますので、ここ最近の診察ではうつ病の話題はほぼ出ず、それ以外の精神疾患や生きづらさに関する話をすることが多いです。
もしうつ病のみの診察だったら、2年~3年ほどで終診になっていたのではないかと思います。

お薬の服薬状況
うつ病発症から4年が経った今でも、お薬の服用は続けています。
以前は1日2回服用したり、複数種類のお薬を服用したりしていましたが、現在は1日1錠の服用で過ごせるようになりました。
しかし私の場合、現在のお薬は「うつ病以外の精神疾患や生きづらさを緩和させるため」に飲んでいる側面が強いです。
医療機関への通院状況の項目でもお伝えしましたが、もしうつ病治療だけならば、終診のタイミングで服用をやめていたように思います。
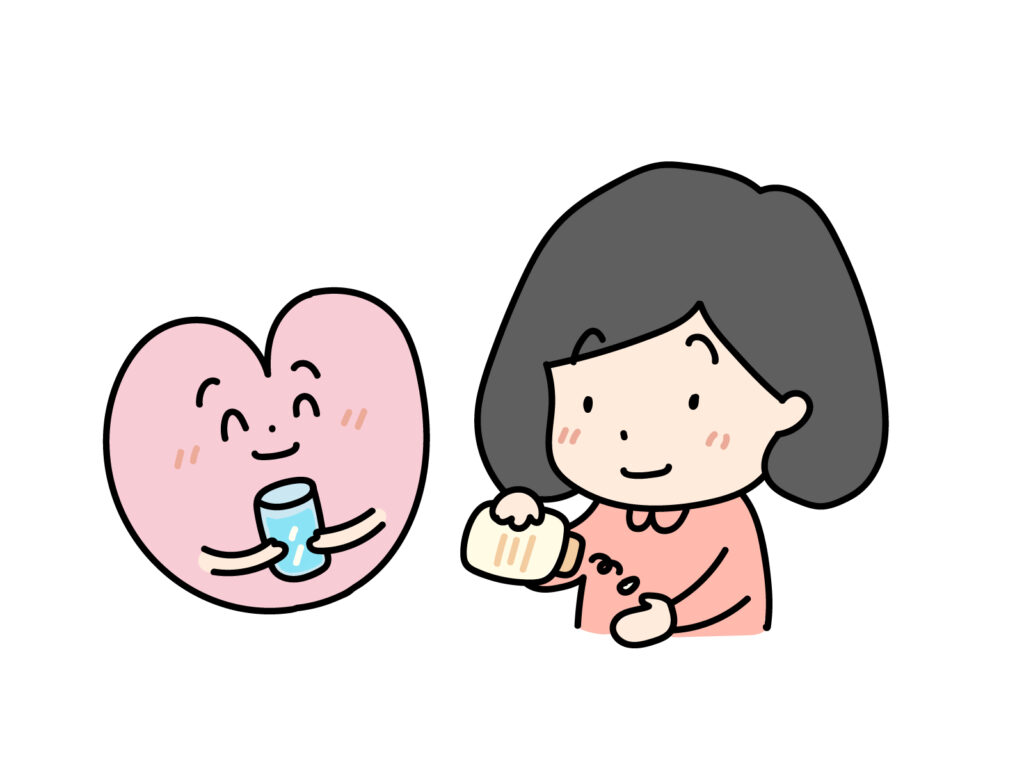
おすすめしたい“生き方”
私は考えること・調べることが大好きなので、この4年間で、うつ病やメンタルケアに関する書籍を100冊以上読み漁りました。
おそらく、現時点で世に出回っている“うつ病対処法”はほぼすべて網羅したと思うのですが、その情報の中から手軽に取り組めそうなセルフケアをいろいろ試し、心身の変化を観察しました。
その中で変化を感じたセルフケアについては、いつかまとめてnoteで公開予定なのですが、それらのセルフケアに共通すると感じるのは「思考ではなく心の感覚を大切に生きる」ということです。
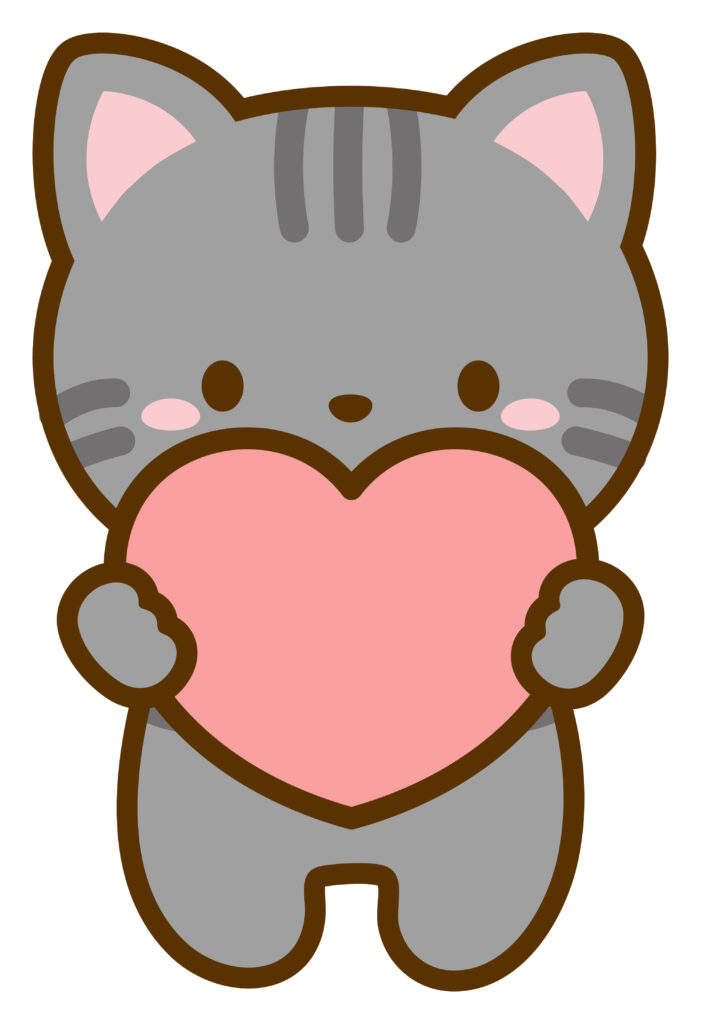
「栄養バランスが整った食事にしなければ」と思うのではなく、その時「食べたい」と感じたものを食べる。
「1日30分は運動しなければ」と思うのではなく、「なんかちょっと体を動かしたいな」と思った時に、好きな運動を心が満足するまでおおこなう。
「人に迷惑をかけたくない・申し訳ない」と思うのではなく、「〇〇さんを頼りたい・助けてほしい」と思った感覚に従って行動する……。
つまり、頭で物事を考えて判断するのではなくて、心の感覚を最優先にひとつひとつの行動を選択していくのです。
これは、うつ病回復だけでなく、生きづらさの解消にもつながる心構えだと思います。
「自分は今何をしたいのか?」「これは本当にしたいことなのか?」ということをいちいち自問自答しながら、心の感覚を鍛えていくことが大切だと思います。
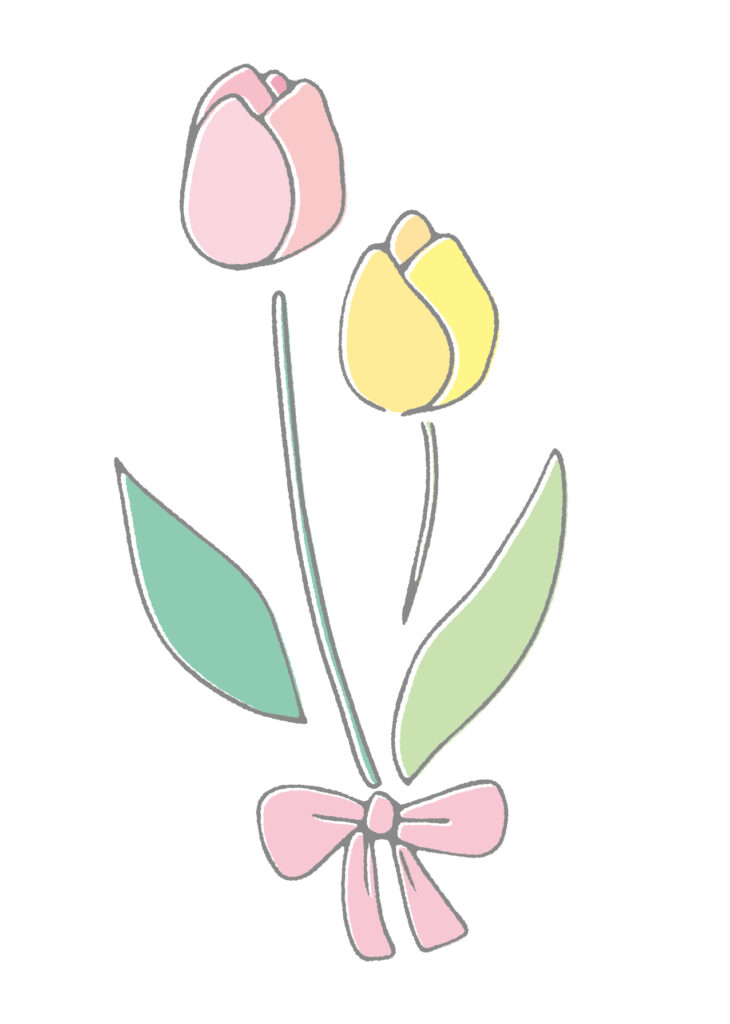
まとめ
本記事では、うつ病の初期症状や治療方法、回復過程について、自身の体験談をもとに掘り下げてみました。
さまざまな症状に苦しみ、人生のどん底を経験した私ですが、発症から4年が経って随分と状態が回復しました。
だから、今この記事を読んでいるあなたもきっと大丈夫です。
今はとにかく、できるだけ心身を休ませて、今まで頑張ってきたご自身をたっぷりと労ってあげてください。
そして、ご自身の気持ちを最優先に考え、心穏やかな日々を過ごすことを大切にしてください。
そうすれば、いつかまた、笑顔で人生を楽しめる日が来るはずです。
ベタな言葉ですが、止まない雨はありません。あなたの健康と幸せを、心から願っています。




