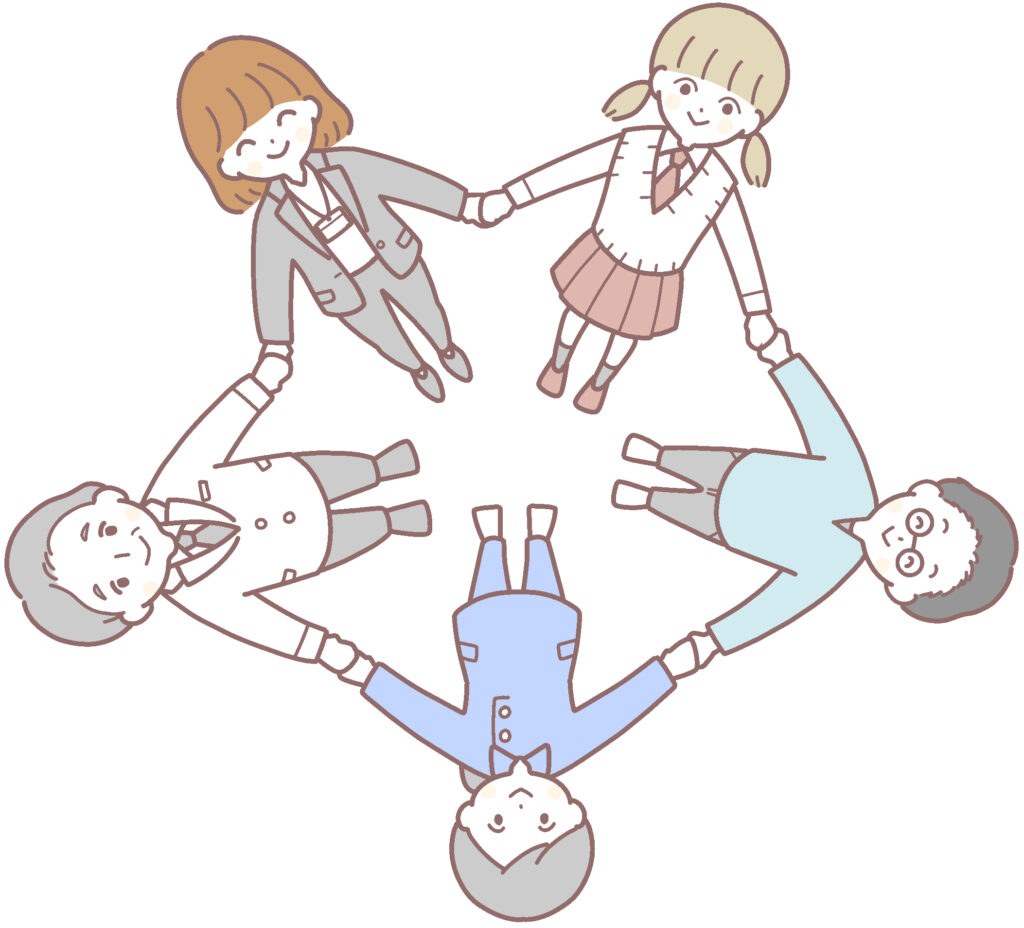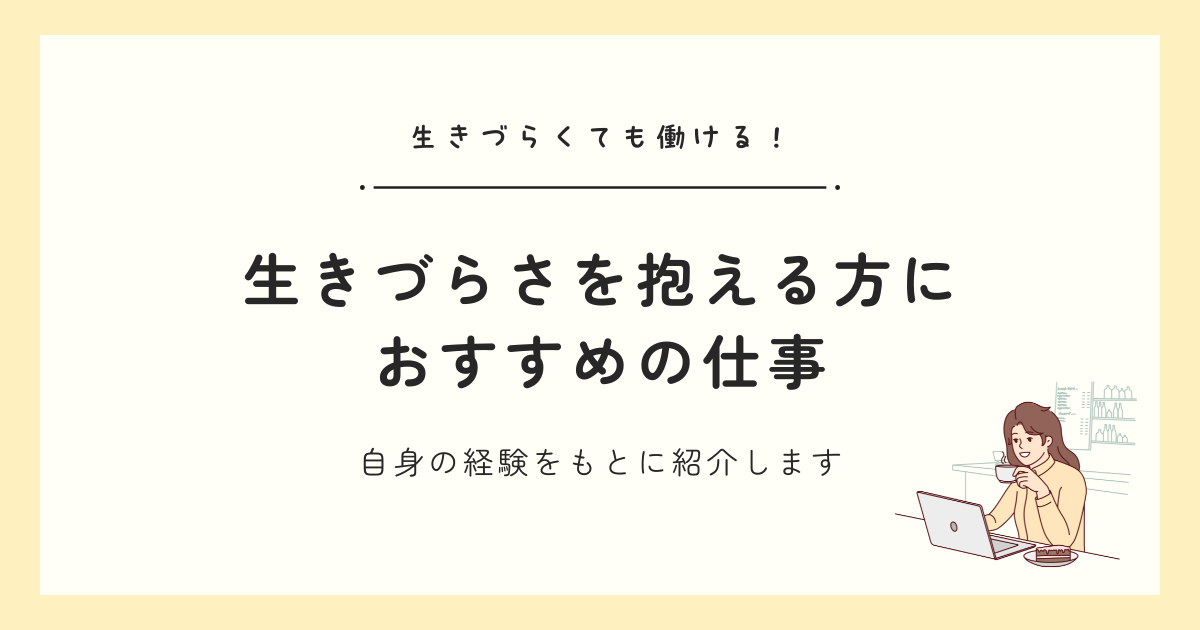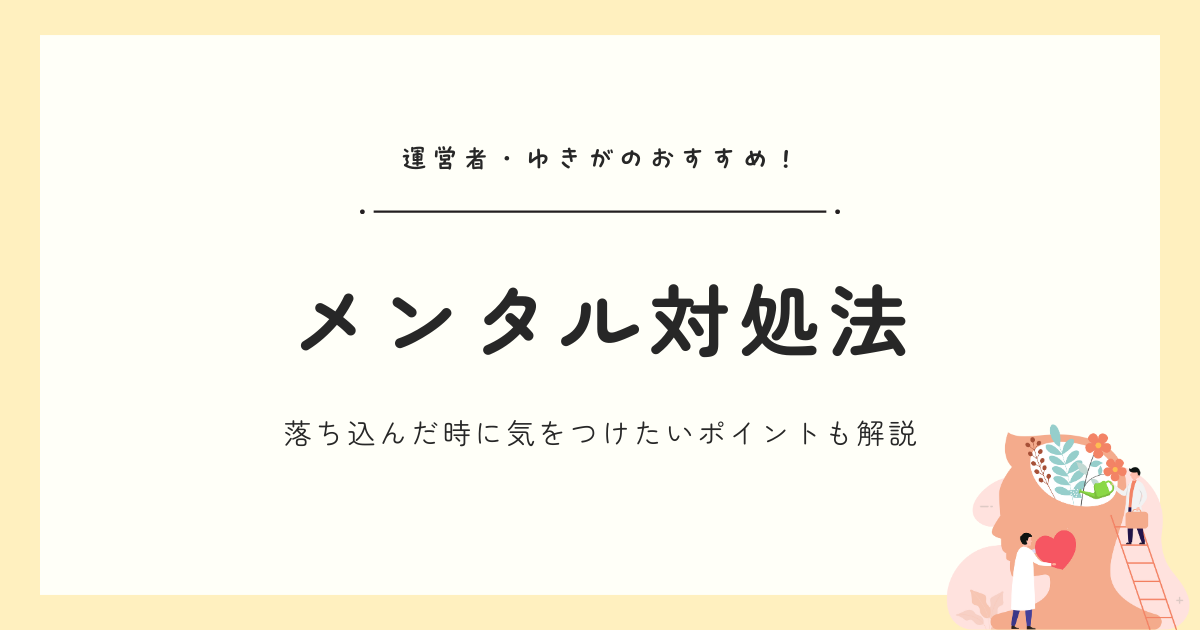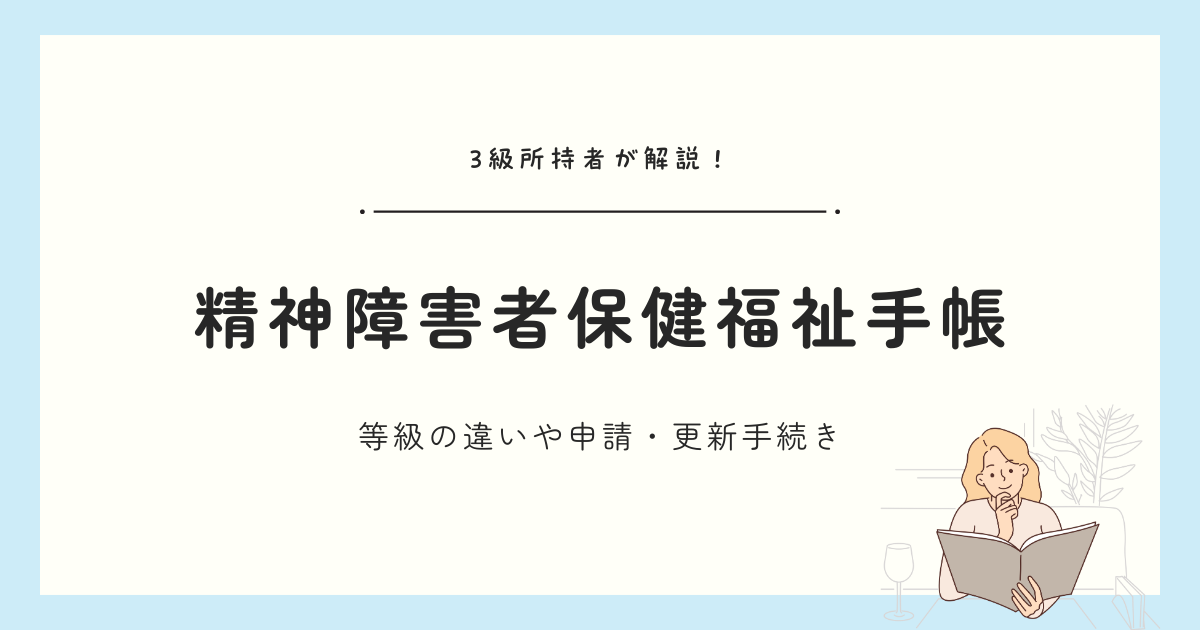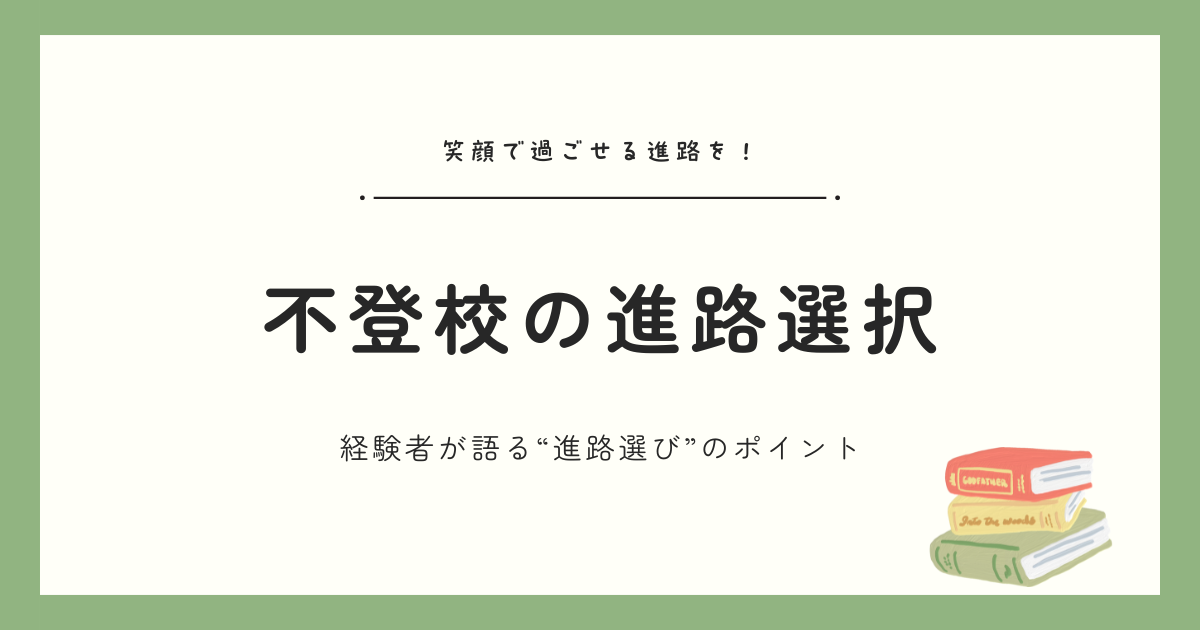HSPとは?特徴や種類、診断や発達障害との違いについて“HSP当事者”がまとめました

皆さんは「HSP」という言葉をご存知でしょうか。
HSPは“敏感で繊細な気質を持つ人”を指す言葉で、当ブログのテーマである“生きづらさ”と深い関わりがあります。
しかし、ここ数年で広まった新しい概念なので、「詳しいことはよく知らない……」という方も多いかもしれません。
そこで本記事では、HSPの特徴や種類について、HSP歴20年以上のブログ運営者(ゆき)がわかりやすくまとめてみました。
運営者自身の体験や症状を例に挙げながら綴っています。
この記事を読むと、あなたの“生きづらさの正体”が紐解けるかもしれません……!
HSPとは
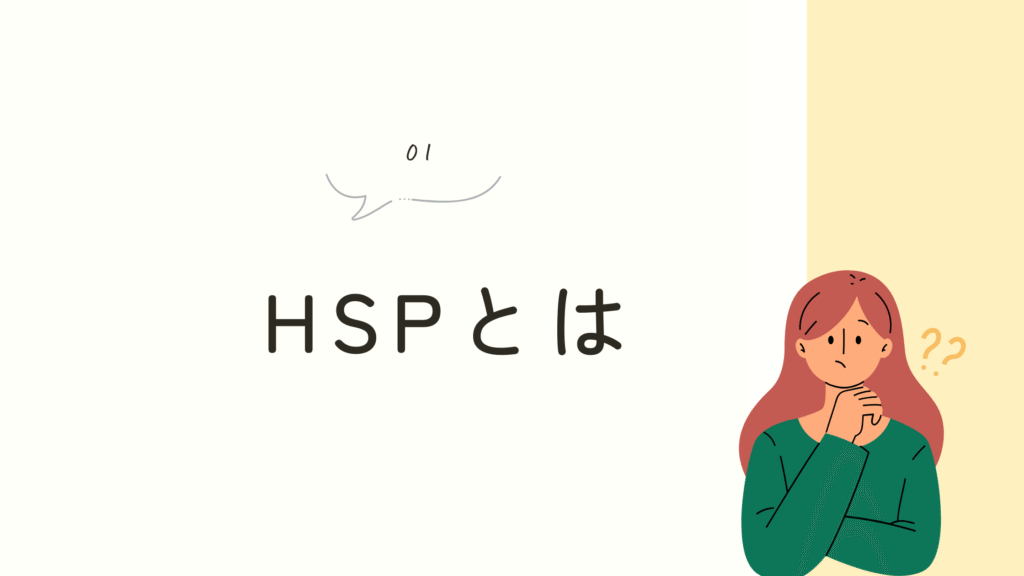
この章では、HSPの特徴や種類などを簡単にまとめてみました。
「HSPの基礎を知りたい!」という方は、ぜひ参考にしてくださいね。
HSP=敏感かつ繊細な人
HSP(Highly Sensitive Person)とは、光や音、匂いなどに敏感に反応し、日常生活や人間関係において繊細な感覚を持つ人のことを指す概念です。
1990年代の後半に、アメリカの心理学者「エレイン・N・アーロン」が提唱しました。
HSPの方は、なんと、非HSPの方と比べて100倍から1000倍の感覚容量を持っているというデータもあるそうです!
HSPは5人に1人の割合で存在しますが、人間のみならず、犬や猫などの動物にもHSPが存在するそうですよ。

「100人のうちの20人がHSP」だと考えると、気持ち的に少し安心できますね。
HSPは病気ではなく「気質」
HSPは病気ではなくて、あくまでも“その人が持つ気質”だと考えられています。
そのため、病院へ行って医師の診察を受けたとしても、うつ病や発達障害などのように診断が下りることはありません。
しかし、精神障害や不登校、ひきこもりなど、何かしらの“生きづらさ”を抱えている人は、HSPの気質を持っているケースが多いと言われています。
もしお心当たりがある方は、以下の【HSP診断チェックリスト】をぜひお試しください。

ブログ運営者の私も、不登校やひきこもり、うつ病やパニック障害の経験があるHSP当事者です。
HSPの対処法は、上手に向き合うこと
HSPは、その人が生まれつき持っている性格と、幼少期の生育環境が合わさって生まれるものだと考えられています。
年齢を重ねるにつれて、敏感さの度合いに変化が生まれる可能性は十分あると思います。
しかしHSPの気質自体は、基本的には生涯変わることはありません。
- 自身の敏感さとしっかり向き合い、上手に受け入れながら生きて行くー。
それが、HSPと付き合う最大のコツだと思います。

「治す・克服する」のではなくて「上手に受け入れて生きていく」ことを意識しましょう!
子どものHSP(HSC)もある
アーロン博士は、HSP気質を持つ子供のことを「HSC(Highly Sensitive Child)」と定義づけています。
HSPと比べると認知度は低いですが、ここ数年で徐々に日本でも広まりつつある言葉です。
HSCのお子さまを育てる際に重要なのは、他のお子さまと比較せず、特殊な気質を認め、その気質を良い方向に伸ばしてあげることだと思います。
大人になってから敏感さと向き合い、生き方を考え直すのは、けっこう大変です。
なるべく早い段階でお子さまの特性を理解し、その子に合った生き方をサポートしてあげるのがおすすめかなと思います。

HSCのお子さまを対象とした『子育て本』を参考にするのもおすすめです!
HSPと発達障害との違い
「さまざまな物事に過剰反応してしまう」というHSPの症状は、発達障害の特性とよく似ています。
しかし、原因や診断方法がそれぞれで異なります。
- 病気ではなく「気質」なので、医師の診断はつかず、セルフチェックで対応できる
- さまざまな物事に過剰反応してしまうのは、感情処理をおこなう「扁桃体」という脳の部位が人よりも強く働いているため
- 「精神障害(病気)」の一種として考えられているので、医師の診断が必要
- さまざまな物事に過剰反応してしまうのは、脳機能の発達に偏りがあるため
このように、HSPと発達障害はまったくの別物ですが、症状や特性そのものは似ている部分が多くあるため、違いを判断するのは難しいです。
自身(もしくはお子さま)の生きづらさについて詳しく知りたい方は、医師やカウンセラーなどの専門家に相談してみることをおすすめします。
HSP診断:セルフチェックリスト
「自分がHSPかどうか知りたい」という方のために、アーロン博士が作ったHSPセルフチェックリストを引用してみました。
以下の23の項目のうち「YES」が12個以上あれば、HSPの気質があると考えられています。
参考文献:『ささいなことにもすぐ「動揺」してしまうあなたへ。』エレイン・N・アーロン(訳:富田香里)

ちなみに私は、19個当てはまります。生粋のHSPです(笑)
HSPの特徴
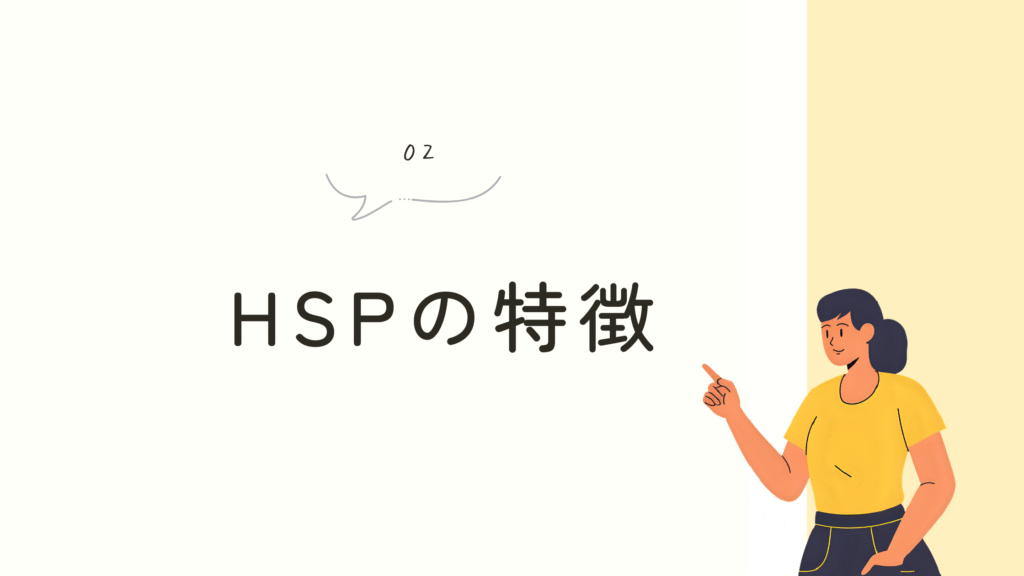
アーロン博士によると、HSPには「DOES(ダズ)」と呼ばれる4つの特徴があるのだそうです。
これらの特徴や、特徴に基づく症状をどのように活かし、自分の長所としていくかを考えることが大切です!
HSPの特徴①:物ごとを深く処理する(Depth of processing)
HSPさんは、物事を深く考えやすい傾向があります。
さまざまなことを瞬時に感じ、分析し、他の人が気に留めないようなことまでひたすらに追求します。
- 他人の言動を深読みしすぎて、寝る前に一人反省会をしてしまう
- 旅行に行く時、最悪の事態を想定して複数のプランを考えないと気が済まない
- 哲学的なことが好きで「人はなぜ生きるのか」みたいなことを考えがち
ものすごくシンプルに言うと「1の出来事に対して、100くらいの考え事をしてしまう」というイメージです。

自分でも無意識のうちに頭が働いているので、止めたくても止められません……。
HSPの特徴②:刺激を受けやすい(Overstimulation)
たくさんの刺激を受けやすいのも、HSPさんの特徴のひとつです。
- 知らない場所に行ったり仕事や学校の環境が変わったりすると、ものすごく疲れる
- 匂いや音、食べ物の味などに敏感に反応する
- 予定が詰まっていると、頭がパンパンになって心がしんどく感じる
非HSPの人が「そんなに些細なことも気になるの!?」とびっくりしてしまうほど、さまざまな刺激を受けています。
大きな音や人混み、急な予定変更などの刺激が続くとキャパオーバーになって、疲労で動けなくなることもしばしば……。

私は特に、薬の副作用が出やすい傾向があるため、自分に合う薬が見つかるまですごく大変です。
HSPの特徴③:感受性や共感性の強さ(Emotional intensity)
HSPさんは共感力が高く、他人の気持ちを察しやすい特徴も持っています。
- 悲しいニュースやSNSの誹謗中傷を見るだけで気持ちが重くなる
- ドッキリ企画のバラエティ番組や、アクション多めのドラマや映画が苦手
- 他人が怒られているのを見ると、自分が怒られたような気持ちになって苦しくなる
相手のちょっとした仕草や言葉づかいを無意識のうちに分析しているので、相手の考えていることが手に取るようにわかります。
相手の気持ちがわかってしまうことで、良くも悪くもその人の感情に左右されてしまうHSPさんも少なくありません。

私の場合は、怒りや不機嫌さを抱えている人に左右されやすく、ピリピリしている人が同じ空間にいるだけでものすごく疲れます……。
HSPの特徴④:繊細な感覚(Sensory sensitivity)
HSPさんは、鋭くて繊細な感覚を持っています。
- 「なんか今日、職場の空気重いかも?」という感じで、目に見えない雰囲気が直感的にわかる
- 照明の明るさや匂い、部屋の温度の微妙な違いが気になって仕方ない
- 書類をぱっと見ただけで、誤字脱字や文章のバランスの悪さなどがすぐにわかる
非HSPの方がスルーするような細かいことでも、自然とアンテナが働きます。
どの分野で鋭い感性を発揮するかは人によってさまざまですが、自分が秀でている感性を把握し、仕事や日常生活で上手に生かしている人も多いです!

私の場合、他の方のブログやSNSを見た時に「この文章はAIだな……」ということが一瞬でわかります。
HSPの種類

HSPは4つの種類にわかれていて、それぞれ微妙に特徴が異なります。
以下で詳しく説明します。
HSPの種類①:内向型HSP(HSP)
HSPの中で一番オーソドックスかつ人数が多いのが内向型HSPで、ベーシックなHSPさんです。
- 一人の時間がないと心が疲れてくる
- 慎重で、じっくり考えてから行動したい
- 話すことよりも、文章を書くことのほうが得意
繊細さと敏感さゆえに、刺激を求めず穏やかに過ごすことを好みます。
長時間の外出や、大人数の飲み会やイベントに疲労やストレスを感じやすい傾向にあります。

私は、純度100%のベーシックHSPです(笑)
HSPの種類②:外向型HSP(HSE)
内向型HSPと対になるのが「HSE」(Highly Sensitive Extroversion)です。
- 人と会うのは好きだけど、後からどっと疲れる
- 「行きたい気持ち」と「しんどい気持ち」が同時にある
- 繊細さが表に出ないので、社交的な人間だと誤解されやすい
HSEの特徴を持つ方はHSPの約3割と言われており、明るく社交的な性格の方が多いです。
内向的な側面を持ちながらも、人と会ったり、話したりすることでエネルギーが湧いてくる方は、HSEの気質を持っていると言えるでしょう。

HSEさんは、面倒見が良くて、人から悩み相談をされやすい方が多い気がします。
HSPの種類③:内向型HSP×刺激追求型(HSS型HSP)
HSS(High Sensation Seeking)型HSPは、繊細ながらも新しい刺激や変化を好む傾向があります。
- 好奇心が強くて、新しいことや刺激が強いイベントにワクワクする
- ワクワクや刺激を楽しむ反面、予定を詰め込みすぎてキャパオーバーになりやすい
- 自己矛盾を感じて落ち込みやすい
繊細さと冒険心を両方持っているため、HSPさんの中で一番葛藤が多いタイプだと言われています。
しかし、好奇心旺盛で学習スピードが早く、独特の視点を持ちやすいという長所もあります!

「刺激を求める気持ち」と「敏感さ」のバランスを意識しながら、無理せず活動することを心がけましょう!
HSPの種類④:外向型HSP×刺激追求型(HSS型HSE)
HSS(High Sensation Seeking)型HSEは、「繊細だけど外向的かつ刺激を求める」という特徴を持っています。
- 新しい刺激・新しい人との出会いが大好き
- 予定を詰めがち → そのあと燃え尽きがち
- じっとしてるより動きたいタイプ
HSS型HSPは、新しい刺激をどんどん求めるため、“飽き性”の特徴も持っていると言われています。
その特徴と敏感体質を理解した上でさまざななチャレンジをすると、活動の幅が広がって楽しく生活できそうです!

エネルギッシュなのはとても素晴らしいですが、仕事も遊びも、詰め込みすぎないように注意です。
まとめ|HSPを知って、より豊かな毎日に!
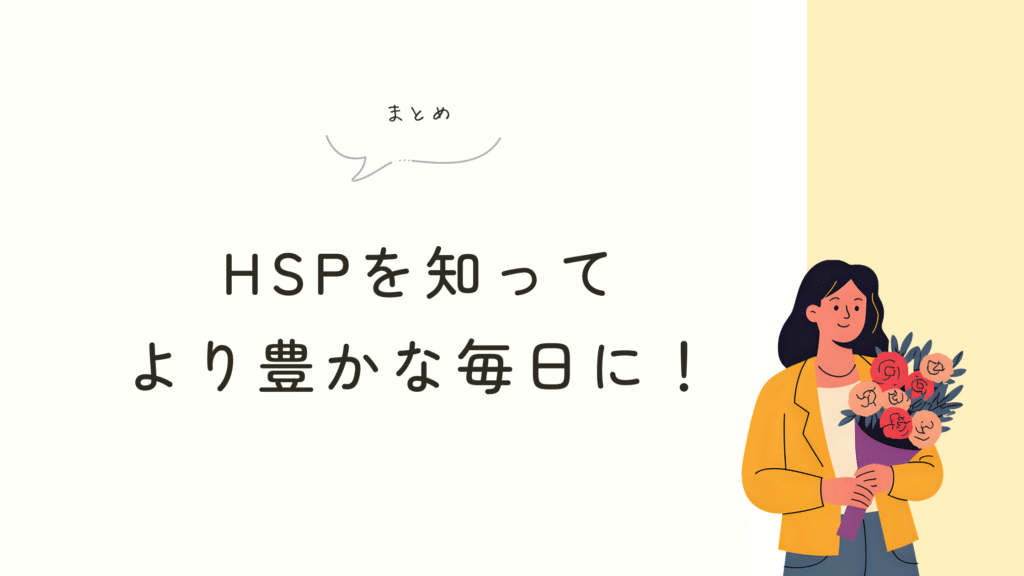
本記事では、HSPの特徴や種類について、HSP当事者の視点からまとめてみました。
ここ数年で、HSPの関連書籍の販売や当事者交流会は急増し、“HSP=生きづらさの代名詞”として語られることも多くなりました。
HSPのことを詳しく知ることで、気持ちが楽になったり、救われたりすることはたくさんあると思います。
もっともっとHSPが広く世の中に知れ渡り、HSPに理解ある社会になっていけばいいなと思います。