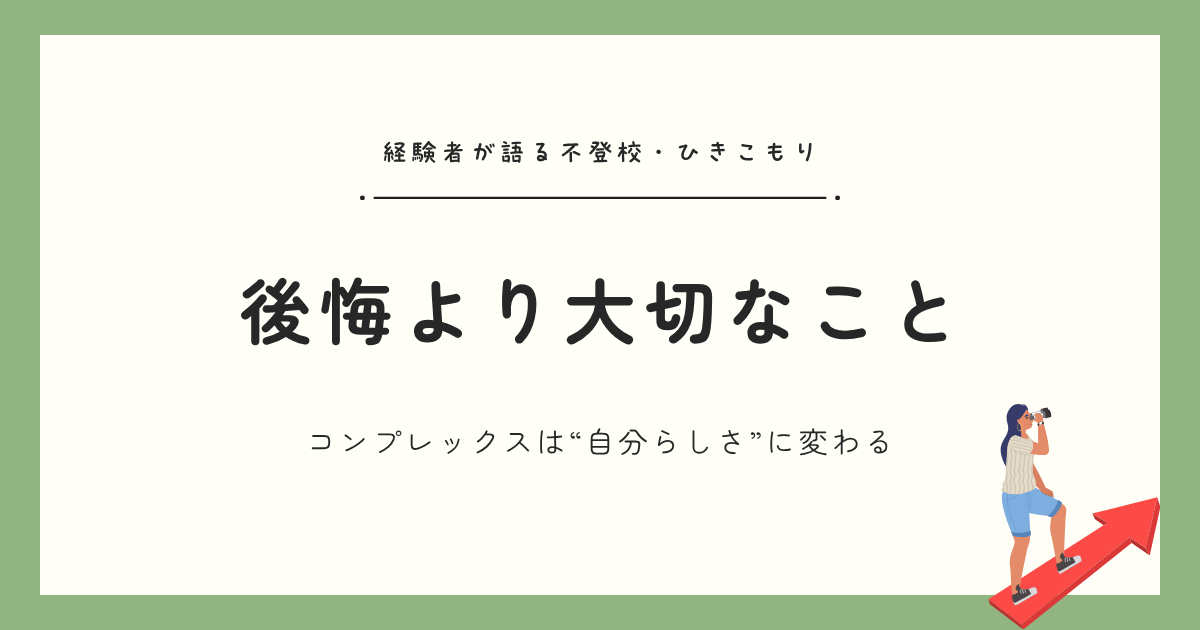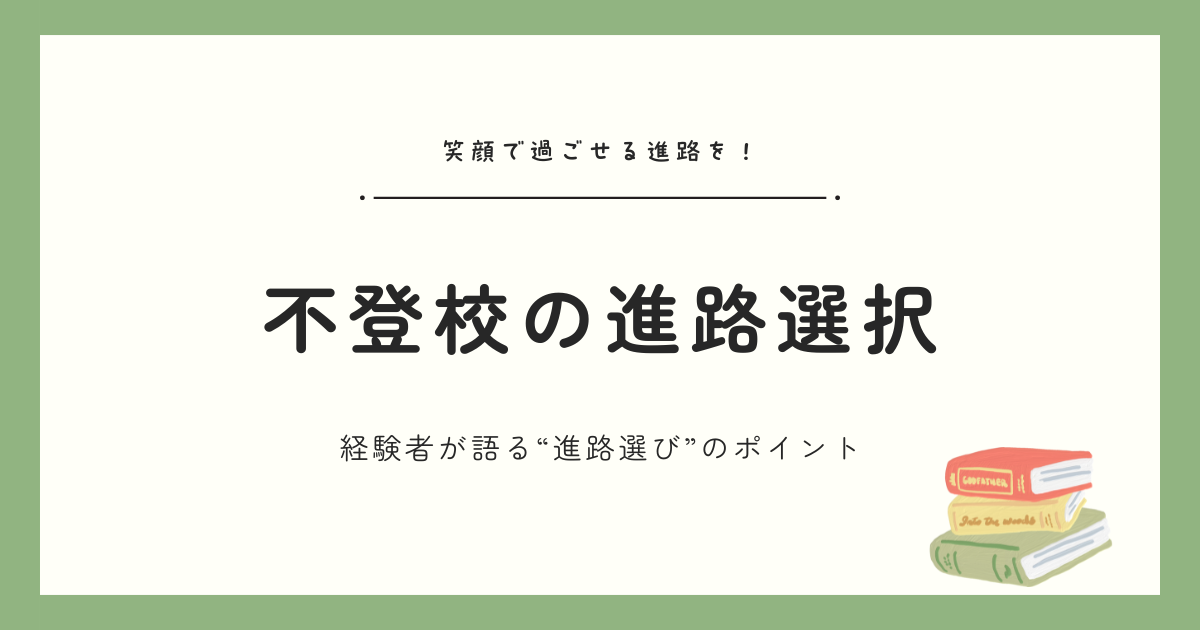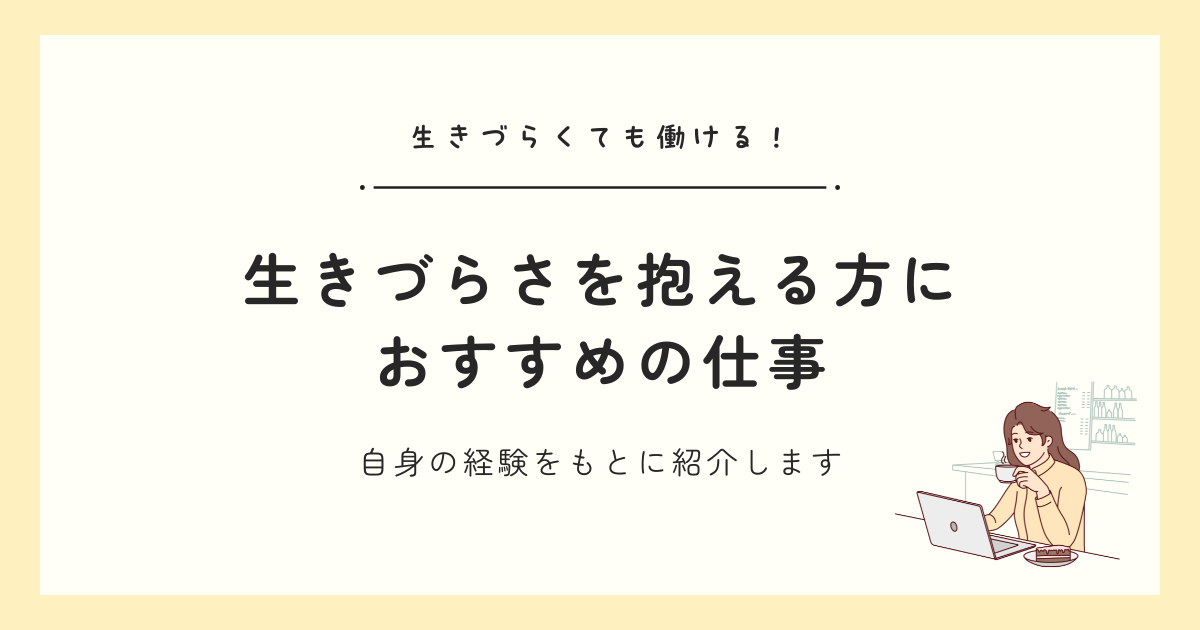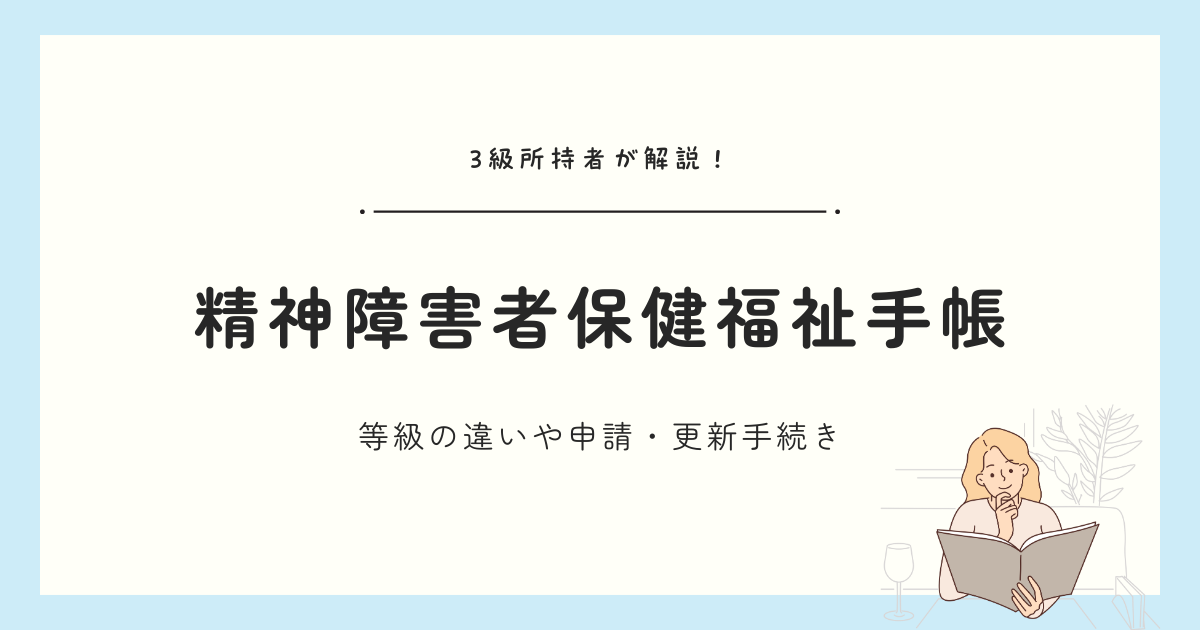親が知るべき不登校の「真の理由」を元当事者がやさしく紐解きます

お子さまが不登校になった時、保護者さまが一番気になるのは「なぜ学校に行けなくなったのか」ということだと思います。
理由がわからないと不安になりますし、どう対処して良いかわからず余計に混乱してしまいますよね。
私は不登校の元当事者・元研究者ですが、その立場で主張したいのは「不登校になる子どもは、なんらかのストレスを抱えている」ということです。
そのため私は、お子さまが不登校になった時にまずやるべきことは「原因探し」ではなく「ストレスへの理解と探求」だと考えます。
そこで今回は、不登校とストレスの関係について、不登校の元当事者・元研究者という独自の視点からまとめてみました。
記事の後半では、中学2年生で不登校になった私が感じていた「さまざまなストレス要素」についても紹介しています。
お子さまの不登校で悩まれている方や、不登校のお子さまを支援されている方は、ぜひご一読ください。
不登校とストレスの関係
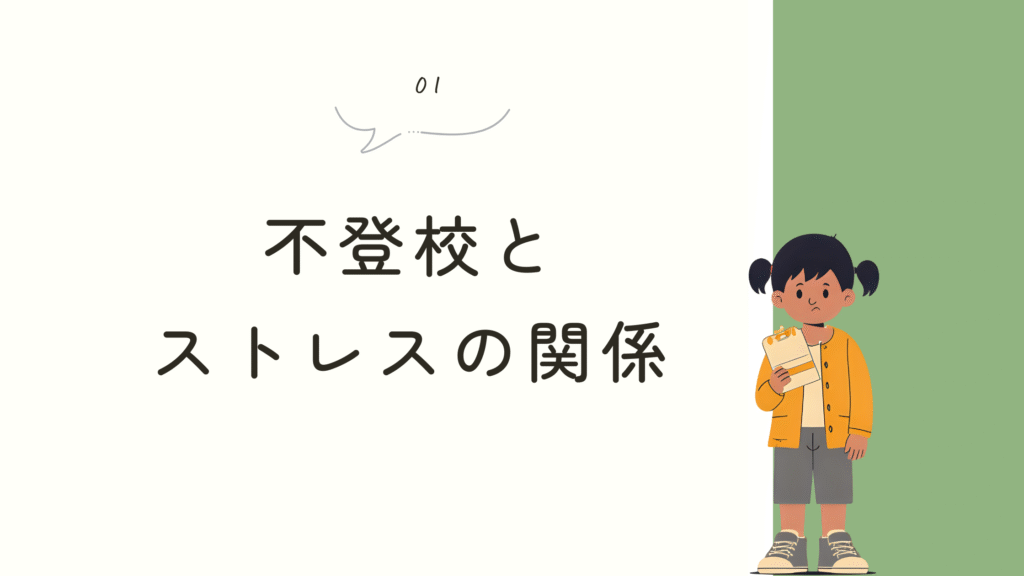
この章では、不登校とストレスの関係について、元当事者・元当事者の視点から掘り下げます。
お子さまの不登校を理解する“一助”となれば幸いです。
不登校になる=ストレスがある
不登校になる一番の理由は、お子さまが日常生活において何らかのストレスを抱えているからだと考えています。
- 学校生活や集団行動
- 友人や教師との対人関係
- 家庭環境(両親や兄弟との関係・生活スタイルなど)
- 地域交流
- 習い事
- 学業面
不登校になるお子さまは、それらの要素に何かしらの心の痛み・苦しみを抱えている状態だと推測されます。
「今現在、子どものストレスになっているもの・ことは何か?」を見きわめ、対処法を考える
それが、不登校のお子さまに対して最初にすべきことだと思います。
不登校はストレスの“大噴火”
不登校は「ストレスの大噴火」だと思います。
どこにも吐き出せずに溜め込んだストレスが、ある日突然、何かのきっかけで“大噴火”するのです。
これは、ひきこもりの方やうつ病患者さんに対しても同じことが言えると思います。
- 友人と喧嘩をしてから学校に行かなくなった
- テストで悪い点数を取ってから学校に行かなくなった
そのような場合でも、その出来事はあくまでも“きっかけ”のひとつに過ぎないと考えるべきだと思います。
長年ため込んできたストレスが、たまたまそのタイミングで爆発しただけの可能性が高いです。
そのため、不登校のきっかけとなる出来事があったとしても、安易にそれを「不登校の原因」として結びつけないことが大切です。
ストレスが複数あるケースも
不登校を生み出すストレスは単一ではなく、複数の事柄が絡み合っているケースが多いです。
そのため、お子さまのストレスをなかなか特定できず、もどかしい時間を過ごす方もいらっしゃるかもしれません。

私自身も、学校生活や親子関係など、さまざまなストレスが絡み合っていて、原因(=ストレス)の特定にはかなりの時間を要しました。
絡まった糸をひとつずつ丁寧に解くように、焦らずゆっくりとお子さまと向き合ってあげてほしいと思います。
“ストレスの正体”は本人もわからない
学校に行けなくなった理由やストレスの正体は、子ども自身もよくわからない
これは、不登校のお子さまを持つ保護者の方に一番知っていただきたい事実かもしれません。
私も、不登校を経験して数年間は、自分の身に何が起きているのかがよくわかりませんでした。
それらをすべて理解し「あの時の私は○○だったんだなあ」と言語化できるようになったのは、20歳で大学に入ってからです。
本人すらも、学校に行けない理由やストレスがわからないし、だからこそ苦しい時期が続く
このことは、一番の“不登校あるある”と言っても過言ではないように感じます。
そんなお子さまの苦しみやもどかしさに寄り添いながら、これからの未来を少しずつ考えていくことが大切だと思います。
体調不良は“ストレス放出”の証
不登校のお子さまの中には、腹痛や微熱、倦怠感などの身体症状に悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私も数々の体調不良に悩まされていたのですが、今思えば「“身体症状”という形で心に溜まったストレスを放出していた」のだと思います。
- 何にストレスを感じているのか?
- なぜ学校に行くことができないのか?
それらを上手に表現できないがゆえ、心にあふれそうなストレスが「身体症状」となってあらわれているのです。
私は、自身の不登校を言語化できるようになって以降、長年付き合ってきた腹痛や吐き気の症状が消えました。
あまり心配しすぎずに、お子さまのしんどさ苦しみに寄り添うことを第一に過ごしてほしいです。
ストレスを取り除けば再登校できる?
不登校の原因となったストレスを取り除けば、再登校できるのでは?
そう思われる保護者さまもいらっしゃるかもしれませんが、それで再登校できるケースは極めて稀だと思います。
不登校が生じた時と同じようなストレス環境にさらされたら、また不登校に逆戻りしてしまう可能性が高いからです。
過去の私は「環境を変えてストレスを取り除けば再登校できるのでは?」という思いから、いろいろな進路を歩んできました。
しかし、ストレスと向き合ったり、自分に合った対処法や生き方を考えたりしていなかったため、不登校や退学を繰り返してしまったのです。

穏やかな人生を送るためには、ストレス除去ではなく“ストレス解明”のほうが何倍も大事だと思います。
たとえ時間がかかっても、お子さまに合った生き方や、ストレスとの向き合い方を考えていきましょう!
私のストレス要因
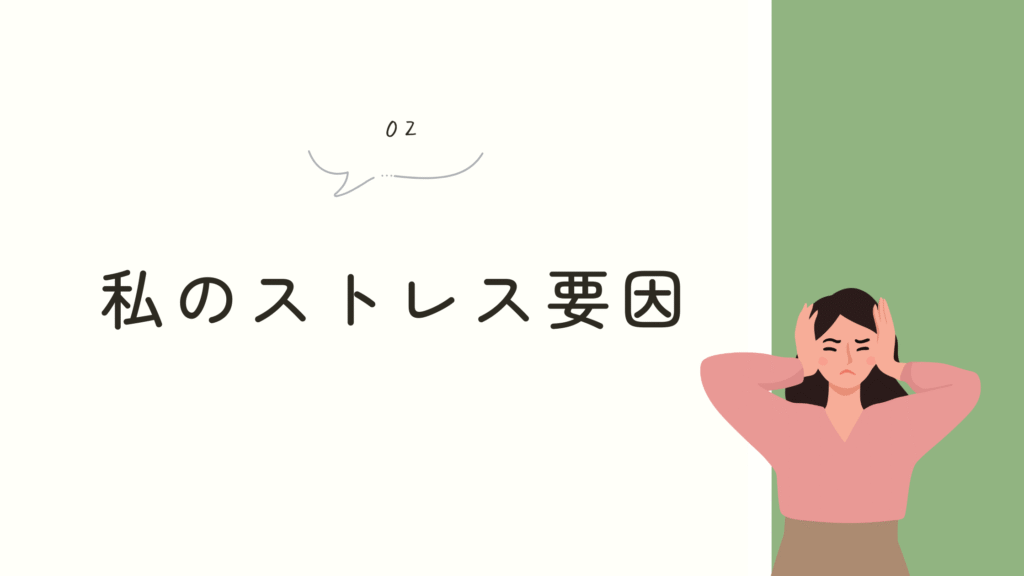
この章では、不登校だった頃の私が「ストレスを感じていた事柄」についてまとめました。
あくまでも一個人の体験談となりますが、少しでもお子さまのストレス要因を探るヒントになれば幸いです。
両親との関係
1つ目は、両親との関係です。
私の両親は「基本的には優しいけれど、事あるごとに何かしらのストレスを与えてくる人たち」でした※①。
- 私の見えるところで大喧嘩を繰り広げる
- 私の気持ちを否定・批判ばかりする
- ちょっとしたことですぐに怒鳴る
- 私の行動をコントロールし、エゴを満たそうとする
今振り返ると、“毒親”と言われてもおかしくない両親だったように思います。

一人っ子でほかに頼れる相手がいなかったことも辛かったですね……。
※①:今は全くそのようなことはなく、とても優しい両親です。
友人との関係
2つ目は、友人との関係です。
小さな頃から、学校や習い事のコミュニティでいじめを受けることが何度かありました。
そのため、対人関係に対する苦手意識が強く、一人で過ごすことも多かったです。
私がはじめて不登校になった中学2年生の時は、クラスメイトとの仲が良かったため、直接的に嫌な思いをすることはありませんでした。
しかし、これまでのトラウマが強すぎて、
- いつか裏切られてしまうかもしれない
- いつか嫌われてしまうかもしれない
という思いが強くあり、友人との交流を楽しむことができませんでした。

価値観や考え方の違いも多く※②「私は誰とも馴染めない」という疎外感が強かったことも、ストレスのひとつだったように思います。
※②:具体例を出すと「同世代のみんなが夢中になるアイドルを好きになれない」「社会や教育に対する批判を理解してもらえず馬鹿にされる」などです。
塾講師との関係
3つ目は、小学生の頃から通っていた学習塾の講師との関係です。
小学生の時は優しい先生が多かったのですが、中学に入ってから担当の先生が代わり、キツイ言動をとられることが多くなりました。
- テストで高得点を取っても褒めてもらえない
- 生徒を差別し、対応を変えられる
- 「なぜあなたは○○さんのように頑張れないの?」と言われる
- 個人的なイライラから不機嫌な態度を取られる
上記はほんの一部ですが、子どものやる気を削いだり、心を傷つけたりする言動がほとんどで、帰宅後は毎日泣いていました。
両親に話しても理解してもらえず、むしろ塾講師と一緒になって私を叱ることもあってすごく苦しかったです。
学校教育のあり方
4つ目は、学校教育のあり方です。
- 「同じ地域で同じ年代に生まれたから」という理由だけで、狭い空間に押し込める
- 個性や性格がバラバラの子どもたちに対し、決まった時間に決まった行動を取らせる
- その生活に馴染めない子どもは「支援の対象」と見なす
小学生の頃から、そのような学校教育の在り方に対して疑問を抱いていました。
「個性を大事に」と謳いながら、個性を押しつぶして“自分らしさ”を奪い続ける学校のことを、どうしても好きになれなかったのです。
その嫌悪感は年齢を重ねるごとに大きくなり、次第に「ストレス」へと変化していったように思います。
養護教諭の対応
5つ目は、中学校の保健室にいた養護教諭の対応です。
さまざまなストレスを抱えてながら生きていた私は、中学入学以降、体調を崩すことが多くなりました。
そのため、ほぼ毎日のように保健室に駆け込んでいたのですが、養護教諭の先生がものすごく厳しい人で、苦しい気持ちに全く寄り添ってくれなかったのです。
- 「熱がないなら教室に戻りなさい」と追い返される
- 「胃が痛いならトイレにでも行ったら?」と追い返される
- 胃が痛すぎてトイレの前で倒れ込んでいたら、冷たく笑われる
私の場合は、たとえ養護教諭が優しい人であっても、遅かれ早かれ不登校になっていたと思います。
しかし「辛い時に寄り添ってくれるはずの養護教諭が冷たい人だった」という事実は、当時の私にとってすごく重たいものでした。
学校教師からの指名制度
6つ目は、学校教師からの指名制度です。
学校の授業は、教師が生徒をランダムに指名し、問題の答えや意見の発表を促す場面が多々ありますが、私はそれが大の苦手でした。
間違った答えや見当違いな意見を言ってしまい、教師やクラスメイトから笑われたり、白い目で見られたりすることがとても多かったからです。
過去に何度かそのような経験をしていたので、私の中ではかなりのトラウマになっていたのだと思います。

この指名制度は、対人恐怖症(社交不安障害)※③発症の大きなきっかけのひとつとなりました。
※③:対人場面で過度な緊張や不安が生じ、他者との交流を避けてしまう病気です。不登校後に患い、29歳になった現在もまだ名残があります。
副科目に対する苦手意識
7つ目は、体育や美術(副科目)に対する苦手意識です。
副科目はほかのクラスメイトの前で(もしくは一緒に)おこなうので、その人の出来・不出来がはっきりと公になります。
その上「学校(教師)側が定めたルール」に則って試合や創作をしなければならず、自分の行動や表現に制約がかかります。
対人恐怖の傾向があり、何よりも“自由”を好む私にとって、そのような副科目の授業スタイルはとても苦痛でした。
特に美術は、いくら自分が努力したところで、教師の好みに沿った作品じゃないと評価されにくい部分もあったので、余計にしんどかったです。
勉強に対する“無価値感”
8つ目は、勉強に対する“無価値感”です。
小学校に入った時から、私は学校の勉強が嫌いでした。正確に言うと、勉強を頑張ることで得られるメリットや成果に特段の魅力を感じなかったのです。
- 勉強して有名な大学に入り、有名な企業に就職することだけが“幸せの形”ではないはず
- 勉強や肩書にとらわれず、自分が“幸せ”と思う生き方を選べば良いだけの話では?
そんな考えを持つ私にとって「高校・大学受験で良い成績を叩き出すことを目的に作られた学校の勉強」は、ストレス以外の何物でもありませんでした。
しかし、普通に学校に通っていると、少なくとも高校卒業するまで(18歳頃まで)は“勉強漬け”の生活が続きます。
そのことを考えた途端に気が遠くなり、次第に“学校に通う意味”すら見出せなくなっていきました。
まとめ|不登校の鍵は、子どものストレスと上手に向き合うこと
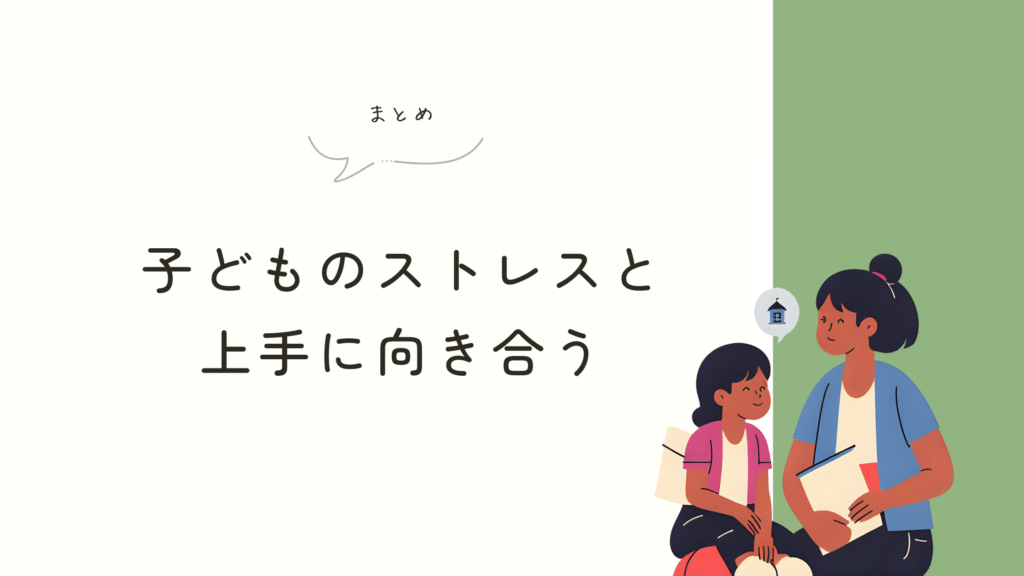
本記事では、不登校の要因を考える上で重要なキーワードとなる「ストレス」について、不登校の元当事者・元研究者が掘り下げてみました。
ここでは私の事例を取り上げましたが、すべての不登校のお子さまが、私と同じようなストレスを抱えているわけではないと思います。
私たち大人が到底考えつかないような、複雑で難しいストレスを抱えているお子さまも多くいらっしゃることでしょう。
お子さまのペースに合わせて、ゆっくりとストレス要因を見つけ出し、ストレスとの向き合い方を親子で一緒に考える
平坦な道のりではないからこそ、それを登り切った時の達成感と幸福感は、何物にも代えがたい宝物になります。
不登校に悩むすべての親子さまに明るい未来が待っていますよう、心から願っています。