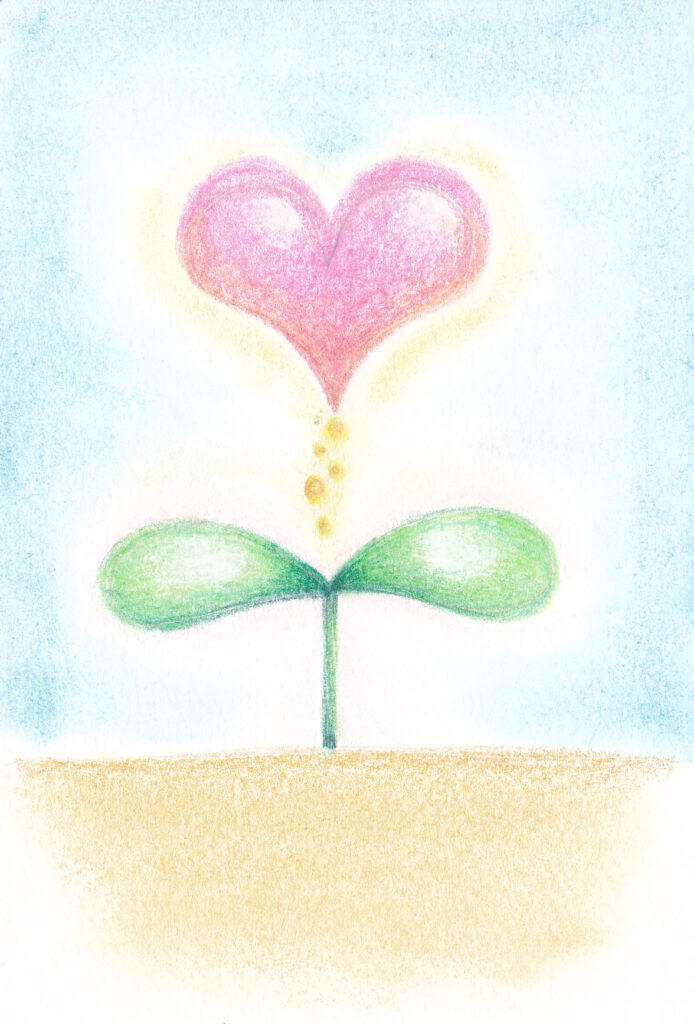不登校の子どもへの接し方がわからない保護者・教師の方に伝えたい!中学2年生で不登校になった私が周囲の対応で辛かったこと・してほしかったことをまとめました

「不登校の子どもに対して、どんな接し方をすれば良いかわからない……」
そのように悩んでいる保護者の方や教師の方は、とても多いと思います。
苦しんでいる子どもに対してどのような対応ができるのか、どんな言葉をかければ良いのか……。
お子さまを大切に想う気持ちが強ければ強いほど、迷ってしまいますよね。
そこで今回は、中学2年生で不登校になった私が周囲の対応で「辛かったな」「苦しかったな」と思ったことをまとめてみました。
「こういう対応をしてほしかった」「こういう言葉をかけてほしかった」と思うことも合わせて紹介しています。
不登校のお子さまがいる保護者の方、学校関係者の方はもちろん、不登校のお子さまと関わるすべての方に読んでいただきたいです。
辛かった対応
この章では、私が不登校だった時に「辛かったな」「苦しかったな」と思った対応をまとめました。
少しでも“不登校のリアル”を知っていただければ幸いです。
登校を催促される
辛かった対応として最初に挙げたいのが「登校の催促」です。
私は中学・高校ともに不登校経験がありますが、どちらの先生からも登校の催促がありました。
- 「この日は来よう」「それが無理ならこの日」と、毎日のように電話がかかってくる
- ある日突然「こんなにも長期間(数か月間)休んだなら、もう教室に戻れるでしょ?」と言われる
- 心理テストの結果が良くなっているのを見て「元気になったじゃん!そろそろ教室に戻れるんじゃない?」と言われる
- 行事の練習に無理やり参加させられ、当日までしつこく誘われる
また、学校の先生だけではなく、両親からも登校の催促・強要がありました。
- 「学校に行きましょう」という内容の長文メールが毎朝のように届く
- 仕事を休み、私を学校に連れて行かせる
- 無理やり服を脱がせて制服に着替えさせる
- 「行事くらいは行けるんじゃない?」と言われる
学校に行きたくない・行けない状態だから不登校になっているというのに、そこを無視して登校を催促されるのは、とてもしんどくて辛いです。
大人の皆さまだって、会社に行きたくない・行けない状態の時に「会社に行きなさい!」「なんで仕事に行かないの!」と言われたら、ものすごく嫌な気分になりますよね。
それと同じことを、不登校の子どもはたくさんの大人からされているわけです。
正直、たまったもんじゃないですね……。
これまで、いろいろな本や論文で不登校経験者の語りを読んできましたが、「登校を催促されて嬉しかった」と言っている人は見たことがありません。
みんな声を揃えて「登校を強要・催促されたのが嫌だった」と語っています。
学校に行ってほしい・来てほしい気持ちは十分わかりますが、その気持ちをあからさまに子どもに向けるのは違うと思います。
本人の気持ちやタイミングを大切に、温かく見守ってほしかったです。
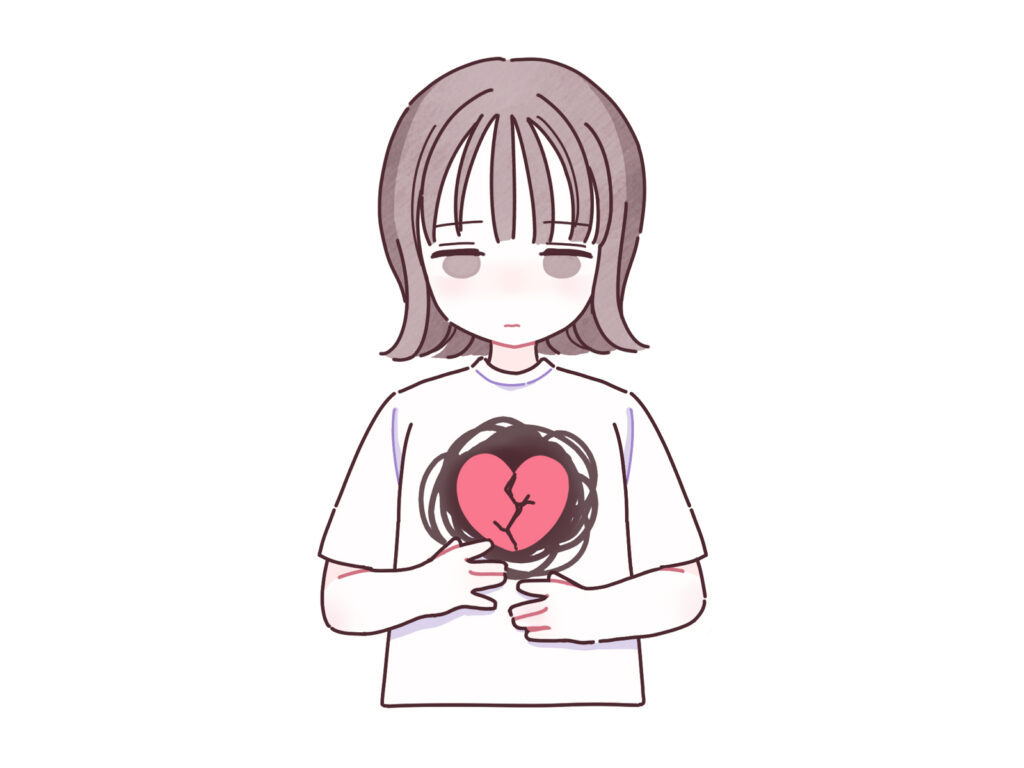
教室に連れて行かされる
登校を催促されるだけでなく、無理やり教室に連れて行かされることもたくさんありました。
教室への連行は、中学・高校ともに経験があるのですが、一番嫌だったのは高校の時です。
カウンセリングに行っただけだったのに、なぜか強制的に教室に連れて行かされて、「どうですか今の気持ちは」と聞かれたのです。
体育の授業中でクラスメイトは不在でしたが、あまりの強引さに泣きそうになりました。
本人の希望を聞かずして無理やり教室に連れて行くのは、一種の“パワハラ”とも言えるのではないかと思います。
どうしても私を教室に連れて行きたかったのであれば、「教室に行ってみない?」「教室には行けそう?」など、ひとこと聞いてからにしてほしかったです。

私の見えるところで泣かれる
不登校になった最初の頃に辛かったのが、毎日のように母親が泣いていたことです。
リビングにいたり、自室で寝ていたりすると、遠くから母親の泣き声が聞こえてくることが時々あったんですよね。
母親も母親で、相当しんどい思いを抱えていたのだと思います。
けれど、そんな母親の泣き声を聞いてしまったら、こちらは泣くに泣けませんし、モヤモヤした気持ちや不安なども一切吐露できません。
「私のせいで母親が傷ついている」「母親を泣かせる私はなんて最低な娘なのだろう」という感情だけが残り、すごく苦しかったことをよく覚えています。
辛い気持ち、泣きたい気持ちは痛いほどわかるのですが、そういうネガティブな気持ちは私が完全に自宅を出ている時に発散してほしかったです。
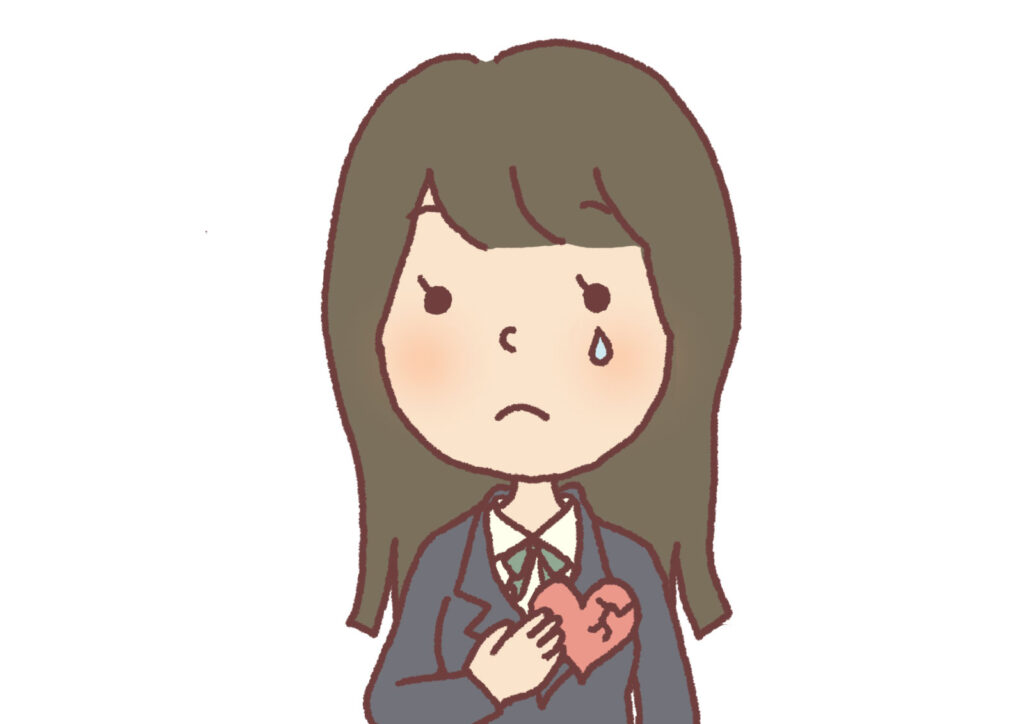
大人たちが揉める
私が自室にこもっている時や、お風呂に入っている時、両親はよく私のことで喧嘩(言い合い)をしていました。
本人たちは私に聞こえないように話しているつもりだったようですが、こういうのって意外とちゃんと聞こえるんですよね……。
両親だけでなく、当時連絡を取り合っていた塾の先生とスクールカウンセラーの先生の2人も揉めることが多く、お互いからお互いの愚痴をしょっちゅう聞かされていました。
「自分のせいで両親(大人)たちが喧嘩をしている」という事実は、子どもにとってかなりしんどいものです。
それがきっかけで自己否定感が強まることも多いですし、私も当時はひたすらに自分を責めていました。
人間同士なので、意見のぶつかり合いは避けては通れないと思います。
しかし、それを子どもの目に触れる場所でおこなうのは、子どもを傷つけるだけですし、何のメリットもありません。
大人同士・親同士で子どものことを話す時は、確実に子どもの目に触れない環境・状況を選ぶべきだと思います。

私が不登校である事実を封印される
両親や祖父母など、私の不登校を知っている人たちは、周囲の親戚や知人たちに「娘(孫)が不登校である」という事実を頑なに隠していました。
「学校に行っている」と嘘をついたり、学校の話題が出るとあからさまに動揺したり、曖昧な返答ではぐらかしたり……。
そんな大人たちの様子を見るのが、とても辛かったです。
不登校である事実を封印するということは、不登校に対してネガティブな考えを持っているからだと思います。
それはある程度仕方がないことなのかもしれませんが、自分の存在までも否定されているような気がして、すごく悲しかったです。
できることなら、「今ちょっと体調崩してて学校行ってないねん」と正直に伝えてほしかったです。
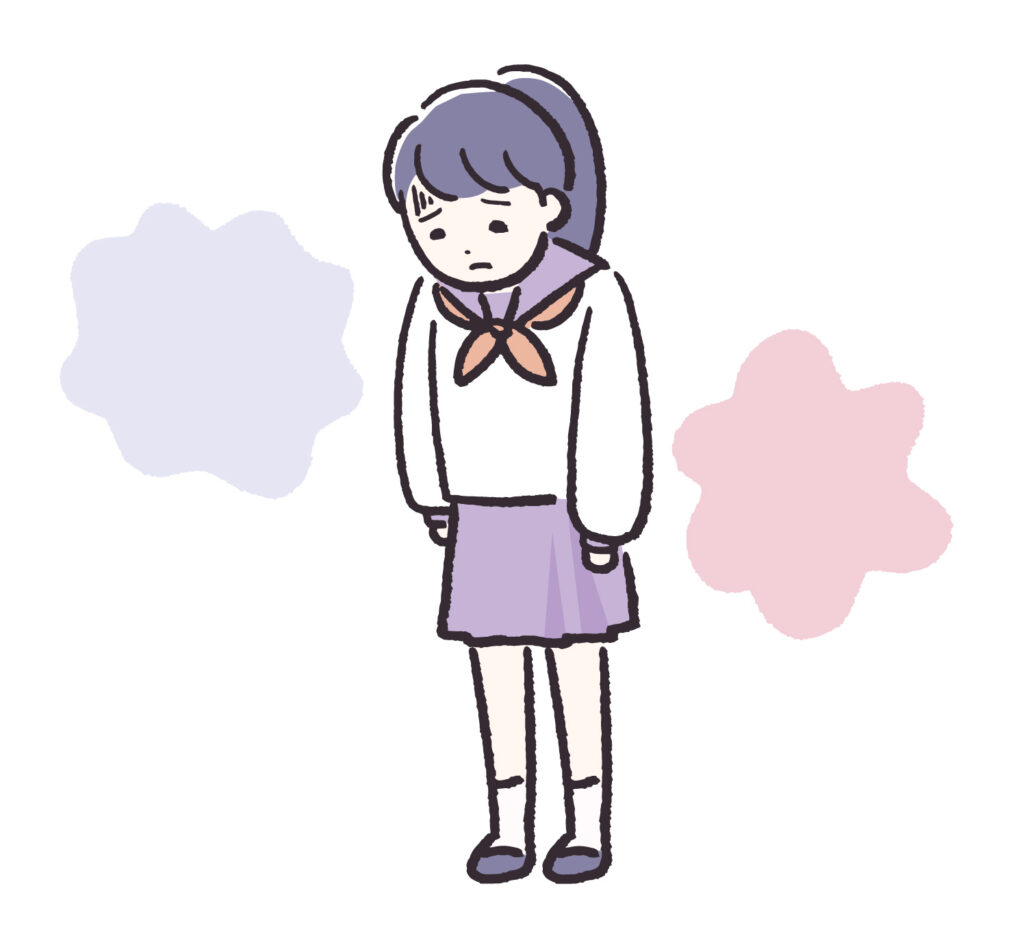
朝に無理やり起こされる
不登校になった当初は、母親が毎朝のように私を起こしに来ていました。
わざとテレビの音量を大きくしたり、顔や頭を触って起こさせようとしてきたり……。
「学校に行きなさい!」ではなく、ただ「朝だから起きて」と言いたいだけみたいでしたが、正直そっとしておいてほしかったですね。
「おはよう~」「朝ご飯できたで~」くらいの軽やかな言葉がけに留めておいてほしかったです。

不登校を否定される
当たり前のことですが、学校に行けないことを否定されるのも辛かったです。
私が一番辛かったのは、当時通っていた塾の先生に言われたこの言葉です。

お前が病んでるようには見えへんし、学校行けへんようになる意味がわからへん。
お前みたいなん、まだ苦しんでるうちに入らへんし、お前よりもっと苦しい思いしながら学校行ってる子もおる。
そんなんで学校行かへんのなんて甘えてるだけや。
不登校に対してネガティブな考えを持つのは自由です。
しかし、それをわざわざ当事者の子どもに言う必要はどこにもないと思います。
もう少し想像力を持って、相手に寄り添う言葉がけをしてほしかったです。

「頑張れ!」という言葉がけ
塾の先生たちはよく「頑張れ!」という励ましの言葉を私に言っていました。
最初は「応援してもらってありがたいな」と思っていましたし、素直に嬉しい気持ちでした。
しかし、あまりにも頻繁に言われ続けたので、段々と「私ってそんなに頑張れていないのかな……」と思うようになりました。
一生懸命頑張っているところに「頑張れ!」と言われてしまうと、その頑張りを否定されたような気持ちになってしまいます。
「応援してるね」「体調に気をつけて無理しないでね」みたいな言葉の方が、個人的には嬉しかったかなと思います。
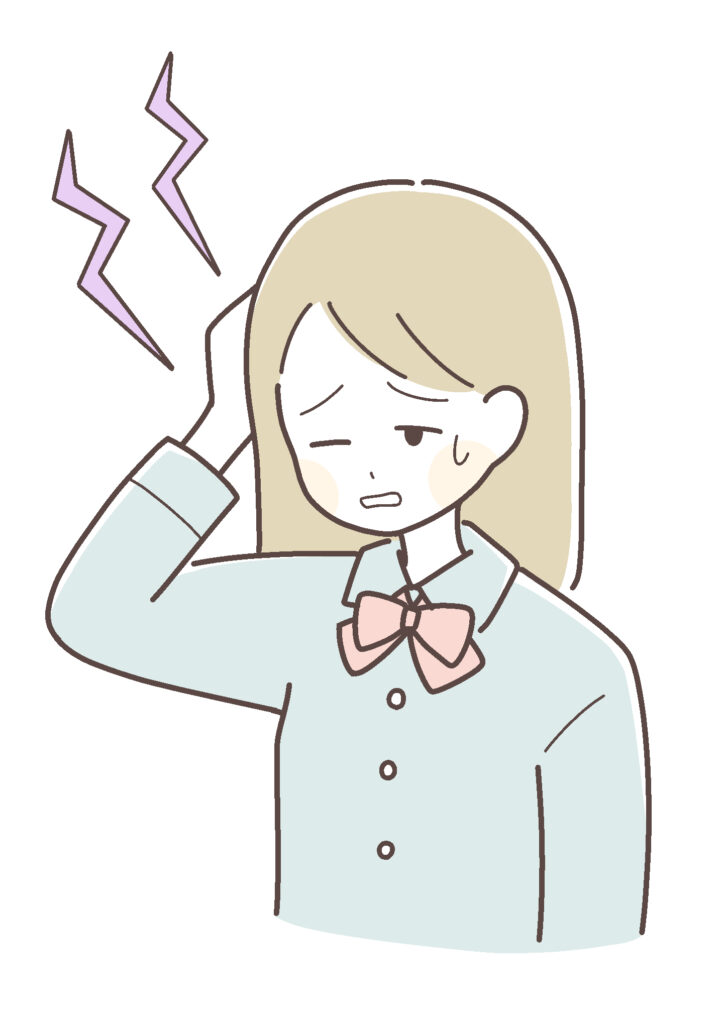
「誰も助けてくれない」
「結局は自分で考えなあかんから、誰も助けてくれへんで。」
こちらも、塾の先生に言われた言葉です。
悩みは自分で乗り越えるものだから、本質的には誰も助けてくれない……。
それは紛れもない事実だと思いますが、心が限界に達している子どもにそれを言うのは、絶対に間違っています。
これを言われた直後、私は軽度の拒食症になりました……。
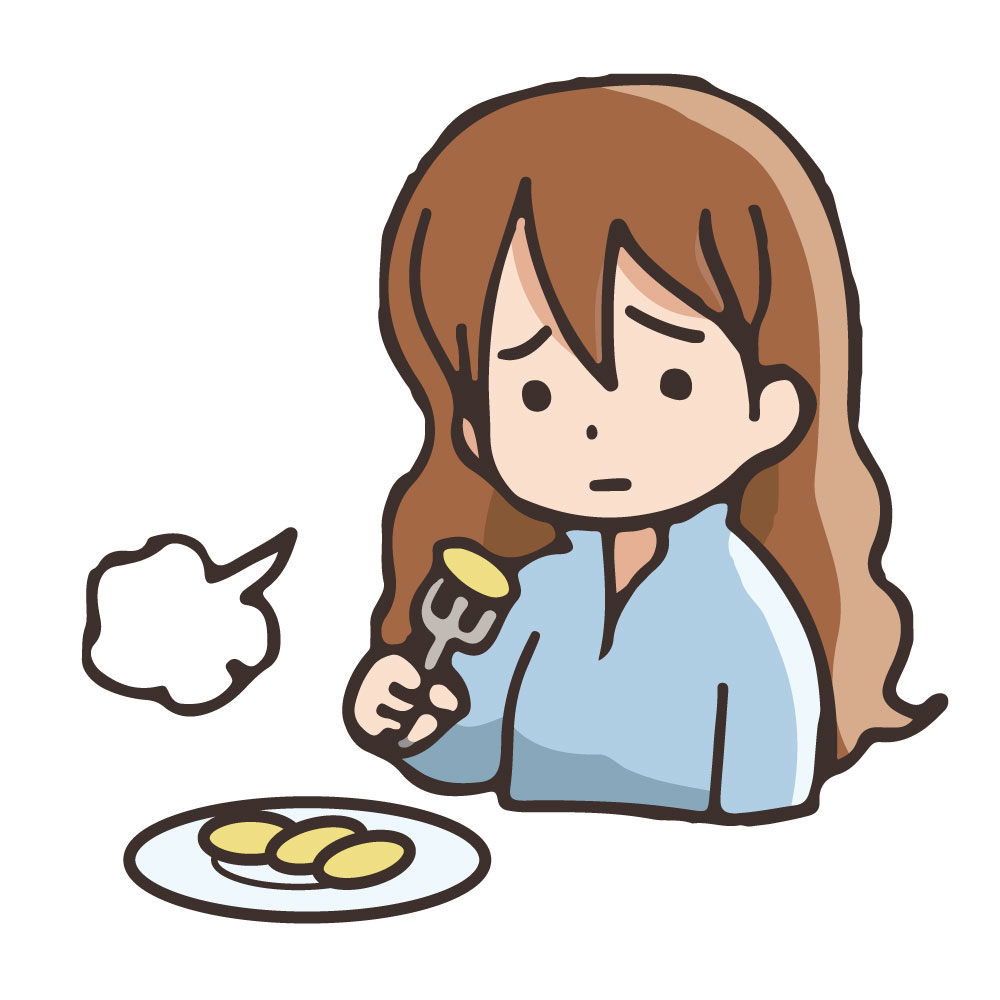
「贅沢で甘えすぎ」
不登校になった直後は、塾の先生方に頻繁に話を聞いてもらっていました。
母親や父親は今ひとつ頼りにならなかったため、ほかに話を聞いてくれる人がいなかったのです。
すると、ある時、先生たちは私にこう言いました。
「ちょっと贅沢だと思うよ。」
「いくらなんでも甘えすぎなんじゃないの?」
悩みや苦しみを他人(大人)に打ち明けることは、子どもにとってとても勇気がいる行為です。
それなのに、それを「贅沢」「甘えすぎ」というネガティブな言葉で片付けられてしまったことが、とても悲しかったです。

子どもが大人を頼ることの何がいけないのでしょうか。
大人の支えは、子どもの成長や自立のために必要不可欠なものではないでしょうか。
不登校になって間もない14歳の私は、ただただ傷つき、泣くことしかできませんでした。

「病んでる」と言うなんて……
中3の一時期だけですが、私は自分のことを「病み子」と呼んでいました。
こちらから積極的に「私は今とても辛いです」ということをアピールしないと、誰も心配してくれなかったからです。
すると、そのことを知った塾の先生がこう言いました。
「本当に病んでいる人は、自分から『病んでる』とは言いません。」
本人は良かれと思って言ったのでしょうけど、私はすごく傷つきましたね。
「私の辛さを理解してくれる人は誰もいないんだな」ということを改めて感じた瞬間でした。
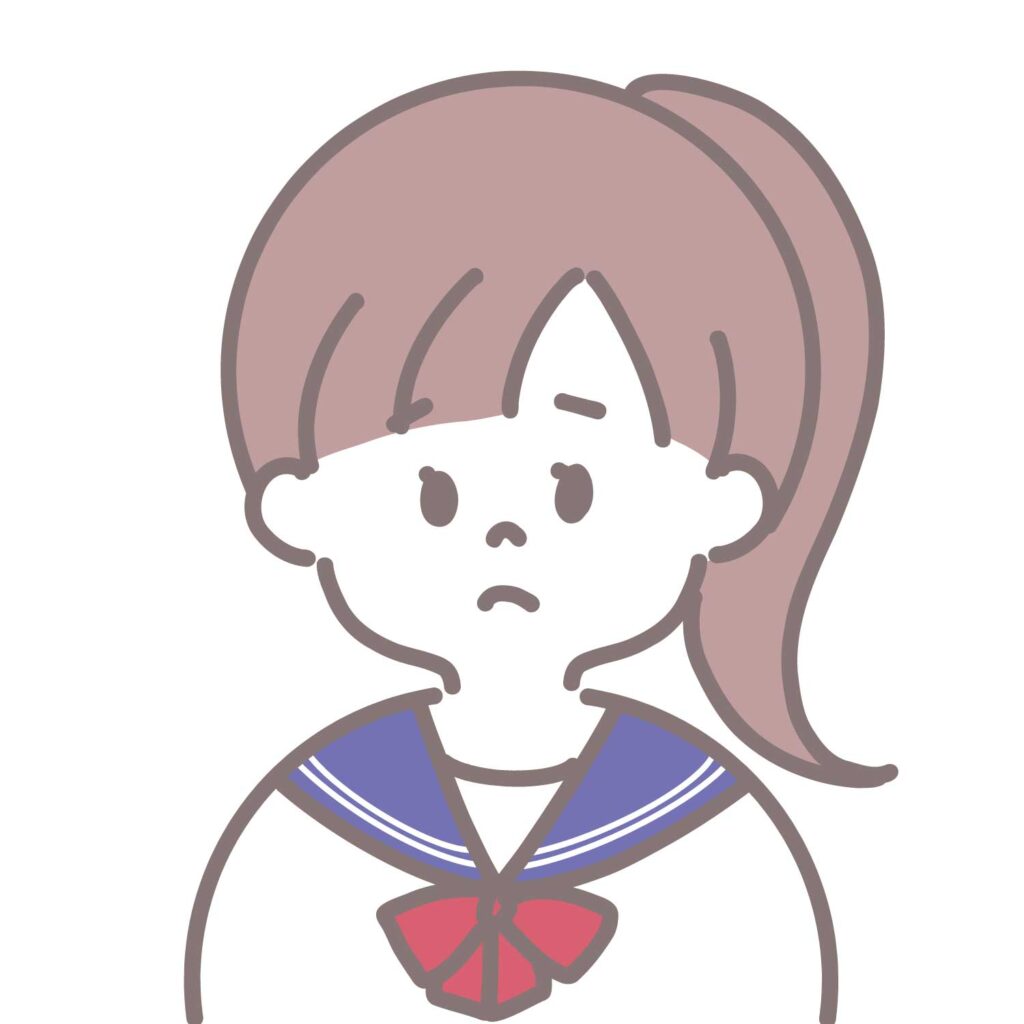
「学校行かずに何してるの?」
高校生の時にお世話になっていた塾の先生は、顔を会わせる度に「学校行かずに何してるの?」と聞いてきていました。
先生はおそらく、不登校の子どもが何をしているかを純粋に知りたいだけだったのだと思います。
しかし私は、「『学校に行く』という当たり前の行為をしていないこと」を責められているような気がして、すごく嫌でした。
「今日は何して過ごしてたの?」とかならまだしも、「学校行かずに」という言い方が、あまりにも無神経だなと思いますね……。

「線路のレールから脱線することになる」
これは、高校のスクールカウンセラーに言われた言葉です。
「このまま教室に戻らないと、あなたは一人だけ線路のレールから脱線することになる」と。
本当にひどいと思います。もっとほかの言い方がありますよね。
今はもう、「この人は視野が狭いかわいそうな人なんだなあ」としか思いませんが、当時は心から傷つき、ずっと泣いていました。
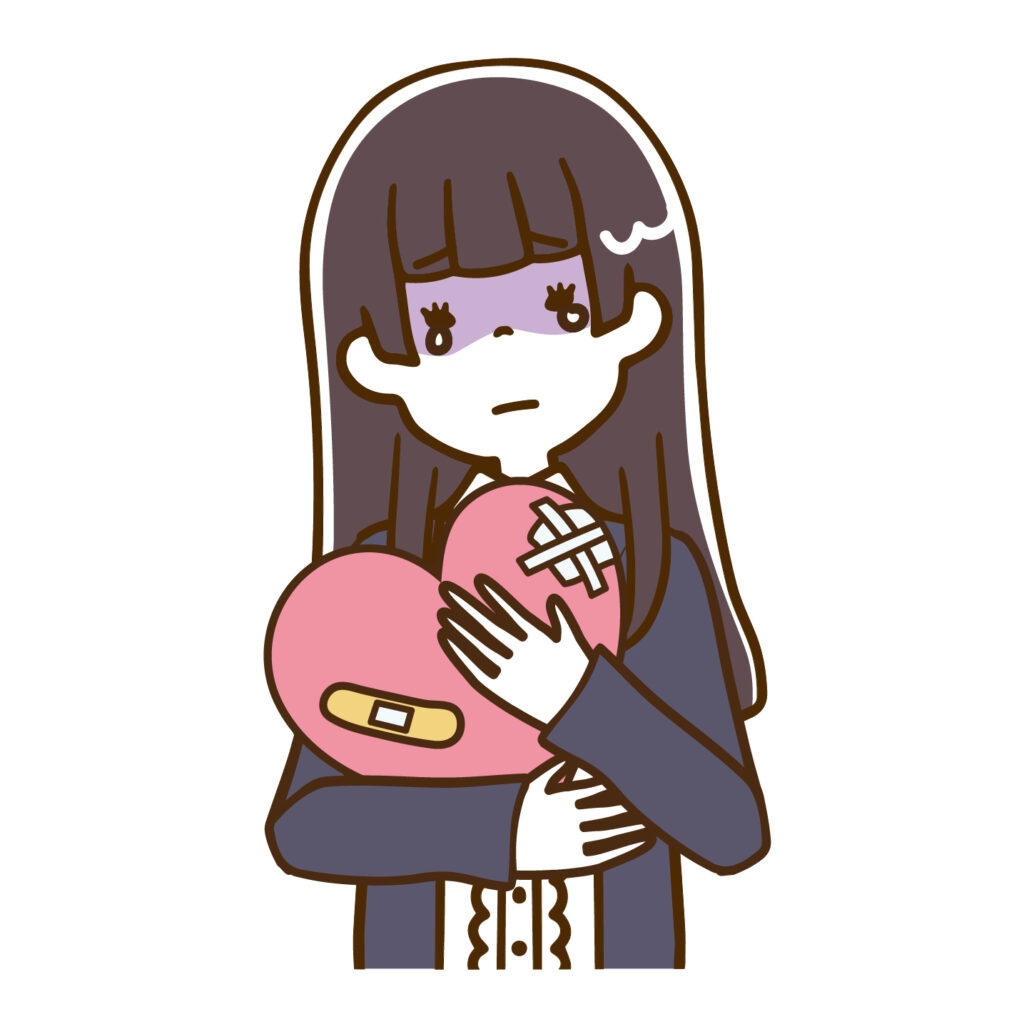
「そんな怖い顔で睨まないでよ」
これも、高校のときのスクールカウンセラーに言われた言葉です。
実はこの言葉は、スクールカウンセラーだけでなく、それ以外の先生にも言われました。
私は自分の高校のことが心底嫌いだったので、きっと先生方と話している時は、かなり険しい顔をしていたのだと思います。
しかし、いくら私が険しい顔をしていたとしても、それを本人に言う必要はどこにもありません。
その言葉を言われた日は泣きながら帰りましたし、しばらくは鏡の前で笑顔の練習をしていましたね。
数年後、心療内科の先生にこの出来事を話した時に、
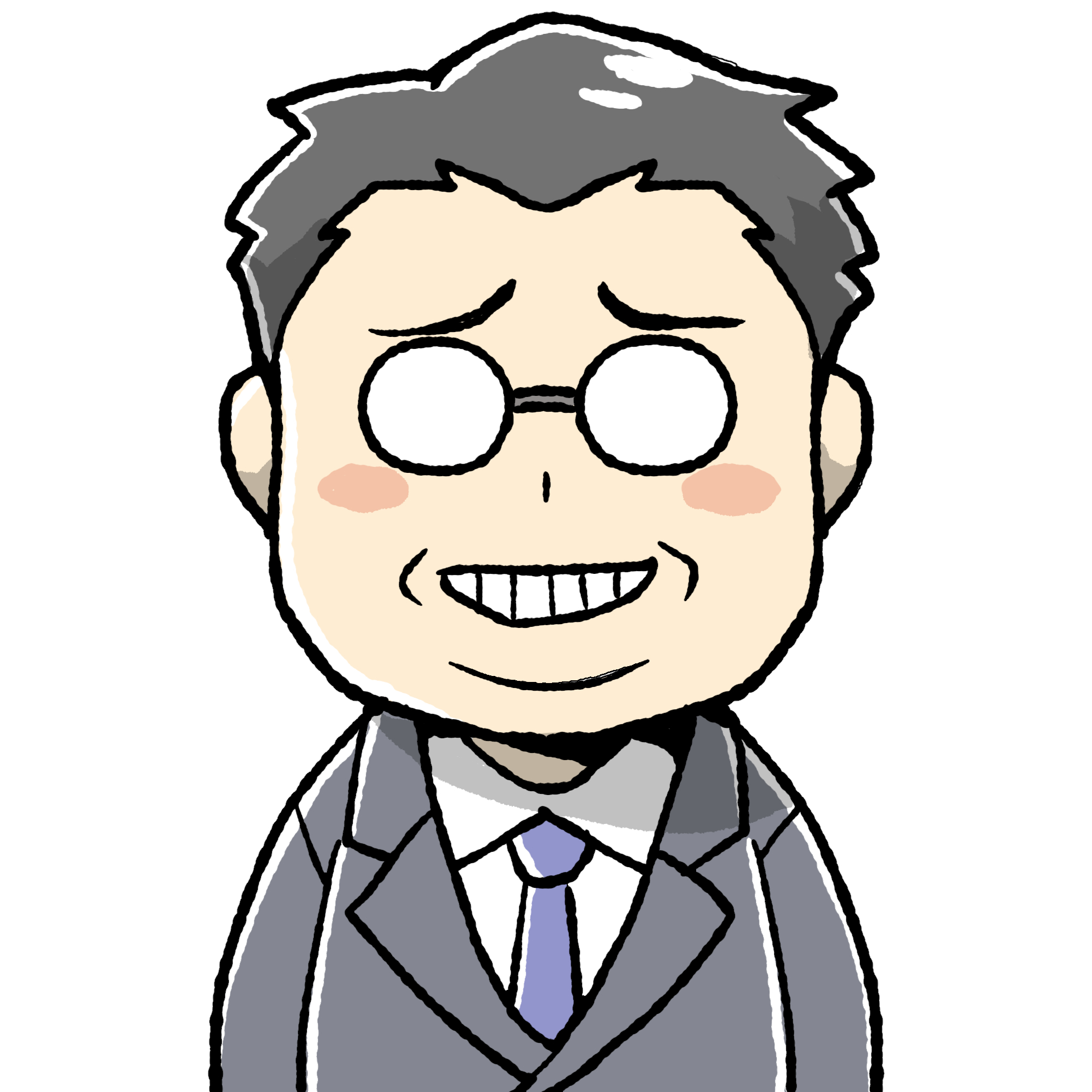
そう言った先生の気持ちもわからなくないよ。あの頃は今よりひどかっただろうし、よっぽど睨んでたんじゃないの?
と言われたことも含めて、辛い思い出です。
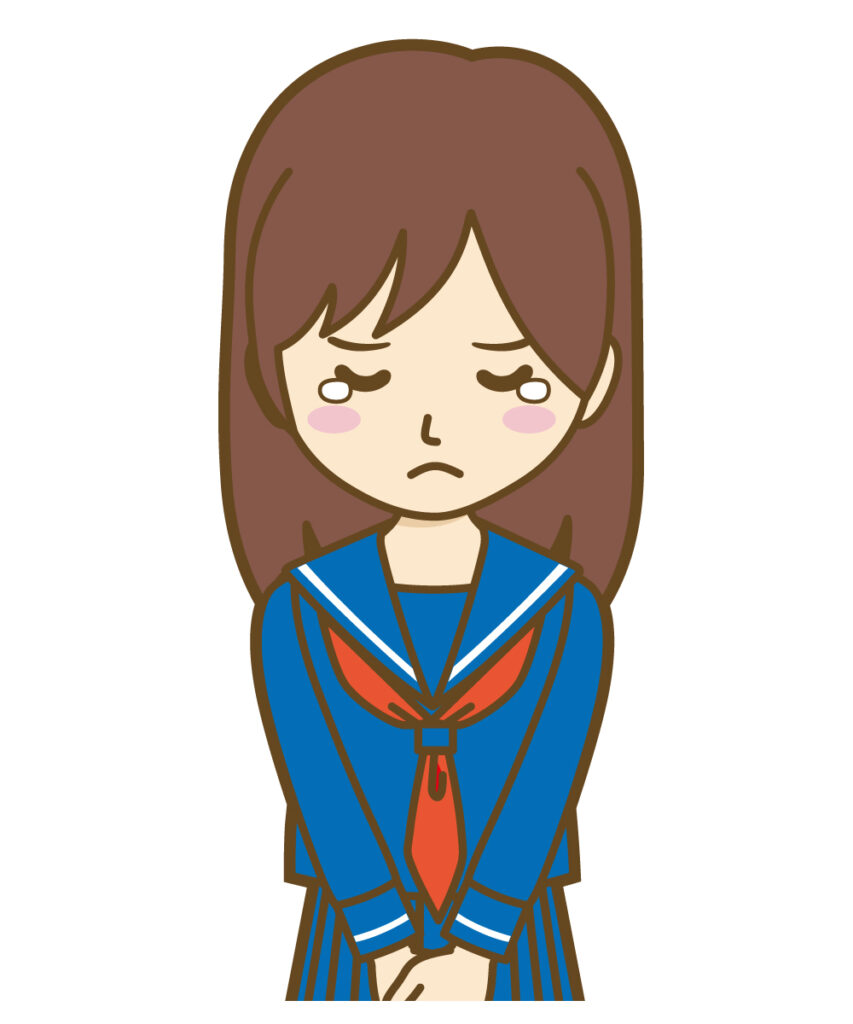
今後の進路を伝えたら怒られる
これも高校の話なのですが、退学して通信制高校に行くことを担任に話した時、こう言われました。

いつから辞めたいと思ってたの?辞めたいと思ってたなら、なんでもっと早く相談しないの?
高校の担任は、毎週のように私を学校へ呼び出し、学校へ引き戻そうとしていました。
「このまま教室に来なかったら、どうなるかわかるよね?」
「どうするのが一番いいか、わかるよね?」
会うたびにそんな言葉を発する人に、「教室に戻りたくない」「辞めたい気持ちがある」とは、なかなか言いづらいですよね。
もう少し本音を言いやすい雰囲気で接してほしかったですし、一方的に学校側の意見を押し付けるのはやめてほしかったです。

この時に一番辛かったのは、「ご両親にいろいろしてもらって申し訳ないと思わないの?」という言葉でした(キレ気味に言われました)。
私の両親(特に父親)は、再登校をめちゃくちゃ望んでいました。
そのため、いつ学校に戻っても大丈夫なように、参考書を大量に買ったり、学校の勉強内容を家で教えてりしていたのです。
両親の気持ちはありがたいですが、私が「そうしてほしい」と頼んだわけではありません。
あくまでもそれは、両親(というより父親)の勝手な“エゴ”ですし、正直、私にとっては迷惑以外の何物でもありませんでした。
そんな父親の行動を正当化し、両親の期待に応えない選択(自分の進みたい道を選択)をした子どもを叱るなんて、教育者として間違っています。
「趣味は育児です☆」と声高々に話す先生でしたが、それならばもっと、子どもの気持ちに寄り添った対応をしてほしかったです。

私の気持ちを決めつける
不登校だった時、「周囲の大人たちに勝手に私の気持ちを決めつけられて、勝手に話を進められる」ということがよくありました。
個人的に印象深かった出来事を、以下にまとめました。
- 「この子はもう教室に戻れるはず」と決めけて、登校を催促したり、無理やり教室に連れて行かされたりする
- 「この前の定期テストは受験できたから次も受験できるはず」と決めつけて、受験する前提で話を進められる
- 「授業は無理でも行事には参加できるだろう」と決めつけて、体育祭や合唱コンクールの練習に連れて行かされる
不登校は子どもの話なので、親や学教師をはじめとした大人による援助が不可欠です。
しかし、物事のすべてを大人たちが勝手に決めつけて、それをもとに行動してしまうのは良くないと思います。
一番大切なのは、不登校当事者である子どもの気持ちです。
何かを決めたり、行動したりしないといけない時は、ひとつひとつ私の気持ちを確認してほしかったです。

対応が急に変わる
中学の頃、母親の対応が急に変化したことが数回ありました。
何の前触れもなく急に冷たくなったり、そうかと思えば気持ち悪いくらい優しくなったり……。
どうやら、スクールカウンセラーの先生からの助言をもとに、対応をコロコロ変えていたようです。
いきなり対応を変えられると気分が悪いですし、信頼関係の崩壊にもつながります。
「カウンセラーに何か言われたんだろうな」というのも、なんとなく察しますしね。
「カウンセラーの先生に『○○をした方がいい』って言われたんだけど、どう思う?」みたいな感じで、正直に話してくれる方が子どもとしては安心できてありがたいかなと思います。
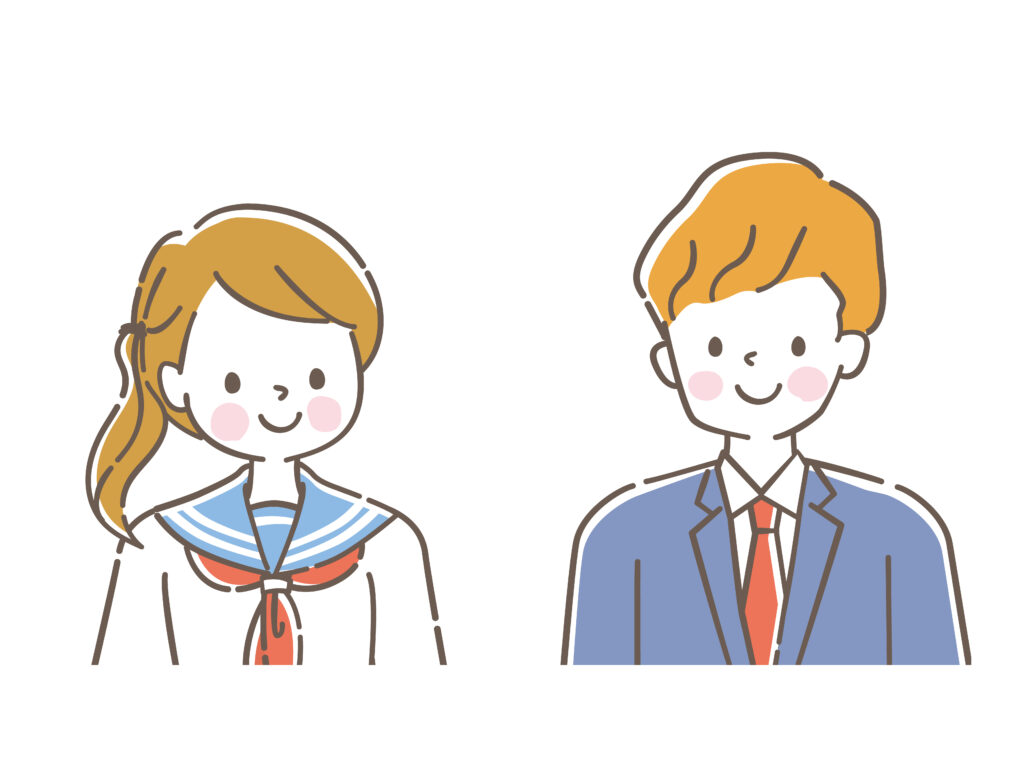
「みんな当たり前に行ってんだから」
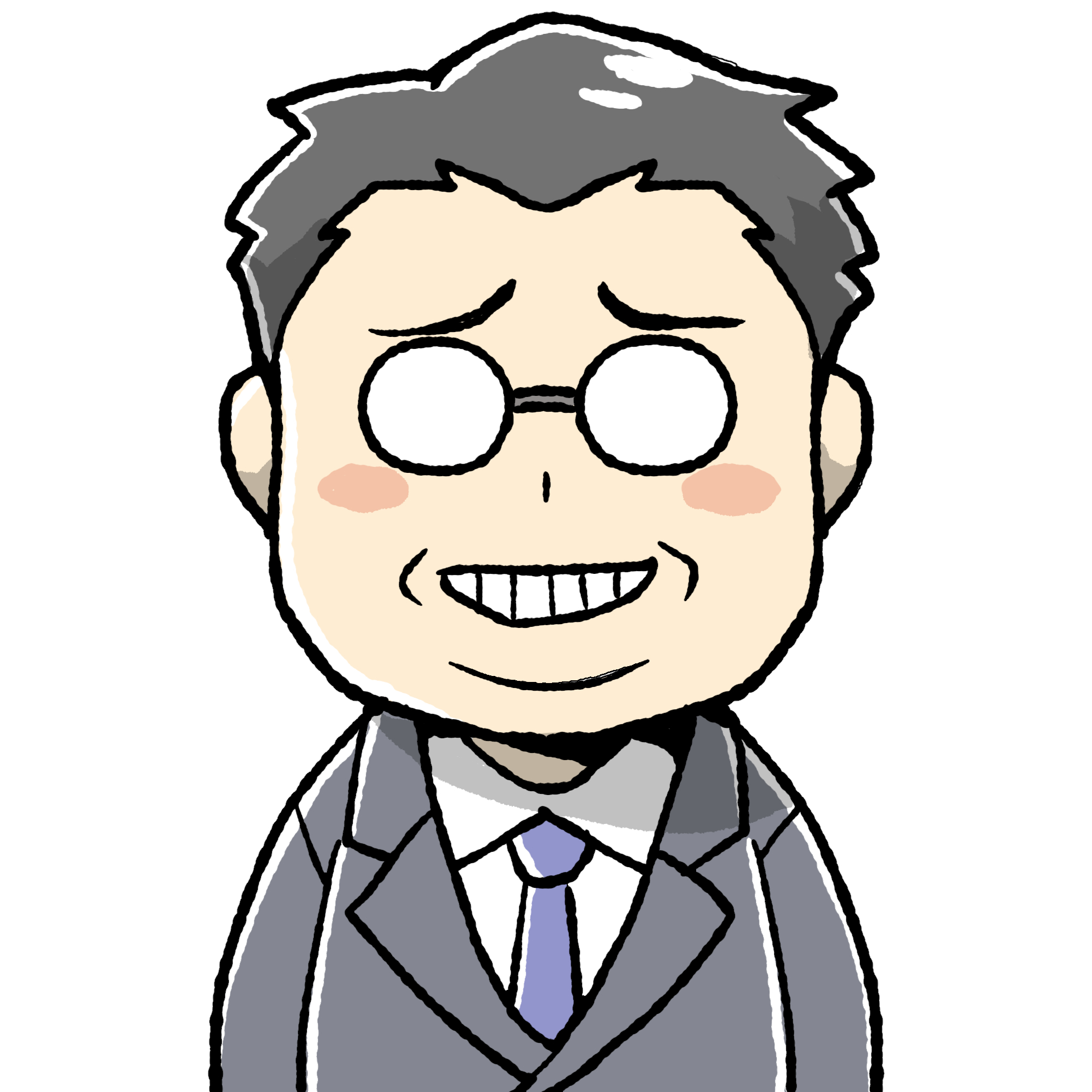
しんどくなるのは甘えだよ。何がそんなに嫌なの?みんな当たり前に行ってんだから。
心療内科の先生に言われた言葉です。
患者に寄り添う立場であるはずの医者からこんなひどい言葉が飛び出すなんて……信じられないですよね。
“みんなが当たり前にやってることができない”という劣等感や、周囲への申し訳なさを一番感じているのは、不登校である子ども自身です。
不登校の子どもと接する方は、まずこの部分だけでもしっかりと理解しておいてほしいなと、心から思います。
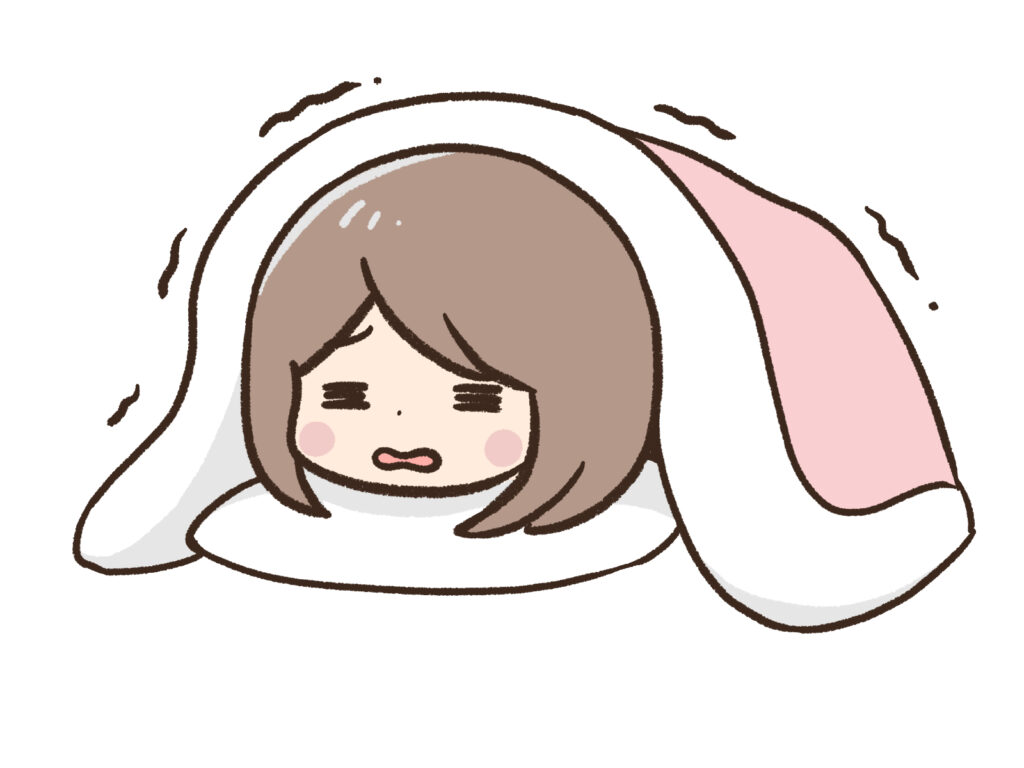
「今度はちゃんと行って」
短大への進学が決まった時、心療内科の先生と祖母、従妹に言われた言葉です。

次は『行くの嫌』って言わないでね。責任取れないから。ちゃんと行ってね。
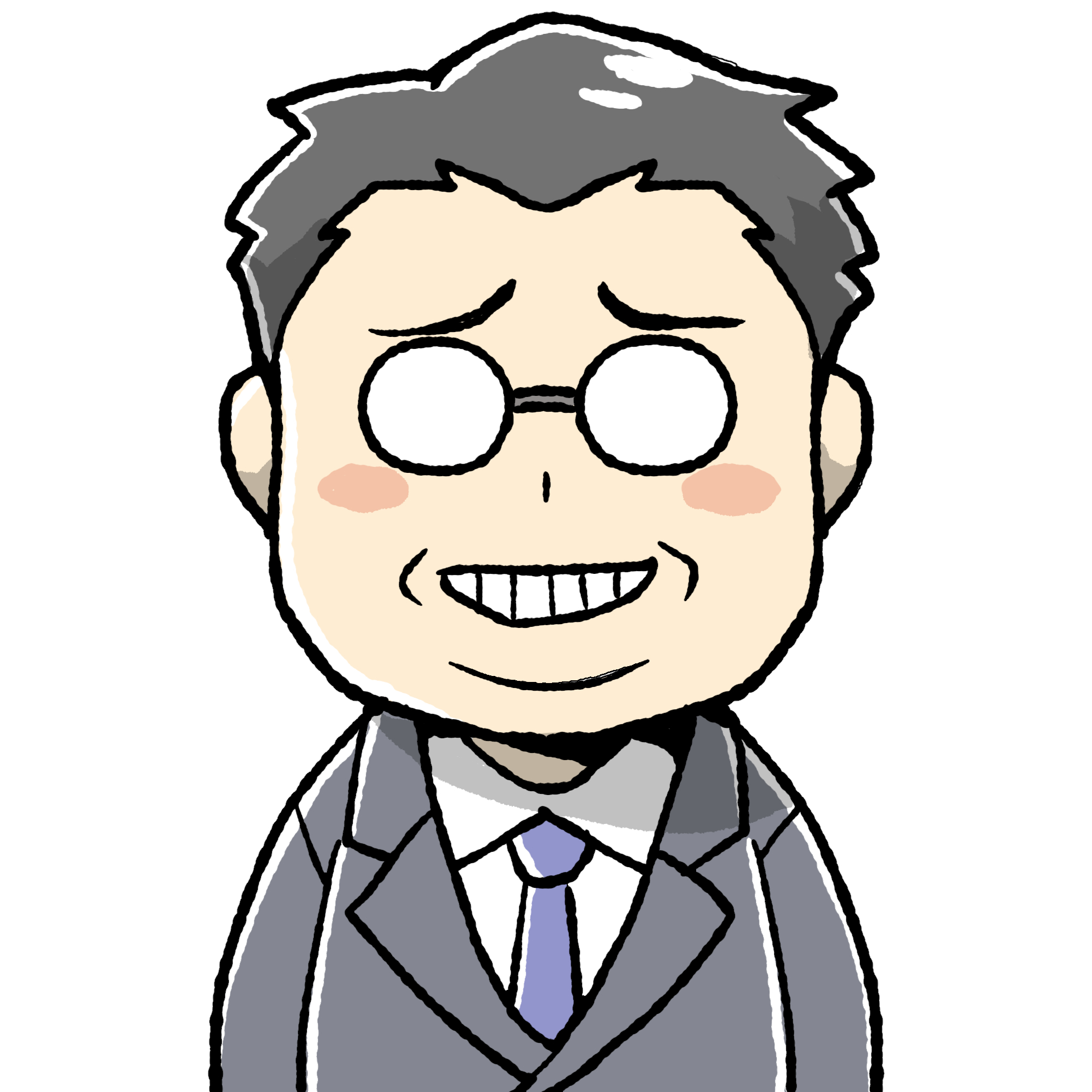
今度は登校拒否しないでちゃんと行ってよね。
私だって別に、好んで不登校になったわけではありません。
「行きたい・行かなきゃいけない」という気持ちに心と体が追い付かなかったから、結果として不登校になってしまっただけです。
そんな私の苦労や葛藤も知らずに、容易く「今度はちゃんと行って」なんて言わないでほしかったです。
その後、自分の気持ちを理解してもらえない悲しさや、「今度は失敗できない」というプレッシャーに押しつぶされ、激しく体調を崩しました。
私が短大に1日しか行けなかったのは、こういう人たちの言動の影響も少なからずあったのだろうなと思っています。

嬉しかった対応
とても残念な話ですが、不登校の対応で「嬉しかったな」と思ったものは、ひとつもありません。
しかし、「不登校とは直接関係がないものの、不登校だった私の心を救ってくれた対応」は少しだけあります。
この章では、そんな優しい対応を紹介したいと思います。
「どんな決断をしても応援する」
中学2年生で不登校になった私にとって一番大きな壁は、「中学卒業後の進路をどうするか」でした。
私立の中高一貫校に在籍していたので、そのまま内部に残るか、外部受験をして別の学校に進学するかをとても悩んでいたんですよね。
そんなとき、とある塾の先生が、こんな言葉をかけてくれました。

どんな進路を決断しても、私はゆきちゃんのことを全力で応援したいと思ってる。
その気持ちは、他の先生たちも同じだと思うよ。
「どんな決断をしても全力で応援する」。
とてもシンプルな言葉ですが、この言葉をさらりと言える人は、あまり多くない気がします。
「ありのままの自分を受け止めて、応援してくれる人がいる」と知れたことは、当時の私にとって大きな救いとなりました。
「私はこう思う」だけではなくて、「他の先生も同じ気持ちだと思う」と言ってくれたことも、すごく嬉しかったです。

「あなたの気持ちを尊重したい」
こちらも先ほどと同様に、中学卒業後の進路を悩んでいた頃のお話です。
卒業後の進路をなかなか決められずにいた時、別室登校していた私のところに担任の先生が来て、こんな話をしてくれたのです。

私はこの学校の先生だから、普通だったら内部進学を勧めないといけない。
けれど、もしゆきちゃんが外部受験に挑戦したいと思っているのなら、私はその気持ちを尊重したい。
正直、学校の先生からは内部進学を勧められるとばかり思っていたので、この先生の言葉にはとてもびっくりしました。
けれど、自分の立場よりも私の気持ちを大切にしてくれた先生の気持ちは、ものすごく嬉しかったです。
この先生の言葉(+塾の先生の言葉)のおかげで、私は数日後に外部受験の決断を下すことができました。

まとめ
本記事では、私が不登校だった時に周囲の対応で辛かったことや、「こういう対応や声かけがあれば嬉しかったな」と思うことをまとめてみました。
私の体験や考えがすべてのお子さまに当てはまるわけではないと思いますが、少しでも参考になる部分があれば幸いです。
今この記事を読んでいる大人の皆さま。
どうか、どうか、不登校の子どもを否定したり、無理やり学校に連れていくような真似はしないでください。
辛さや苦しみに寄り添い、優しい言葉をかけてあげてください。
子どもたちが安心して毎日を過ごせるよう、温かく見守ってあげてください。
どの保護者さまも、どの先生方も、「子どもに笑顔でいてほしい、幸せでいてほしい」と願う気持ちは皆同じだと思います。
その優しい願いを大切にしながらお子さまと接すれば、きっと想いは伝わるはずです。