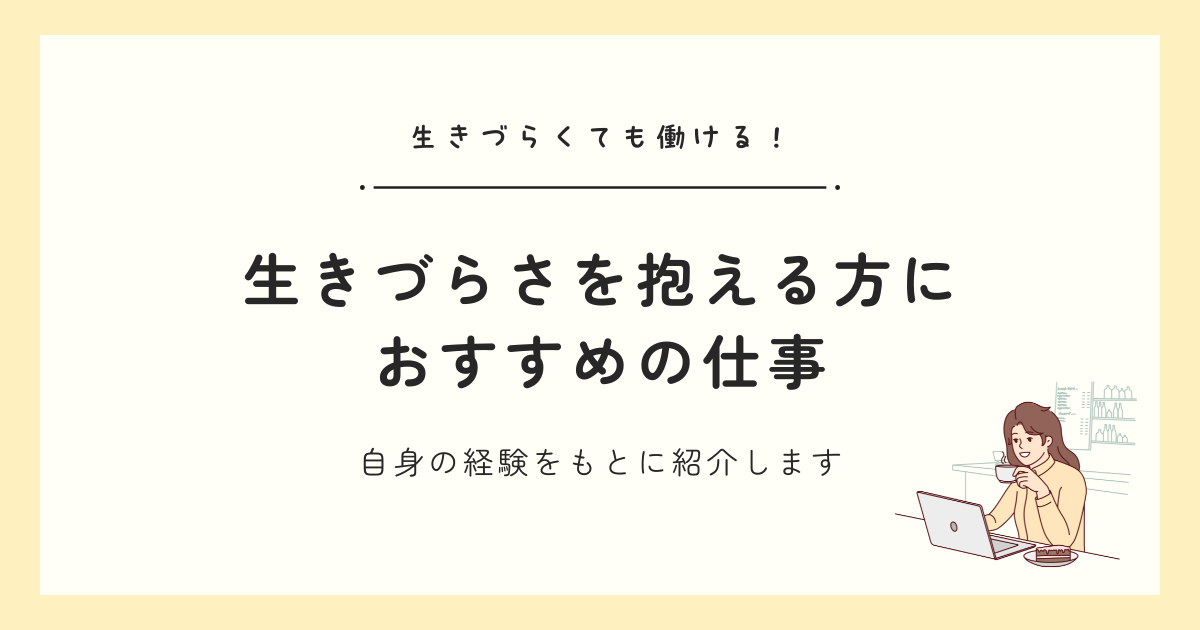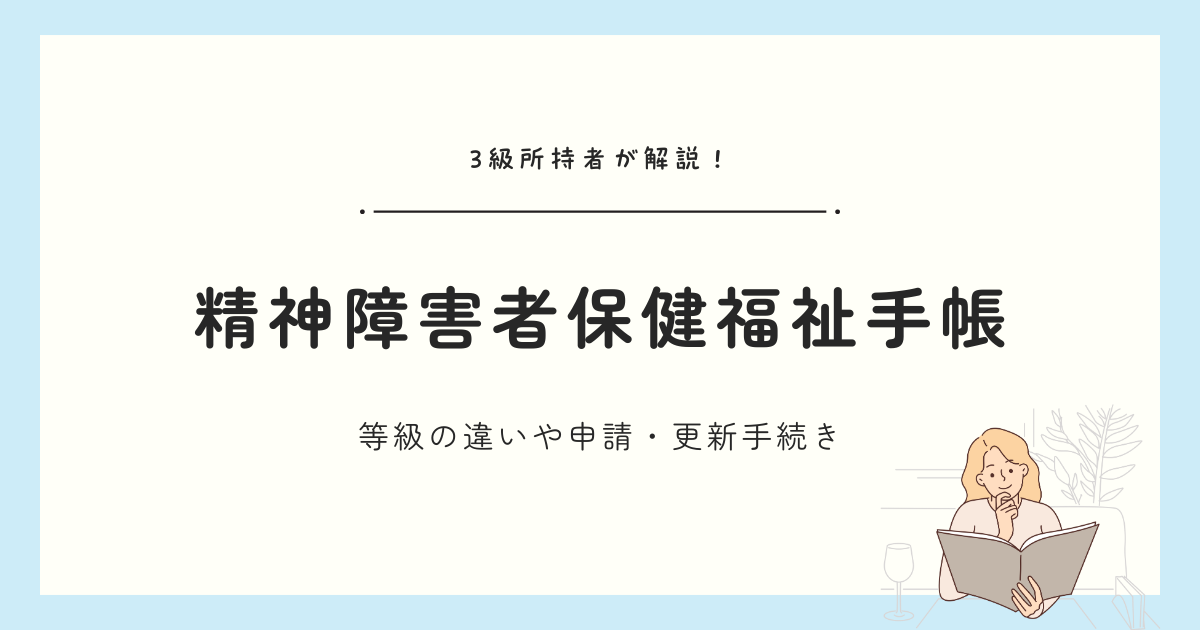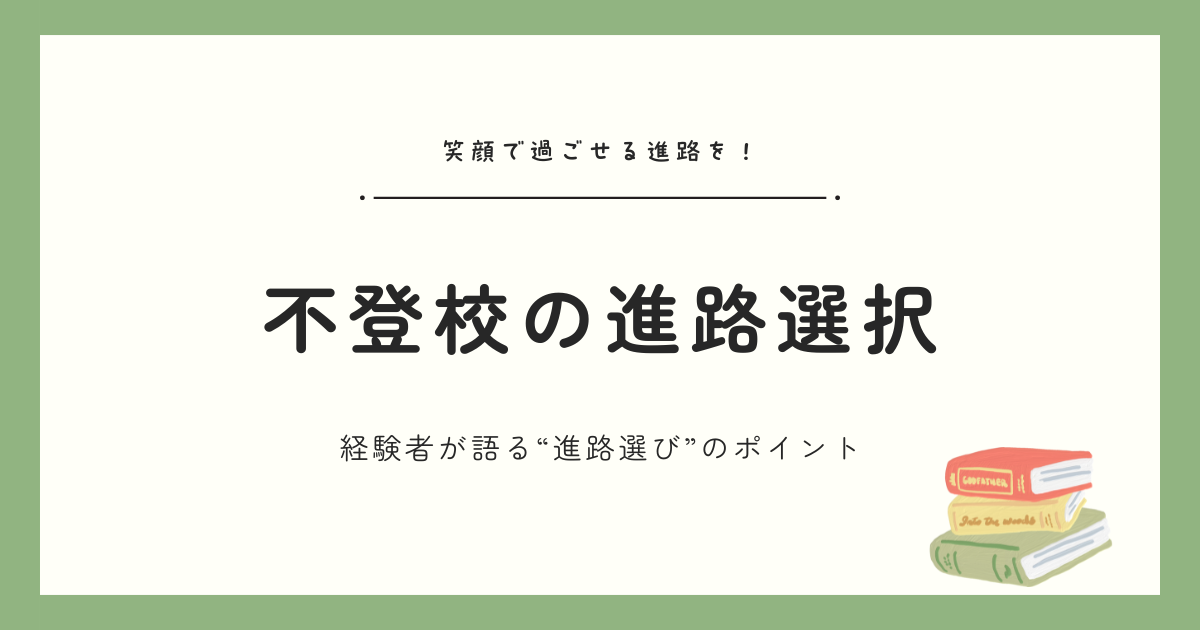【婦人科受診ガイド】つらい生理痛・不正出血・PMSで悩む方が受診前に知っておくべきこと
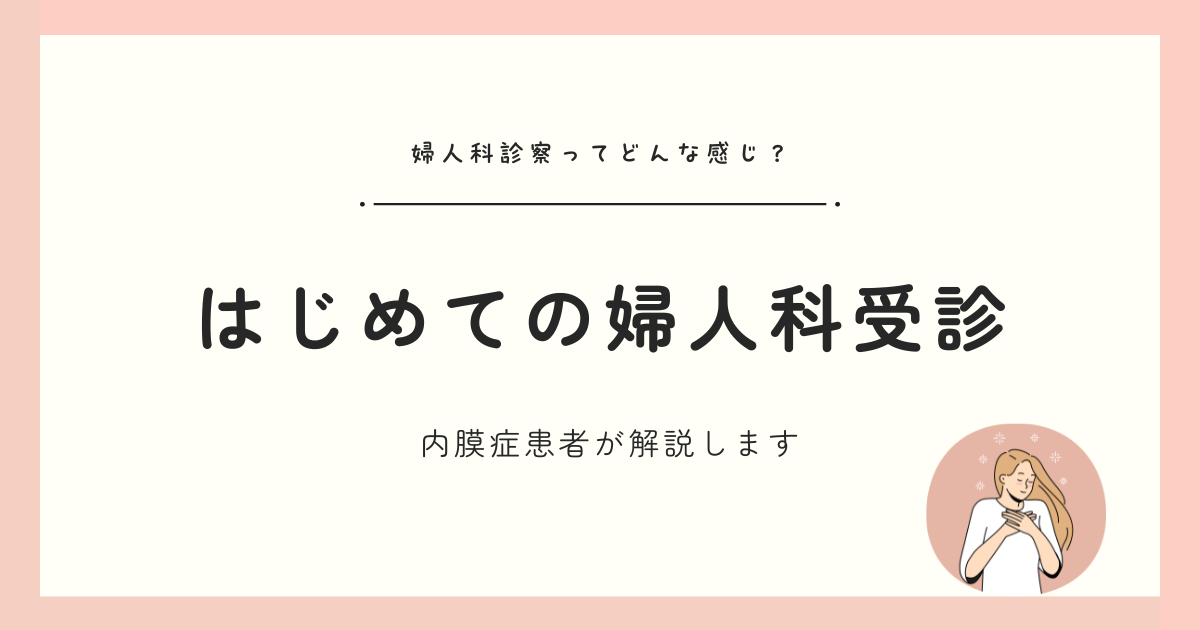
生理痛の悪化や不正出血があると「何かの病気なのかな……?」と不安になりますよね。
しかし、婦人科はほかのクリニックと比べて受診のハードルが高く、受診を躊躇してしまう方も多いと思います。
そこで本記事では、はじめて婦人科を受診しようと考えている方に向けて、婦人科受診ガイドを作成してみました!
「子宮内膜症」の診断で婦人科通いをしている私が、受診の目安や病気の可能性、受診前に知っておくべきことを丁寧に解説します。
初の婦人科受診で不安になっている方は、ぜひ参考にしてみてください。
- 婦人科を受診したいけれど、はじめてで不安がある方
- 受診する症状の目安を知りたい方
- 検査や治療について、経験者目線の記事を読みたい方
婦人科受診の前に知っておくべきこと
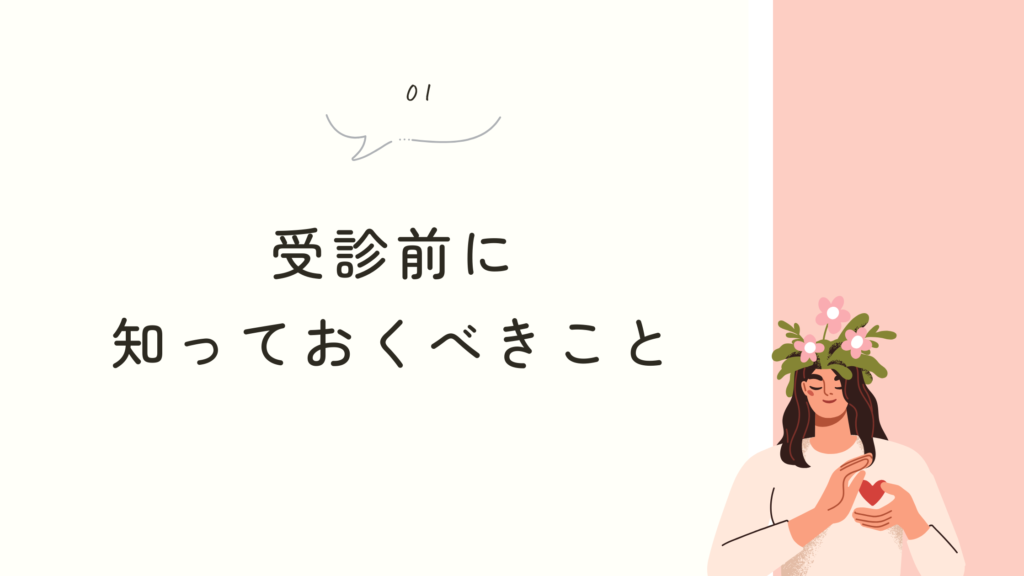
この章では、婦人科を受診する前に知っておくべきことをまとめました。
受診を考える目安や症状の原因など、体験談をもとに綴っています!
受診する症状の目安
あくまでも一当事者の考えですが、日常生活に支障が出ているかどうかが、婦人科受診を考えるひとつの目安だと思います。
たとえば、以下のような症状がある場合は、早めの受診がおすすめです。
- 痛み止めが効かない
- 生理が来るたびに寝込んでしまい、学校や仕事に行けない
- 不正出血や腰痛、下腹部痛などが長く続いている
- 生理期間が極端に長い・短い
- 出血量が増えた・減った
「なんとなくおかしい」「いつもと違う気がする」と思ったら、勇気を出して相談してみてください。
原因がわかれば少し気持ちが楽になりますし、もし異常がない場合でも「大丈夫だった」という安心感につながります。

ちなみに私は、不正出血が2週間以上続き、下腹部の痛みが強くなってきたタイミングで受診しました。
症状の原因として多いもの
生理痛や不正出血などの症状には、さまざまな婦人科疾患が関係していることがあります。
原因はひとつとは限らず、いくつかが重なって症状が出ている場合も少なくありません。
ここでは、婦人科でよく見られる症状の原因を4つ紹介します。
PMS(月経前症候群)
生理前に気分の落ち込みやイライラ、強い眠気などが出る場合は、PMS(月経前症候群)が関係している可能性があります。
症状の現れ方や辛さには個人差があり、日常生活に支障が出てしまう方も少なくありません。
また、「生理が定期的にある女性のうち7~8割の人」※①にPMSの症状があるというデータもあり、PMSは多くの女性が直面する身近な悩みのひとつです。

私も10代の頃からPMSがあり、いろんなセルフケアや対処法を試しながら症状と向き合っています!

※①:参考サイト:ツムラ「女性の7〜8割が悩むPMSの症状には漢方を」
子宮内膜症
子宮内膜症は、子宮の内側にあるはずの組織が、子宮以外の場所にできてしまう病気です。
主な症状として、強い生理痛や下腹部痛、腰痛、不正出血などがあり、症状が進行すると薬の服用や手術などが必要になるケースもあります。
痛みや不調が続く場合は、できるだけ早めに婦人科を受診し、適切な治療を受けることが大切です。

内膜症の治療で手術をおこなった際の詳しい体験談は、以下の記事に綴っています。

子宮筋腫
子宮にできる良性の腫瘍で、比較的よく見られる病気です。
症状の出方には個人差があり、自覚症状がほとんどない方もいます。
必ずしもすぐに治療が必要になるわけではなく、症状や経過に応じて、定期的な経過観察や治療がおこなわれます。

私も2024年に筋腫が見つかりましたが、小さなものなので、治療はせずに経過観察をしています。
ホルモンバランスの乱れ
女性の体は、生理周期に合わせてホルモンの分泌が大きく変化しています。
このバランスが乱れることで、生理痛や不正出血をはじめとした、さまざまな不調が現れることがあります。
時間が経てば自然に落ち着くことが多いですが、不調が続く場合や症状が重い場合は、婦人科で相談するのがおすすめです。

主な治療方法
婦人科でおこなわれる治療は、症状の強さや原因、体質に合わせて選ばれます。
「いきなり強い治療をする」というより、無理のない方法から段階的に進めていくことが多いです。
この記事では、私の体験に基づいて4つの治療方法を紹介します。
低用量ピル
低用量ピルは、ホルモンの変動を安定させることで、生理痛の軽減やPMS症状の改善、不正出血の予防などができる治療薬です。
避妊目的のイメージが強いかもしれませんが、婦人科疾患に関する症状の治療として処方されることも少なくありません。
私も、2020年に手術を終えてから、約5年間ほど低用量ピルを服用しています!

低用量ピルに関するブログ記事は、近日中にアップ予定です!
漢方薬
漢方も、婦人科疾患によく使われる治療薬のひとつです。
病気そのものを治療するというよりは、体全体のバランスを整えることを目的に処方されることが多いです。
体質や症状に合わせて処方されるため、できるだけ体にやさしい治療を希望する方におすすめです。

漢方、すごく興味があって、現在は担当医に服用を相談中です。
鎮痛剤
生理やPMSによる腹痛や腰痛などが強い場合には、鎮痛剤を使って痛みをコントロールすることもあります。
痛みを我慢するのではなく、医師と相談しながら適切なタイミングで服用し、日常生活に生かしてみてください。

私も、腹痛や頭痛がひどい時は、鎮痛剤を服用しています。
定期的な経過観察
症状や検査結果によっては、すぐに薬を服用せず、定期的に状態を確認しながら様子を見るという治療が提案されることもあります。
特に、子宮筋腫や子宮内膜症などは、症状の変化を見ながら、必要に応じて治療方針を見直していくことが多いです。

私も、内膜症で手術をする前は、お薬なしの定期検診のみでした。
婦人科受診に向けた準備
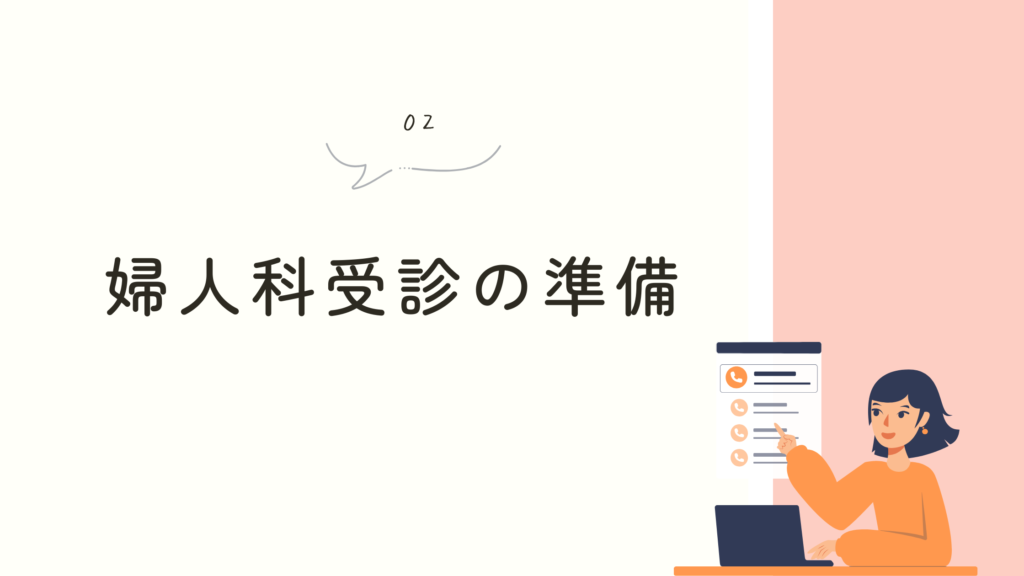
この章では、婦人科受診の際に事前に準備しておいた方が良いことをまとめました。
体験談をもとにまとめていますので、少しでも受診への不安が和らぎますと幸いです!
診察の流れ・内容
診察の流れや内容は、クリニックによって多少異なりますが、一般的には、以下のような流れで進むことが多いです。
- 受付・問診表の記入
- 医師の診察・検査
- 検査結果の説明
- 今後の治療についての説明
- 会計・次回予約
基本的には、内科など他の診療科と大きな違いはありません。
ただし、検査の内容によっては、結果が数日後に出るものもあります。
その場合、再受診が必要となるクリニックもあれば、異常がなければメールや電話で結果を伝えてくれるクリニックもあります。
受診が必要かどうかは検査内容やクリニックの方針によって異なるため、気になる場合は事前に確認しておくと安心です。

私が通っているクリニックは、検査の結果に異常がなければ、メールで結果を伝えてくれます。
再受診の手間を省けるので、とても助かっています!
問診や診察で聞かれること
問診表や診察では、現在の症状や体の状態について質問されることが多いです。
- 悩んでいる症状(継続期間や痛みの強さなど)
⇒いつ頃から続いているのか、どのタイミングで強くなるのか、日常生活にどれくらい支障が出ているかなどを聞かれることがあります。 - 生理周期・生理の状態
⇒生理の周期や日数、経血量の多さ、強い生理痛があるかなどを確認されることがあります。 - 過去の病歴・手術歴
⇒これまでにかかった病気や手術、婦人科系の治療歴があれば、わかる範囲で伝えましょう。 - 家族の病歴
⇒母親や姉妹など、近い家族に子宮内膜症や子宮筋腫などの婦人科系の病気があったかどうかを聞かれることもあります。
受診前に、症状の内容や生理周期、気になっていることなどをメモにまとめておくと、診察がスムーズに進みやすくなります。
緊張でうまく言葉にできなくても、メモを見せるだけで大丈夫なので、それだけで気持ちが楽になるはずです!
受診時におすすめの服装
婦人科を受診する際の服装は、上半身は特に気にしなくて大丈夫ですが、ボトムスはスカートやワンピースがおすすめです。
経膣超音波検査では、ショーツを脱いだ状態で診察台に上がります。
そのため、スカートやワンピースならショーツの着脱だけで済み、準備がスムーズです。
私はいつも、スカートもしくはワンピースで診察に行っています!

また、診察の際は足を大きく開く必要があるため、固くてタイトなスカートよりも、柔らかくゆとりのあるものの方が楽に受診できます。
個人的には、なるべく締め付けが少ない服装の方が、検査だけでなく診察中も落ち着いて過ごしやすいかなと思います。

経腹超音波検査の場合は、ズボンやショーツを脱ぐ必要がないため、基本的にはどんな服装でも大丈夫です。
受診時に用意しておくと安心なもの
婦人科の診察を受けるにあたり、事前に用意しておくと安心なものを2つ紹介します。
生理周期や日数がわかるメモ・アプリ
婦人科診察では、生理周期や日数の把握がとても重要になります。
そのため、生理周期・日数がわかるメモや、生理管理アプリは必ず用意しておきましょう。
私が通っているクリニックでは、過去3か月分の生理周期や日数を聞かれることが多いです。
あわせて、その時の症状や痛みの強さ、出血量なども簡単にメモしておくと、よりスムーズで詳しい診察につながりやすくなります!
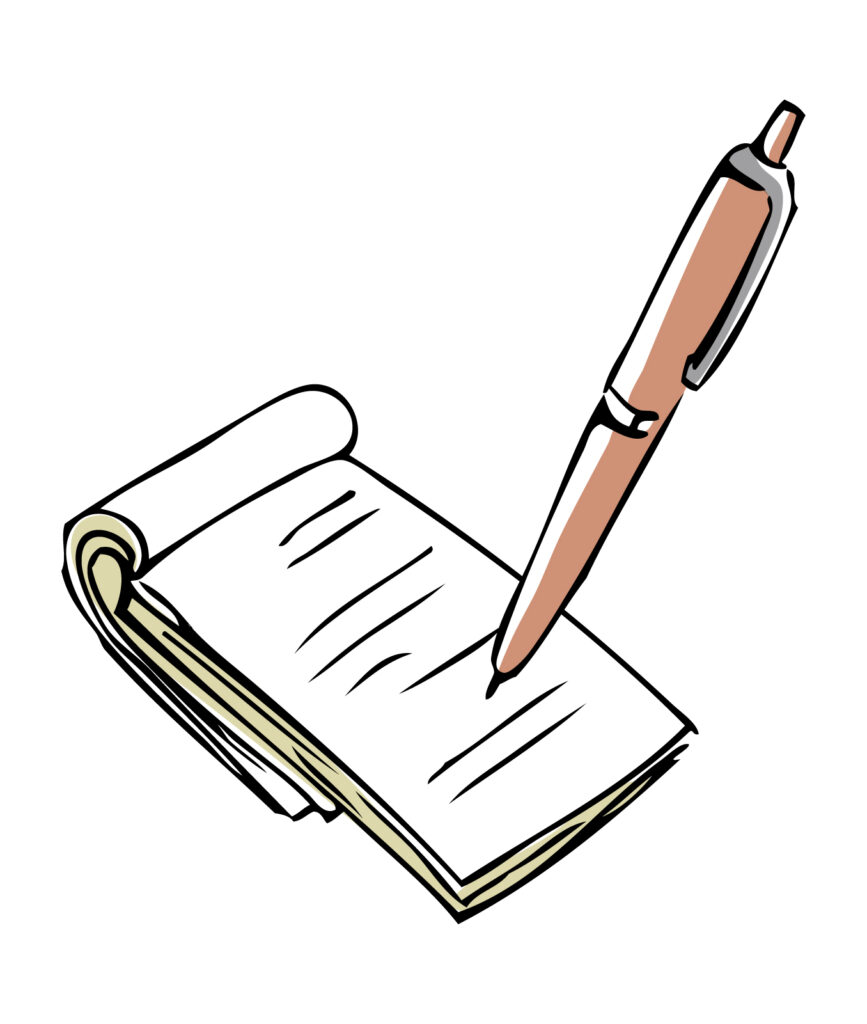
ナプキンやおりものシート
もうひとつ、持参しておくと安心なのが、生理用ナプキンやおりものシートです。
検査の内容によっては、少量の出血が起きることがあります。
私自身も、検査後に少し出血することがあるため、受診の際は必ず持っていくようにしています。
出血は当日中におさまることがほとんどですが、翌日以降も出血が続く場合は、早めに医師へ相談してくださいね。
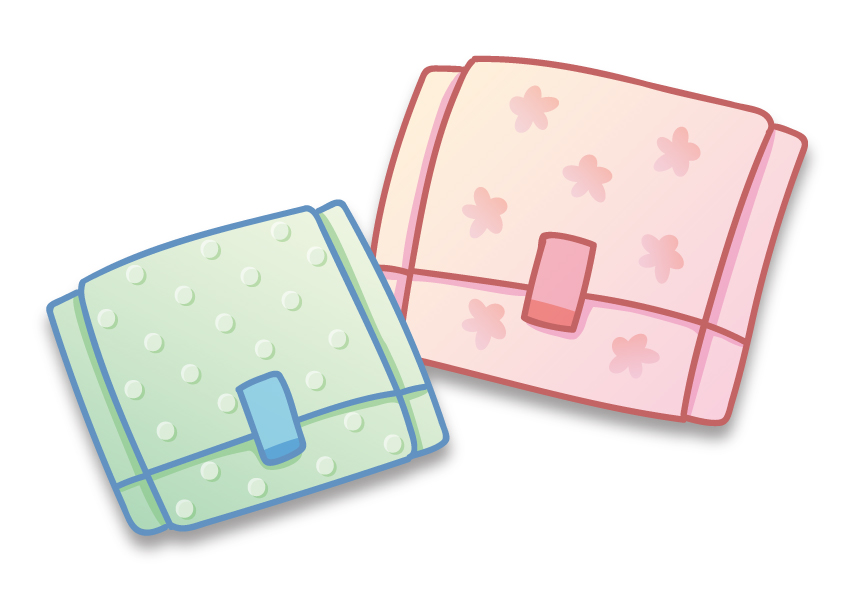
婦人科の検査方法
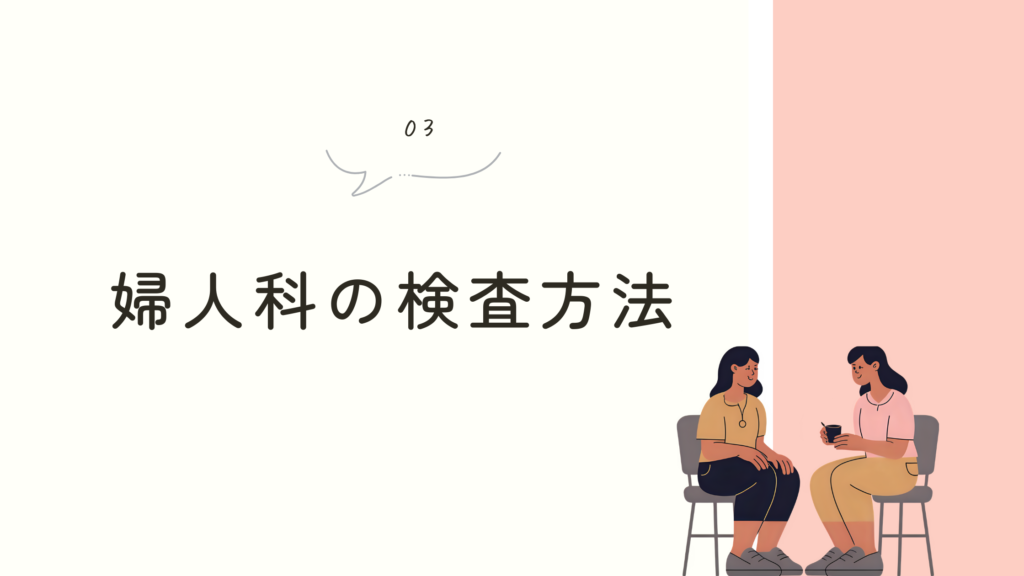
この章では、婦人科診察における代表的な検査方法を、体験談をもとに3つ紹介します。
どんな検査がおこわなれるのかをイメージすることで、安心して検査に挑めるようになると思います!
経膣超音波検査
婦人科の検査で最もメジャーなのが、経膣超音波検査です。
専用の椅子に座った状態で、膣内に超音波機器(長い棒のようなもの)を挿入※②し、子宮や卵巣の状態を調べます。

私が通っている医院も、こちらの検査方法です。
検査では専用ジェルを塗った機器を挿入されるのですが、やはり、多少の痛みや異物感はあります。
しかし、検査そのものは1~2分程度で終わるため、個人的にはそこまでのストレスは感じません。

※②:膣からの検査に抵抗がある場合や、性交渉が未経験の場合は、肛門から挿入することもできます。
経腹超音波検査
超音波検査は、お腹からおこなう(経腹超音波検査)場合もあります。
ベッドに仰向けになった状態でお腹に特殊なジェルを塗り、その上から機器を当てて子宮や卵巣の状態を調べる方法です。

私も過去に、一度だけ訪れた医院で経験したことがあります。
経腹超音波検査をする場合は、尿がたまっている状態の方がより精密な検査をおこなえるのだそうです。
そのため、なるべくお手洗いを我慢した状態で検査に挑むのがおすすめです。
MRI検査
もしも超音波検査や触診などで異常が発見された場合は、臓器の状態がより精密にわかるMRI検査を勧められるケースもあります。

私の場合は、子宮内膜症の腫瘍(チョコレート嚢胞)が大きくなったタイミングでMRI検査を受けました。
MRIは、お腹に重しを乗せた状態でトンネルのような機械に入り、30分くらい安静にした状態で体の異常を調べる検査です。
機械に入るのは少し怖かったですが、慣れれば全然問題なく、すぐに終わった記憶があります。

その他の検査方法
上記の検査を主軸に、以下の検査を追加でおこなう場合もあります。
- おりもの検査
- 触診
- 血液検査など
血液検査は、ホルモンバランスや貧血、炎症の状態を調べられるため、よく使われます。

私も定期的に血液検査をやっているので、ここ最近は、注射に対する免疫がかなりつきました(笑)
ただし、クリニックや医師によって、検査方法や診断方法は異なります。
詳しく知りたい方は、受診するクリニックのホームページなどを確認することをおすすめします。
婦人科受診のよくある質問
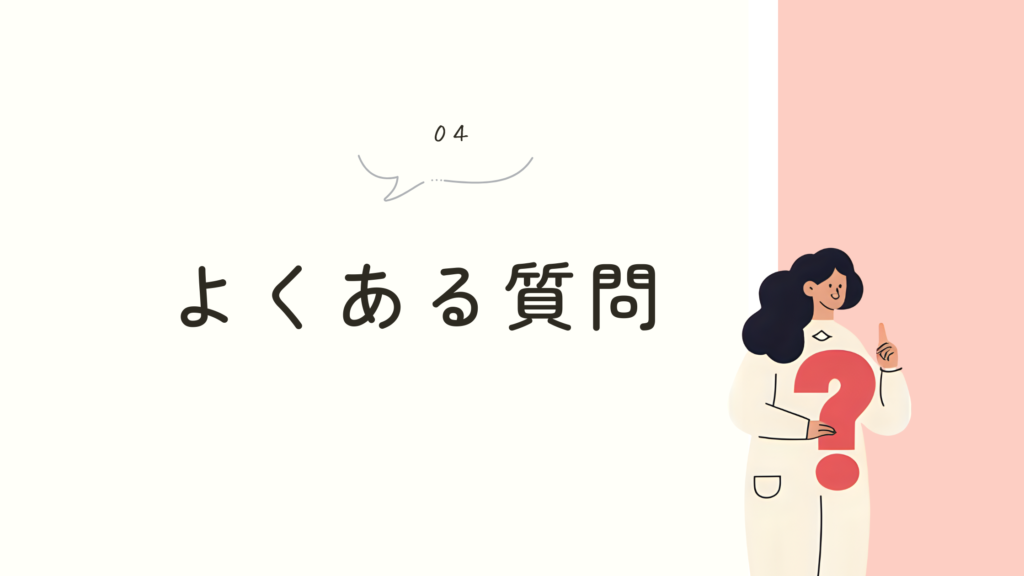
この章では、婦人科受診をする際のよくある質問をまとめてみました。
受診にあたってさまざまな不安や疑問がある方は、ぜひ参考にしてください!
初診の診察料は?
婦人科を初めて訪れる場合、どのくらいの費用がかかるのか気になりますよね。
そこで、私の過去の領収書をもとに、初診と2回目以降の費用をざっくりとまとめてみました。
- 初診……1万円弱
- 2回目以降……2,000円から8,000円
医療機関のサイトを見ていても、だいたい初診は1万円前後かかることが多いようです。
2回目以降の診察は、検査の有無や内容によってかなり幅がありますが、私の場合は2,000円から8,000円あたりがほとんどです。

私の場合、追加で血液検査をおこなった日は、いつもより費用が高くなる傾向があります。
最近はキャッシュレス決済ができるクリニックも増えていますが、現金払いのみのクリニックも少なくありません。
「お金が足りないかも……!」という心配事を減らすためにも、余裕を持った金額を持って行くことをおすすめします。
生理や不正出血があっても受診はできる?
生理や不正出血で出血している場合でも、検査をおこなうことはできます。
私も、生理中や不正出血中に検査をしてもらったことがありますが、特に問題なく検査ができました。
ただし、私の担当医によると「あまりに出血量が多い場合は正しく検査ができない場合もある」とのこと。
もしも診察日に出血がある時は、事前にクリニックに問い合わせてみるのが安心です。

症状が重い場合は、早めの検査が必要になることもあるかもしれません。
もしも受診のタイミングに悩んだら、クリニックに相談するのが一番確実です!
受診に最適な時期は?
痛みや生理不順、不正出血などの症状が続いている場合は、早めの受診に越したことはありません。
ただし、もし「子宮内膜症」が疑われる場合は、生理終了後から排卵までの期間に行くことをおすすめします。
子宮内膜は生理前に厚くなり、生理後に薄くなるため、生理後の検査だと異常を発見しやすいためです。
診察予約を取るタイミングのひとつの目安として考えていただければ幸いです。

私は初受診が生理直前のタイミングだったので、生理終了後に再検査が必要となり、二度手間になってしまいました……。
10代・20代でも受診して大丈夫?
若い世代の方の中には、婦人科診察に抵抗を持っている方もいるかもしれません。
私も、最初に診察を受けたのは大学生の時だったので、とても不安でした。
しかし、いざ行ってみると、私と同世代くらい(と思われる)の方も多く来られていて、一気に安心したことを覚えています。
最近はテレビやSNSで婦人科系疾患が取り上げられる機会が増えているので、若い世代の方でも受診しやすくなっているように思います。
症状が重くなる前に、勇気を出して受診してみてほしいです。

現在も定期的に診察に行っていますが、私より若い世代の方も多く来られている印象です。
まとめ|症状に気づいた今が、心身を守るチャンス

本記事では、はじめて婦人科を受診する方へ向けて、受診の目安や診察の流れ、検査方法などを体験談をもとにお話させていただきました。
生理のトラブルで婦人科を受診するのは、女性として当たり前のことだと思います。
症状が気になっている今こそ、あなたの心と体を守るチャンスです。
どうか一人で抱え込まず、あなたの辛さを安心して相談できる場所を見つけてくださいね。