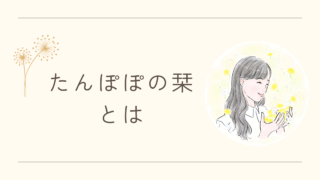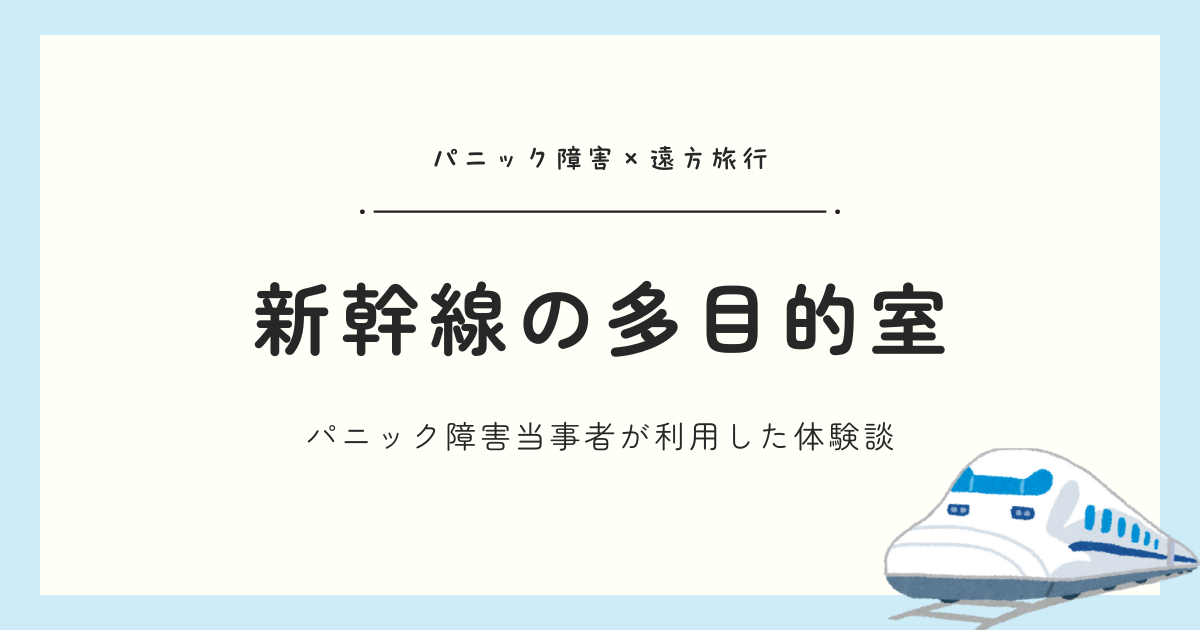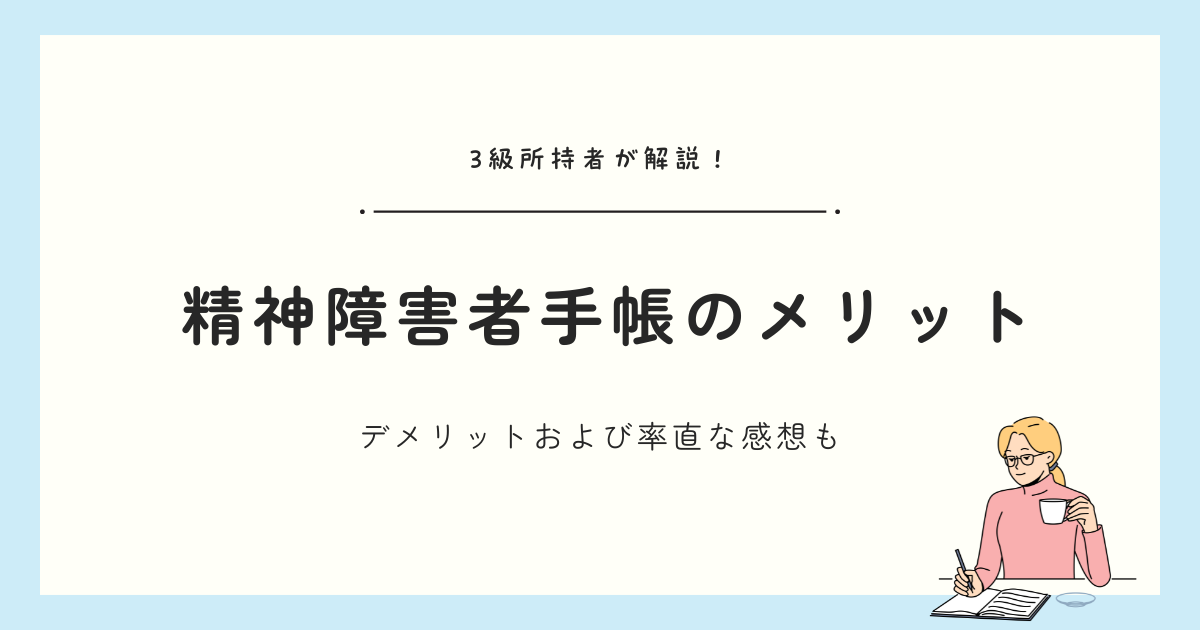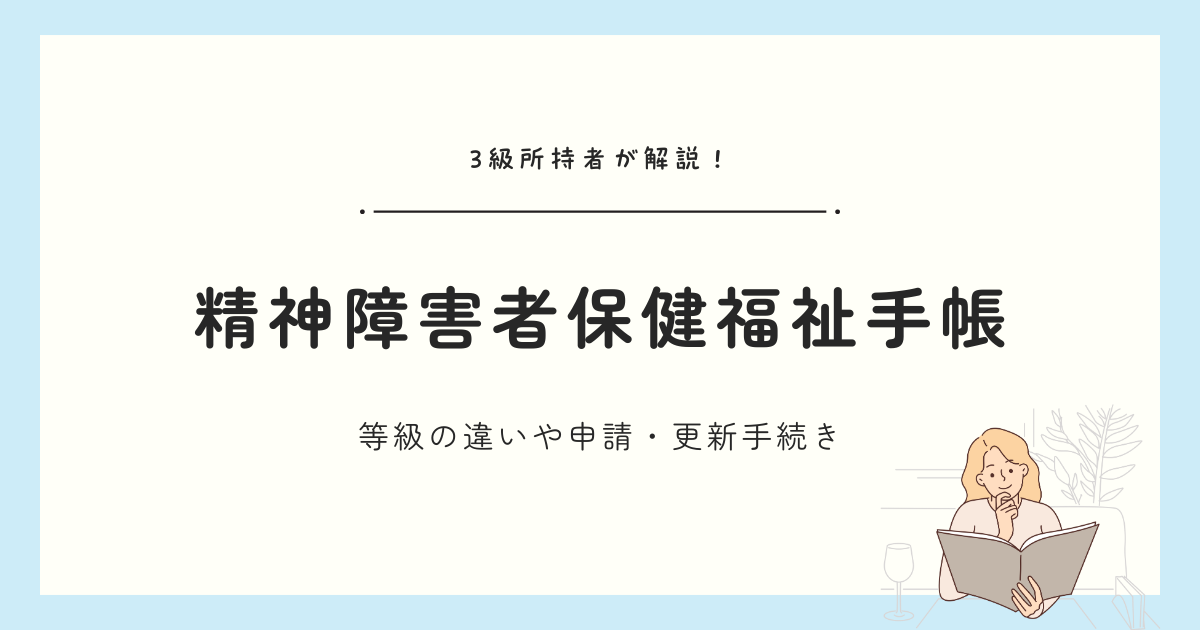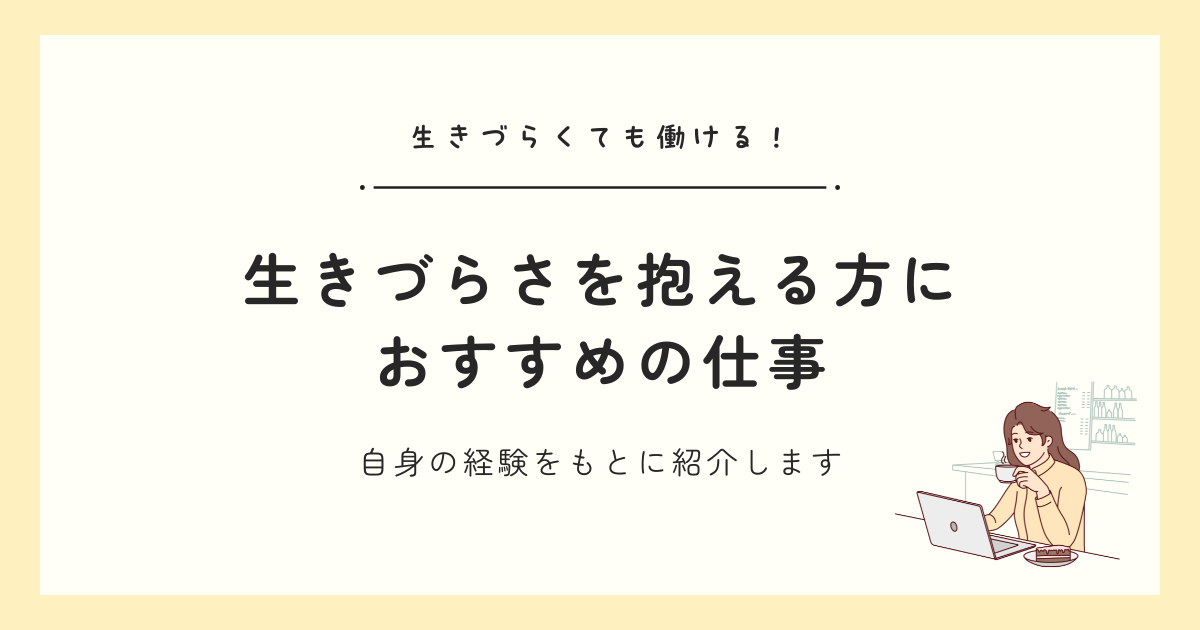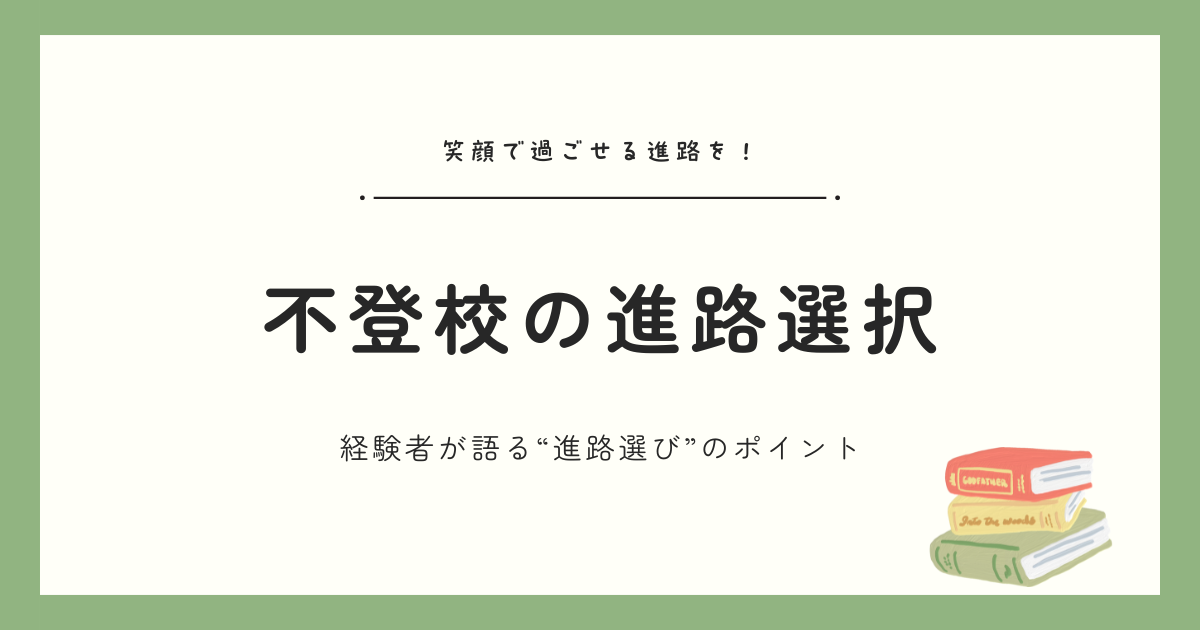【体験談あり】パニック障害で電車が怖いときに試したい7つの対処法

「パニック発作が怖くて、電車に乗るのが怖くなってしまった……」
そんなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
私も10代の頃からパニック障害を患っており、電車を利用するのが大の苦手です。
発作に対する不安があまりにも強すぎて、家から出られなくなってしまった経験もあります。
そこで本記事では、パニック障害と10年以上向き合い続けている私が、電車を利用する時におこなっている対処法や工夫をまとめました。
この記事を読んで、パニック障害の知識を深めながら、上手な対処法を見つけてみてくださいね。
パニック障害で電車に乗るのが怖い理由
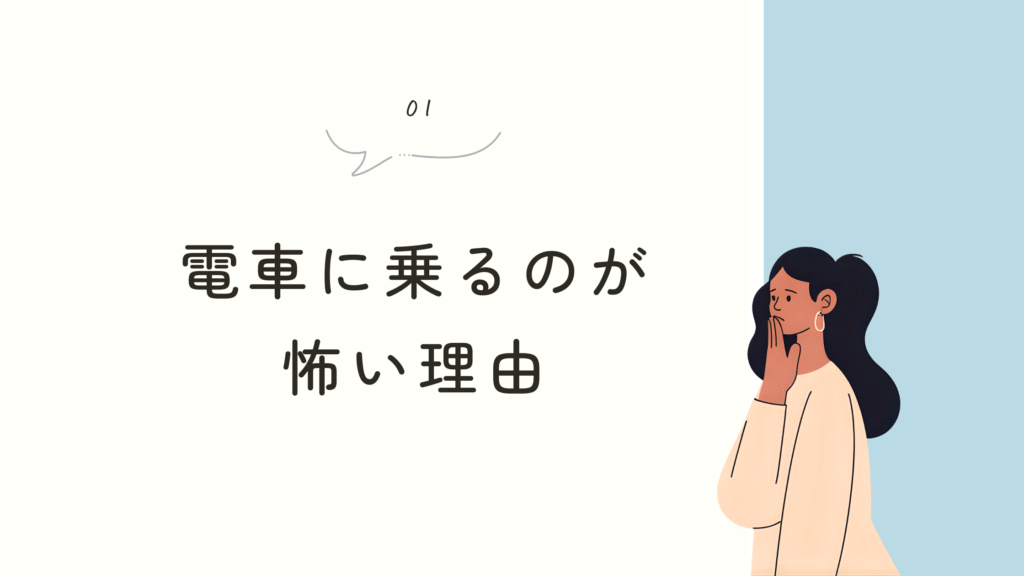
そもそも、パニック障害があるとなぜ電車になるのが怖くなってしまうのでしょうか?
この章では、電車利用に不安を感じる理由について、パニック障害当事者の目線で紹介します。
「周りの目」が気になってしまう
私が電車利用に恐怖を感じる一番の理由は「周りにどう見られるか?どう思われるか?」が気になるからです。
- もし発作を起こしてしまって、自分のせいで電車が遅れたらどうしよう
- 周りの人に変な目で見られたり、誰も助けてもらえなかったりしたら怖い
- 家族以外の人に「ふつう」とはちがう様子を見せたくない
- 私の症状によって、誰かに迷惑をかけたり、困らせたりしてしまうことがすごく嫌だし怖い
とにかく周囲の視線や反応が強く気になるため、電車利用を避けてしまうのです。

これは、私が社交不安障害(対人恐怖)を患っていることも大きく影響していると思います。
逃げ場がない「閉ざされた空間」の恐怖
電車は公共交通機関なので、一度乗ったらすぐに降りることができません。
特に、快速列車や特急列車は1駅の間隔が長く、なかなか降りられないため、
- もし途中でしんどくなっても降りられない……
という「逃げられない不安」が高まりやすく、乗車のハードルが上がります。
さらに、特急列車は混雑しやすく他人との距離が近くなるので、その圧迫感から余計に不安が強くなることも多いです。

満員電車に毎日乗っている人、本当に尊敬します……!
「また発作になるかも……」という予期不安が出る
パニック障害のしんどいところは「また発作が出たらどうしよう」という“予期不安”が強く出ることだと思います。
- 過去にパニック発作が出た体験を思い出して「また起きるかも……」と不安が高まってしまうことです。
- 過去の発作体験が一種の“トラウマ”になり、発作が出たシチュエーションに挑戦することを避けるようになる場合もあります。
私は過去に、電車利用中にパニック発作を起こした経験が複数回あります。
そのため、電車に乗る際はいつも「また発作が出てしんどくなったらどうしよう……」という予期不安が強く出ます。
頭では「大丈夫」と思っていても、心の危機察知能力が強すぎるがゆえに、胸のドキドキや胃のキリキリが止まらなくなります……。

これは、私が社交不安障害(対人恐怖)を患っていることも大きく影響していると思います。
予期不安や緊張が強すぎて疲れる
予期不安が強い時は、電車に乗る前からずっと気が張り詰めていて、体がとても緊張しています。
医学的に言うと、交感神経が過剰に働いて“戦闘モード”になってる状態だと思います。
そのため、たとえ発作なく電車に乗れたとしても、家に帰った瞬間どっと疲れてしまうことが多いです。
特に、2021年にうつ病を患って以降は疲労を感じやすくなり、2~3日寝込んでしまうので、
- 仮に発作が起きなかったとしても、このしんどさ(疲労感)が来るのが怖い……
という不安から、電車利用を避けることが増えました。

ただ電車に乗るだけで、数日間何もできなくなってしまうのはとてもキツイです……。
電車でパニック発作が起きそうな時の7つの対処法
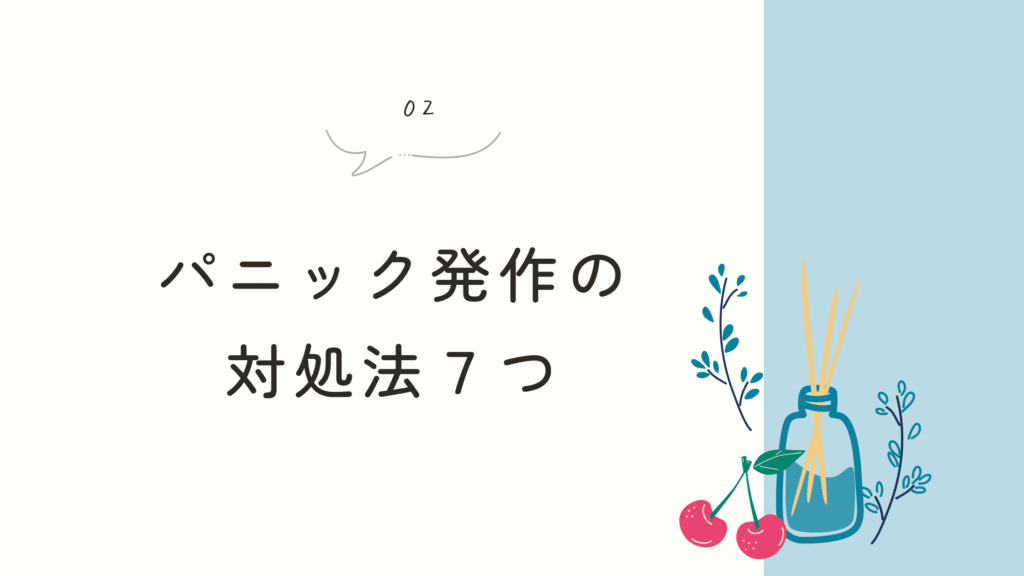
この章では、パニック障害歴10年以上の私が、電車でパニック発作が出そうな時に実践している対処法を7つ紹介します。
人によって合う・合わないはあると思いますが、少しでもご参考になれば幸いです。
アロマの匂いを嗅ぐ
1つ目は、アロマオイルの匂いを嗅ぐことです。
発作が起きそうな時にアロマの匂いを嗅ぐと、不思議と心がリラックスできて、緊張の波が落ち着きます。
- ラベンダー
- ベルガモット
- ティーツリー
- ヒノキ
- ペパーミント
上記の5つは優しくリラックスできる香りなので、個人的にはとてもおすすめです!
私はいつも、お気に入りのハンカチにオイルを数滴垂らし、鞄の中に忍ばせています。
ハンカチのふわふわした手触りも「緊張の軽減」に一役買ってくれますよ。

楽天ROOMでは、私が実際に使って良かったアロマ商品を紹介しています。
気になる方は、ぜひチェックしてみてください!
目を閉じてゆっくり呼吸する
2つ目は、目を閉じてゆっくりと呼吸をすることです。
電車内はとても人が多いので、目を閉じて、視覚からの刺激をゼロにするだけでもかなり落ち着きます。
先ほど紹介したアロマオイルを利用して、香りに意識を向けながら深呼吸をするのもおすすめです。


鼻ではなく口から息を吐く方が、よりリラックス効果が高まります。
タッピングをする
3つ目はタッピングをすることです。
指先のはらを使って体や顔を優しく叩き、ストレスや不安を軽減させるリラクゼーション方法です。
私は過去に、新幹線の中で発作が起きそうな時にタッピングをおこない、なんとか乗り越えられた経験があります。
乗客が多くて人目が気になる時は、体をさすったり、撫でたりする“簡易タッピング”をおこなうことも多いです。

ゆっくり体を撫でると不思議と気持ちが落ち着くので、自宅でも時々やっています。
体の力を緩める
4つ目は、電車に乗る前に体の力を緩めておくことです。
- 腕を伸ばす
- 肩を上げたり下げたりする
- 手のグーパー運動を繰り返す
不安や緊張が強い時は必ずと言っていいほど体に力が入っているので、できるだけ“脱力すること”を心がけています。
実際に体を動かさなくても「力を抜こう・リラックスしよう」と意識するだけでも、体の軽さが全然違うと感じます。

「力を抜こう~」と意識するだけなら、満員電車でもやりやすいとお思います。
体を温める
5つ目は、体を温めることです。
体を温めて血のめぐりを良くすると、手っ取り早く全身の力を緩めることができます。
私はいつも、夏以外の時期は、お腹部分にカイロを貼って外出しています。
服の上からお腹に手を当てると、じんわりとした温かさが伝わってきて安心できます。


個人的には、腹巻をする習慣をつけることもおすすめです!
スマホで動画を視聴する
6つ目は、スマホで好きな動画を視聴し、緊張から意識を逸らすことです。
- YouTubeチャンネル
- ドラマや映画
- 自分で撮影したお気に入りの動画
アロマやタッピングは「一時的な緊張を和らげる」という意味合いが強いです。
そのため、長時間移動の場合は、ある一定時間集中して楽しめるコンテンツがある方が安心します。

私はディズニーが好きなので、YouTubeでお気に入りパレードの動画を観ることが多いです。
「お守り」を持つ
7つ目は「お守り」を持つことです。
ここで言う“お守り”は、神社のお守りではなく「持っているだけで気持ちが安心できて、心を守ってくれるもの」です。
- 小さなぬいぐるみやストラップ
- 好きなアイドルやキャラクターのグッズ
鞄につけられたり、気軽に持ち運べたりするサイズのものなら何でもオッケーです!
私はいつも、ディズニーキャラクターの「ベイマックス」のぬいぐるみストラップを鞄につけています。

ぬいぐるみが目に入るだけでなんとなく安心しますし、ふわふわな触り心地もお気に入りです!
電車でのパニック発作を軽減する工夫
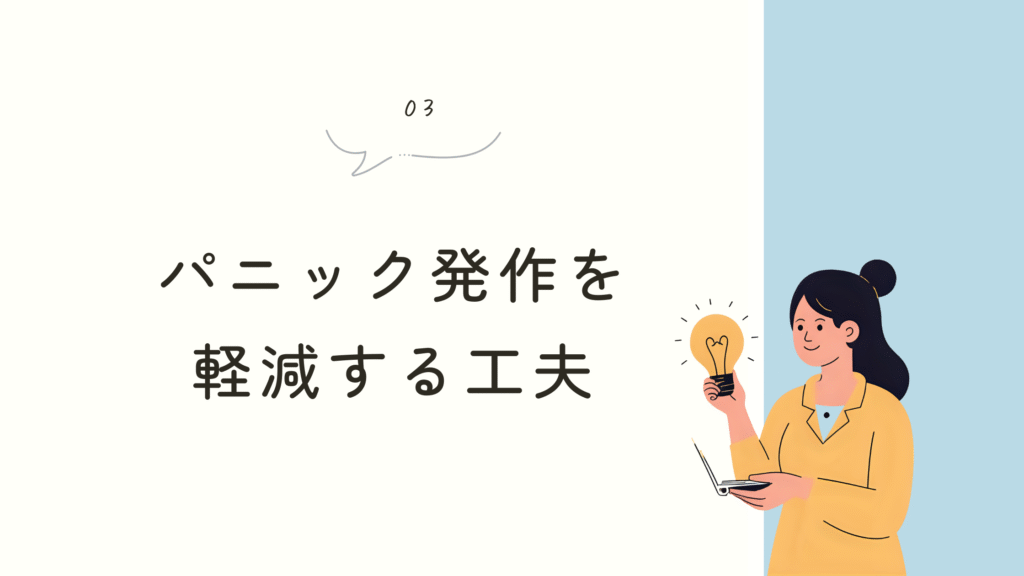
この章では、電車でのパニック発作を軽減するためにおこなっている工夫を6つ紹介します。
取り入れられそうなものがあれば、ぜひ参考にしてみてくださいね。
空いている車両を利用する
1つ目は、空いている車両を利用することです。
- 出発駅
- 終着駅
- 利用者が多い駅
どの電車も、上記3つの駅の改札や階段(エスカレーター)に近い車両は混雑する傾向があるように思います。
そこを避けて乗車するだけでも、ストレスの軽減=発作リスクの軽減に繋がることが多いと実感しています。

私はいつも、改札や階段の距離は無視し、なるべく人が少ない車両を探して乗るようにしています。
混雑時を避けて利用する
2つ目は、可能な範囲で混雑する時間帯を避けて乗車することです。
当たり前の話ですが、平日の朝や夕方の時間は、通勤・通学などで電車が大混雑します。
休日の場合も、朝10時を過ぎると徐々に混雑する傾向にあるようです。
そのため私は、できるだけ以下の時間帯に電車を利用するようにしています。
- 平日の11時から15時まで
- 休日の10時まで、もしくは20時以降
あくまでも私の経験に基づいた工夫ですが、ご参考になれば幸いです。

私の体感だと、平日の12時から13時半までの間が一番平和に乗車できる印象です。
有料座席を利用する
3つ目は、有料座席を利用することです。
特急列車や新幹線など、一部の電車には「有料座席(指定席)」が用意されています。
有料座席はある程度のプライベート空間が確保できるので、通常の座席よりも発作のリスクを軽減できます。
私はここ数年、遠方に出かける予定がある際は必ず有料座席を予約するようにしています。
もちろん、余計に費用はかかってしまうのですが、お金を払う価値は十分にあると思います。

パニック障害持ちさんが新幹線に乗る場合は「多目的室」という個室を利用することも可能です。
ご興味がある方は、以下の記事をご覧ください!
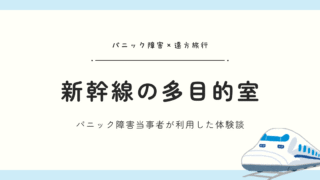
途中下車して休憩する
4つ目は、途中で電車を降りて休憩することです。
もしも乗車中に発作が出そうになった場合、時間に余裕があれば、いったん電車を降りてしまうのもひとつの方法だと思います。
電車を降りて休憩すると、張り詰めた緊張感が一気に緩和され、緊張や不安が落ち着きます。
長い人生、時には立ち止まって休む時間も必要だと思います。
焦らずゆっくり、ご自身の心と体を大切に進んでいきましょう!
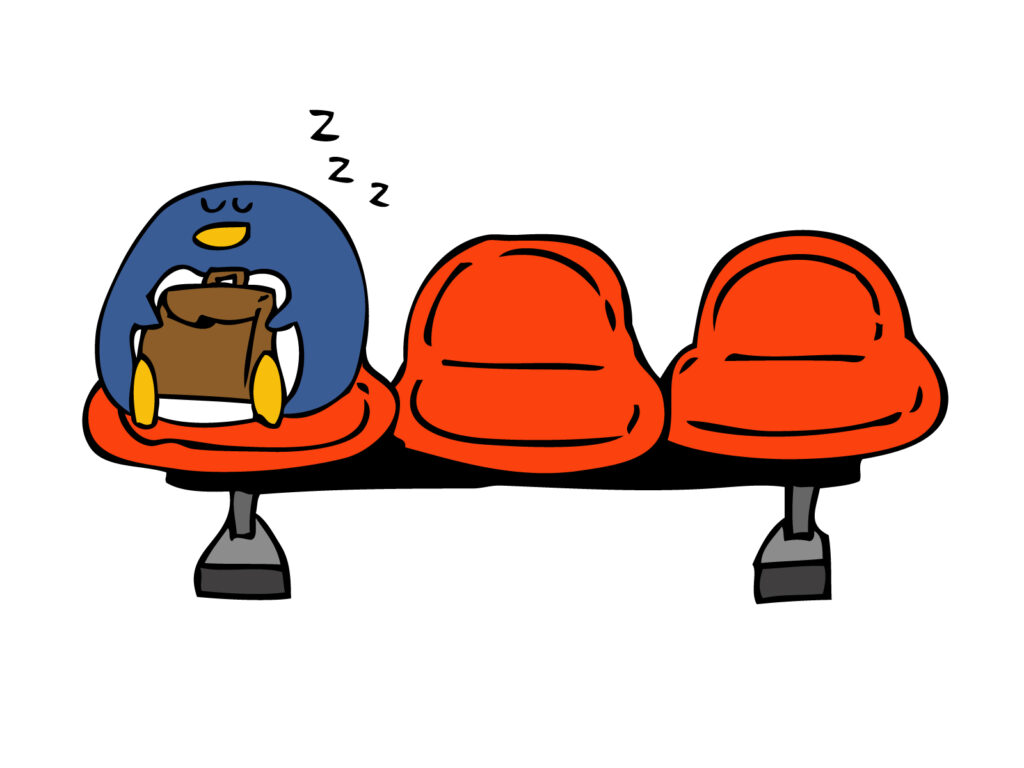

大学生の時、地下鉄を途中下車して休憩し、数本分の電車を見送ってから大学に行ったことが多々ありました。
家族に付き添ってもらう
5つ目は、家族に付き添ってもらうことです。
- 少し遠い場所に行く時(旅行を含め)
- 体調が思わしくなく、一人で電車に乗れる自信ががない時
このような時は、父母のどちらかに付き添いをお願いすることが多いです。
「万が一の場合は知っている人が助けてくれる」という安心感は、パニックの軽減とストレスの緩和につながります。
もしもご家族がパニック発作に理解のある方ならば、付き添いをお願いしてみても良いと思います。

少し遠い場所行く時は、私よりも父母の方がお出かけタイムを楽しんでいる感じです(笑)
車やバイクで移動する
6つ目は、車やバイクを有効活用することです。
私はもともとドライブ好きのため、どうしても電車を利用しなければいけない状況以外は、自家用車で移動しています。
生きづらさは「乗り越えるもの」ではなく、上手に向き合って生かしていくものだと思います。
無理に電車を克服するのではなく、車移動やバイク旅を思いっきり楽しむのも、立派な生き方のひとつではないでしょうか。


生き方の正解は、ひとつではありません。
ご自身が心から安心して、ストレスなく移動できる方法を見つけることが一番大事です!
まとめ|焦らずゆっくり、あなたに合った対処法を見つけましょう!
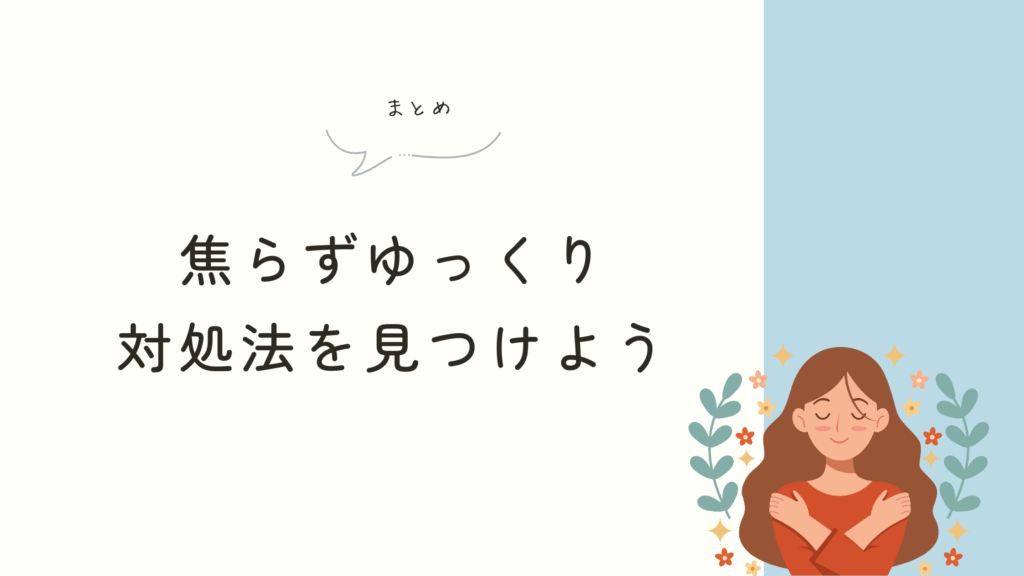
本記事では、パニック障害当事者の私が電車を利用時ににおこなっている対処法や工夫を紹介しました。
パニック障害が影響してひきこもりになってしまったり、学校や仕事に行けなくなってしまうケースは少なくありません。
けれど、対処法や工夫次第では、たとえパニック障害があっても電車を利用できる場合もあります。
あなたのペースで、あなたに合った方法で、焦らずゆっくりパニック障害と向き合ってみてください。
その地道な作業は、いつかきっと、あなたを支える人生の糧になるはずです。
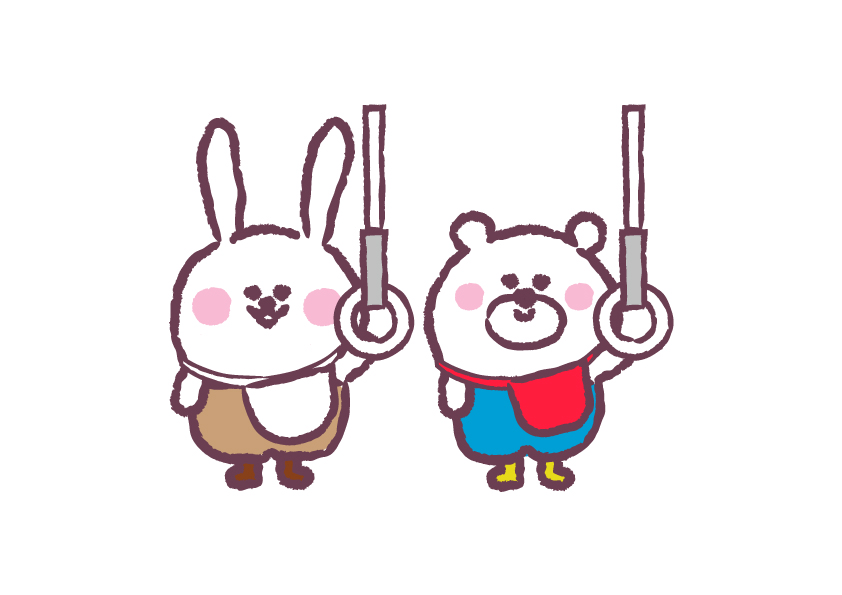

以下の記事の「努力で解決できないこともある」という項目にも、自身のパニック障害について綴っています。
もしご興味がある方は、こちらもぜひ読んでくださると嬉しいです!