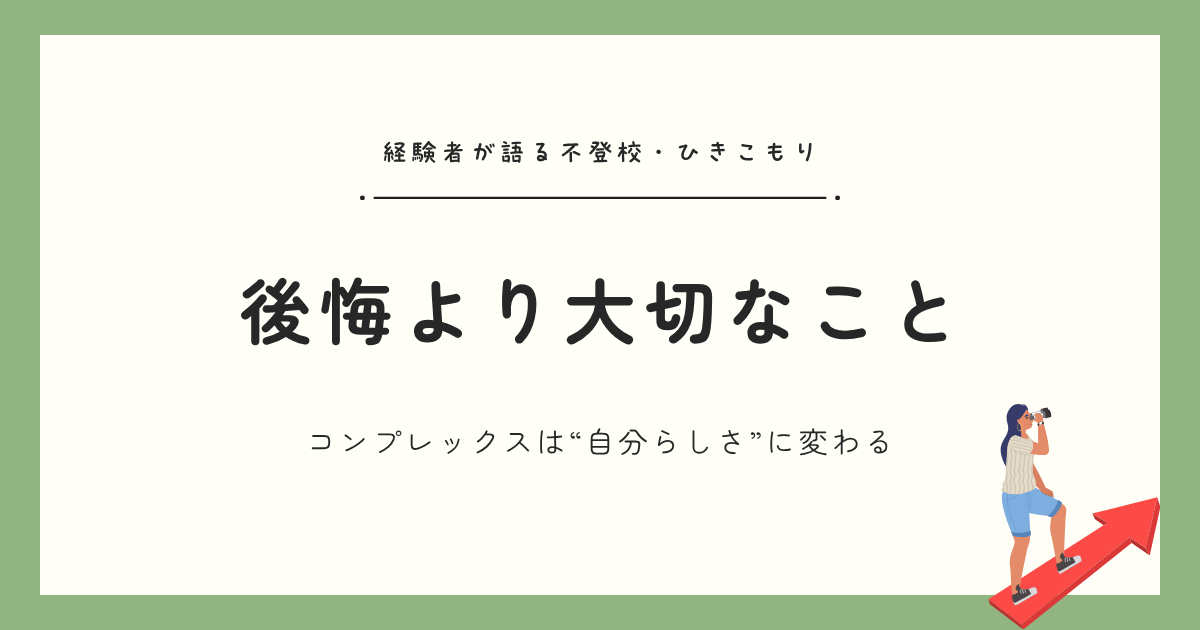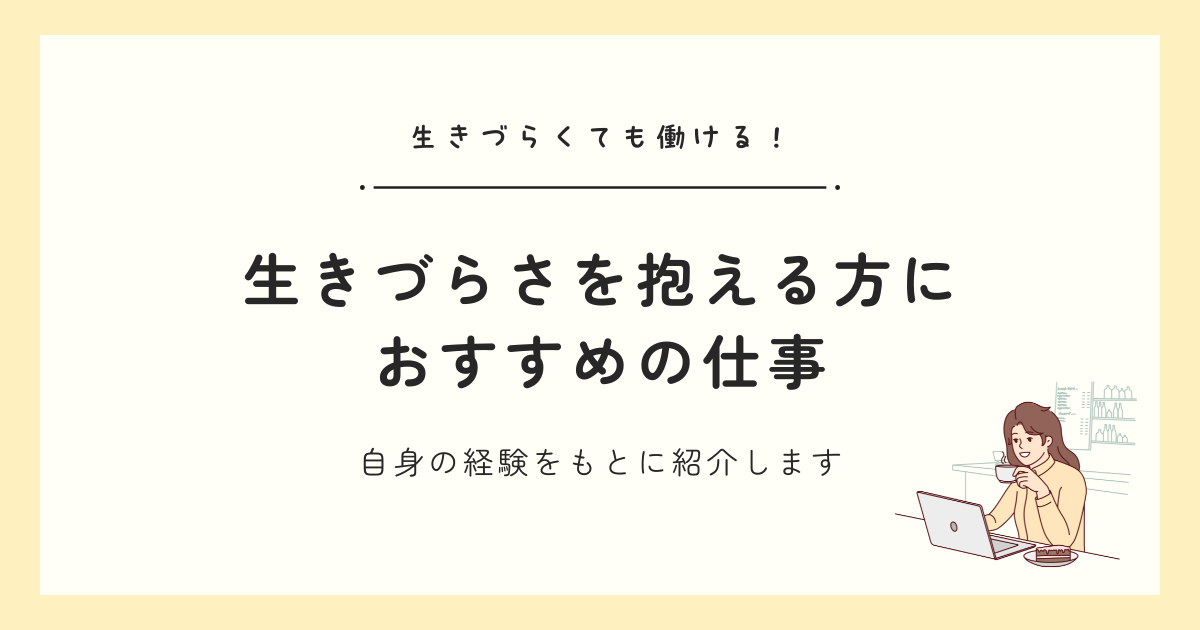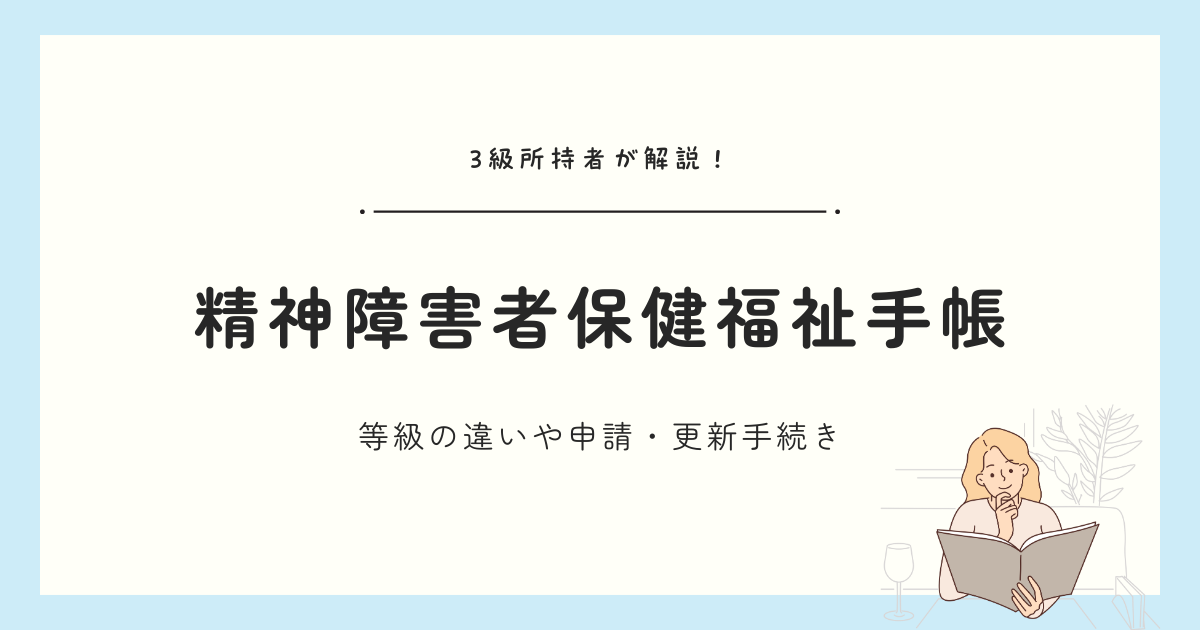不登校のお子さまにおすすめの進路とは?不登校経験者が選び方のポイントを解説します
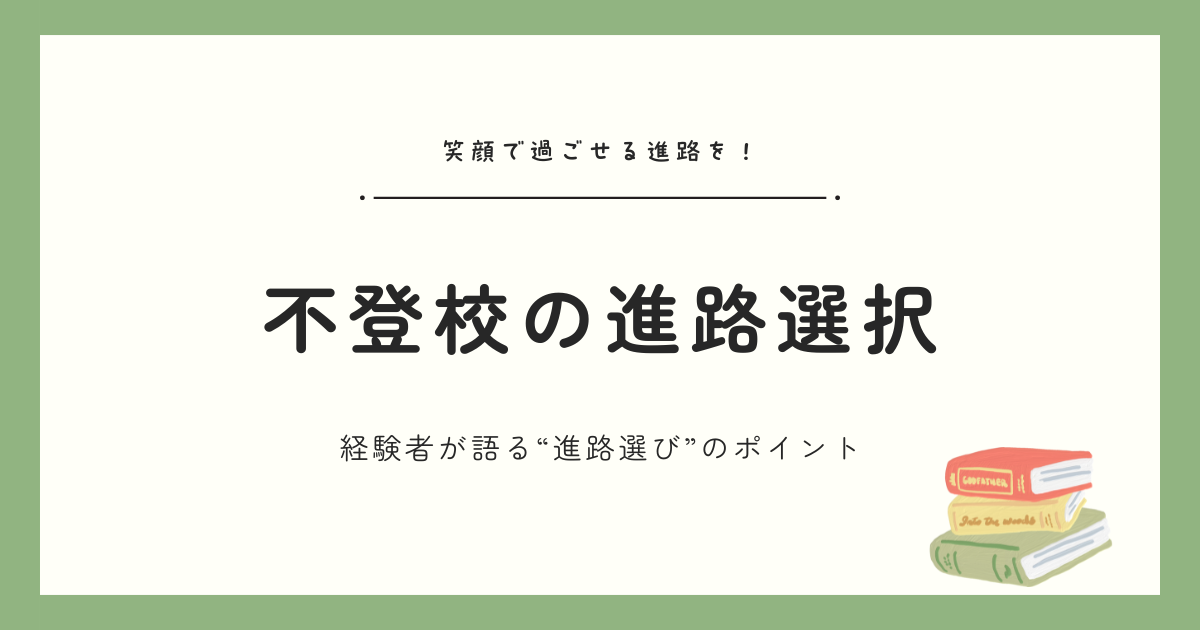
不登校を経験した場合の一番大きな壁は「その後の進路をどうするのか」だと思います。
「これからどうなるのか不安でいっぱい」
「どんな進路がうちの子に合っているのかわからない」
そんなふうに悩む保護者の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不登校だった私が実際に体験した進路の中から、中学卒業後以降におすすめしたい進路を5つ紹介します。
記事の後半では、自身の不登校経験をもとに「不登校のお子さまが進路を選ぶ際のポイント」についても綴っています。
お子さまの進路に不安を感じている方は、ぜひご覧ください。
- 不登校のお子さまに合う「進路」がわからない保護者の方
- お子さまに合う進路を見つけるための「ポイント」を知りたい保護者の方
- 不登校経験者の意見や体験談を参考にしたい方
不登校のおすすめ進路
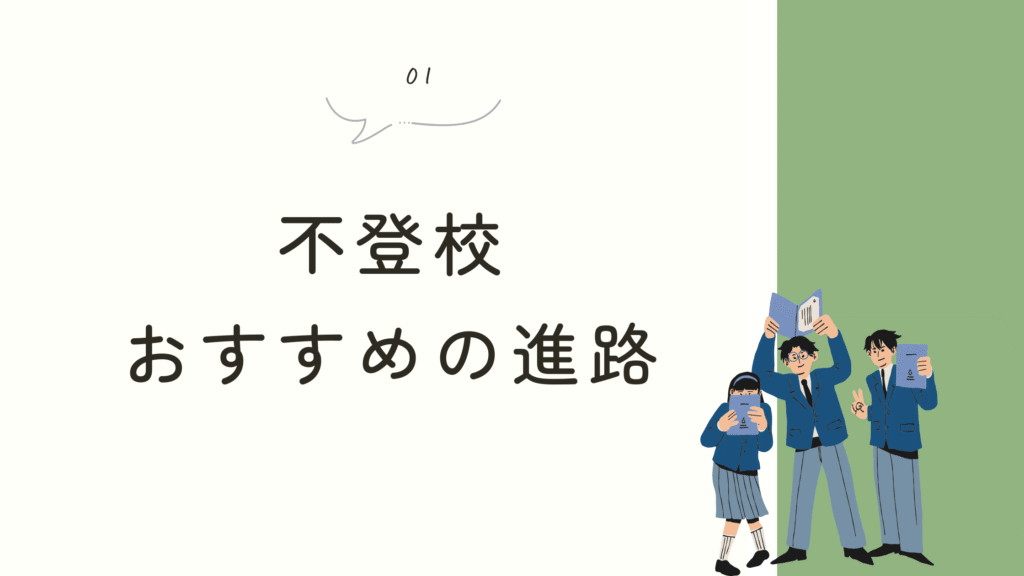
この章では「不登校だった私がおすすめしたい、中学卒業後以降の進路」を5つ紹介します。
少しでも参考になる部分があれば幸いです!
通信制高校
1つ目は、通信制高校に行くことです。
通信制高校は、全日制高校と違って毎日学校へ通う必要がなく、比較的自由が利きやすいです。
そのため、中学時点で不登校経験があるお子さまにとって、選びやすい進路のひとつだと思います。
- 対面授業ではなく、オンライン学習やレポート提出がメインとなることが多い
- 朝から夕方までみっちり通う必要がなく、自分のライフスタイルに合わせて学習計画を立てられる
- 学校によっては、全日制高校と同じような感じでクラブ活動や行事、修学旅行などもある
通信制高校は、高校ごとにいろんな特色があるので、それぞれの高校ならではの良さや魅力があります。
気になる高校のパンフレットを取り寄せたり、実際に見学に行ったりして、お子さまに合いそうなところを選ぶのがおすすめだと思います。
私も何校か見学に行き、一番相性が良さそうな高校に入学しました。
不登校に理解がある優しい先生や、おもしろい授業をしてくれる先生が揃っていたので、居心地はすごく良かったです。

残念ながら、体調不良が治らず退学してしまいましたが、体調が良ければもっと通いたかった学校でした。
高校卒業程度認定試験
2つ目は、高校卒業程度認定試験(高卒認定)の受験です。
以前は「大学入学資格検定(大検)」と呼ばれていましたが、平成17年から現在の名称に変更されました。
高卒認定に合格すると「高校卒業と同程度の学力がある」と見なされ、大学や専門学校などの受験が可能になります。
つまり、高卒認定は、高校に通わずに大学受験を目指せる(高卒の資格が取れる)唯一の手段でもあるのです。
「高校に通うことは難しいけど、大学受験はしたい」というお子さまには、かなりおすすめの進路だと思います。
- 16歳以上なら誰でも受験可能
- 全国各地の会場で、8月と11月に試験が開催される
- 中3~高1レベルの基礎知識が出題され、すべてマーク式
- 合格ラインは4割程度
- もし不合格になっても、何度でも再挑戦が可能
高卒認定の科目数は、8~9です(2026年度以降は9~10になります)。
しかし、高校で取得した単位がある場合や、英検などの資格がある場合は、受験科目を減らせるケースもあります。
私は、通信制高校で取得した単位が少しだけあったので、3科目の受験で合格することができました。
詳しい情報は、文部科学省の『高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)』のページをご確認ください。

試験内容が気になる方は、ネットや書籍で販売されている「過去問集」を参考にしてみてください!
通信制(通信課程)大学
3つ目は、通信制大学に行くことです。
通信制大学はオンライン学習がメインのため、通学回数がとても少ないです。大学によっては、ほとんど通学しないところもあります。
そのため、不登校歴が長かったり、体調や対人関係に不安があったりして「大学には行きたいけど通える自信がない……」というお子さまにおすすめです。
私が在籍していた大学の通学頻度は、月に1回から2回でしたが、通学のタイミングは自分で自由に選べたのですごくありたがかったです。

現在はさらにオンライン化が進んだらしく、履修科目によっては通学なしで卒業できるケースもあるみたいです。
もし通学課程が併設されている大学であれば、2年次もしくは3年次に通学課程へ転籍できる場合もあります。
私も、体調がある程度回復した3年次に通学課程へ転籍し、念願のキャンパスライフを送ることができました……!
ただし、転籍制度の有無や詳細は、大学によって異なりますので、詳しい情報は各大学に問い合わせてみてくださいね。
習い事
4つ目は、習い事に通うことです。
私は小学4年生の頃から近所の学習塾に通っていたのですが、その塾は、中学生で不登校になってからも引き続き通っていました。
もちろん、ずっと順調に通えていたわけではなかったですし、授業を欠席したり、遅刻や早退をしたりすることも多々ありました。
けれど、自宅と学校以外の居場所があったことは、当時の私にとってかなりの救いになっていたように思います。

不登校になる前から私を知っている先生や友人が多かったので、変に気を遣われることがなくてありがたかったです。
私の場合は「学習塾」でしたが、音楽やスポーツ、英会話やプログラミングなど、お子さまが好きなことを極めるのが一番良いと思います。
最近はネット上でレッスンや講義を受けられる習い事も増えているので、外出が難しいお子さまは、そちらを利用してみるのもおすすめです。
アルバイト
5つ目は、アルバイトをすることです。
学校はしんどいけど、それ以外の場所なら大丈夫そう!
そんな思いを持つ高校生以上の方におすすめの進路です。
私が初めてアルバイトを経験したのは19歳でしたが「社会の一員として働いてお金を稼いでいる」という実感は、大きな自信につながりました。
「最初から長期のバイトをするのは不安……」というお子さまは、1日のみの単発バイトから始めてみるのもおすすめだと思います。
どんな職種の仕事でもさまざまなことを学べるので、自分の未来を考えるきっかけのひとつになるはずです!

ちなみに、私の初アルバイトはTOEICの試験監督でした(1日のみの単発バイトです)。
不登校の進路選びのポイント
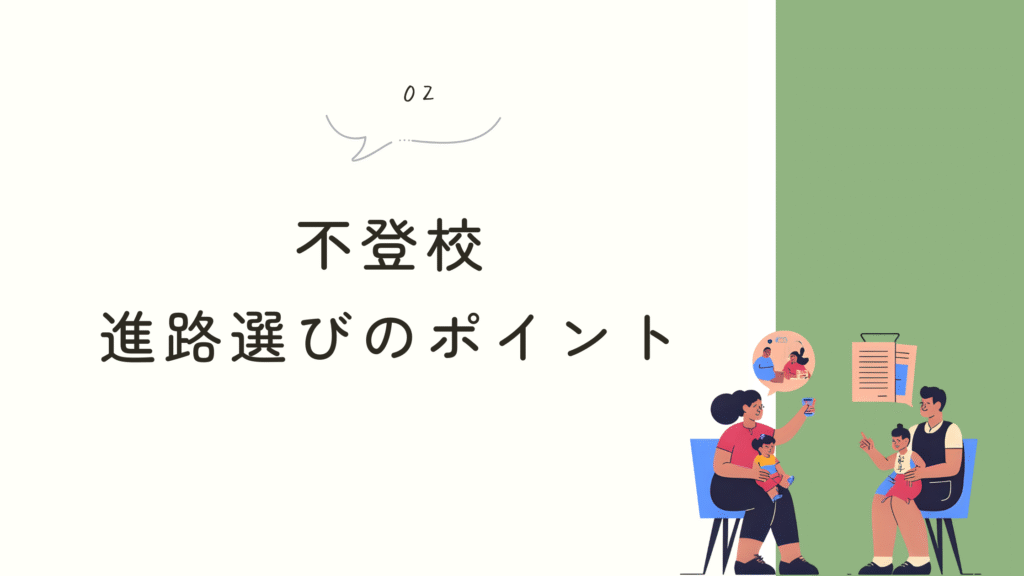
この章では、自身の体験談を踏まえながら「不登校になった場合の進路選びのポイント」を紹介したいと思います。
さまざまな壁にぶつかった私だからこそお話できる経験談をたっぷりと詰め込みました。
ピンときた項目があれば、ぜひ参考にしてみてくださいね。
子どもの気持ちを最優先に考える
1つ目は、お子さまの気持ちを最優先に考えることです。
私は過去に、学校を3回退学した経験があるのですが、その一番の理由は「周りの目を気にして無理をしてしまったから」です。
本当は学校に行きたくなかった(行ける状態ではなかった)のに「周囲から色眼鏡で見られたくない」という思いから、無理して進学してしまったのです。

「両親を安心させたい」「これ以上困らせたくない」という思いも、無理をしてしまった要因のひとつでした。
不登校に対する社会の偏見は、未だに根強いです。そのため、
- 周りから色眼鏡で見られることが怖いから、学校に行かせたい
- 不登校だと将来が不安だから、できるだけちゃんと行ってほしい
というような気持ちを持つ保護者さまも少なくないと思いますし、お子さまも同じような気持ちだと思います。

だからこそ「学校に行かなければいけないのに、どうしても行けない……」というギャップに苦しむ子どもが多いんですよね。
しかし、お子さまの人生は、お子さまが幸せになるためにあるものです。
周囲を気にして無理やり登校したり、本心とは違う進路を選んだりするのは、あまり良いこととは言えません。
可能な範囲でお子さまの希望に沿う道を選び、お子さまの心身を大切に守ってあげるのが一番だと思います。

合わなかったらやめる
2つ目は、進路が合わない場合はスパッとやめるということです。
たくさん悩んで決めた進路だとしても、いざその場所に身を置いてみると「思ってたのと違ったなあ……」と感じることもあると思います。
そんな時は、なるべく早くその環境から離れた方が良いです。

私は、全日制高校で二度目の不登校になった時、退学の決断をするまで約半年かかりました。
やめたい気持ちはその前からありましたが、いろんな不安や恐怖が強く、ずっと決断できずにいたのです。
しかし、私たち人間は、数々の「トライ&エラー」を繰り返しながら成長していくものだと思います。
より良い人生を過ごすために環境を変えるのは悪いことではなく、むしろ「良いこと」なのではないでしょうか。
その時のお子さまの状況にふさわしい選択をし続けることが、幸せへの一番の近道だと思います。

「絶対にこの決断を失敗させてはならない」と思いすぎず、風のように、軽やかに生きましょう!
学校や居場所にとらわれない
3つ目は、学校やフリースクールをはじめとした、さまざまな“居場所・学びの場”にとらわれないということです。
- 別の学校に転校・編入した方がいいのかな?
- 近くのフリースクールやフリースペースに行かせるべきなのかな?
お子さまが不登校になった時、上記のようなことを考える保護者の方は多いと思います。
しかし、学校や居場所に属することだけが「進路」ではありません。子どもの進路や生き方は、それ以外にもたくさんあります。
進路とは本来、子どもが笑顔で、幸せに過ごせる生き方を選ぶことだと思います。
「どこかに属すること」にとらわれすぎず、お子さまが笑顔でいられる生き方を一緒に考えてあげてほしいと思います。
とにかく情報を集める
4つ目は、とにかく情報を集めることです。
私は約6年間の不登校を経験しましたが、その期間中はずっと心が晴れることなく、モヤモヤした毎日を過ごしていました。
その一番の理由は、不登校になった場合の進路や選択肢に関する情報がまったく得られず、将来の見通しが立たなかったからです。

人間が不安を感じる時は、悩んでいる事柄への情報が不足していて、今後の未来が想像できない時が多いです。
そのため、少しでも不安を解消するためには、できるだけ多くの情報を集め、未来への大まかな道筋がイメージできる状態を作る必要があります。
今はとても便利な時代なので、ネット検索や書籍、SNSなど、いろんな媒体を使って手軽に情報をゲットすることができます。
ご自身に合う手段で、できるだけ多くの情報を集めてみてください。

当ブログや関連SNSも、ぜひたくさん活用していただけると幸いです!
ハンデは「人生の糧」になる
5つ目は、ハンデは「人生の糧」になるということです。
不登校のお子さまの中には、同級生と同じタイミングで学校を卒業したり、就職したりすることが難しい方もいらっしゃると思います。
私も、大学卒業時は同級生と2年のハンデがありましたし、大学院修了時に至っては、うつ病で休学したため3年のハンデに増えました。
しかし、卒業する時期が遅れたからこそ出会えた人、得られたものも多くあり、それらの経験は私にたくさんの幸せを与えてくれました。
どんな経験も、いつか必ず人生の糧になります。慌てず、焦らず、ゆっくりと光を見つけてくださいね。

最初は数年のハンデを引け目に感じていましたが、今は「ハンデがあって良かった」と心から思っています!
「何もしない 」のもひとつの選択肢
何もしたくない場合や体調に自信がないお子さまは、無理に前へ進む必要はないと思います。
一番大切なのは、お子さまのタイミングで、お子さまに合う進路や生き方を選ぶことです。
その生き方を見つけるために、少し立ち止まって色々なことを見たり、考えたりするのもひとつの選択肢なのではないでしょうか。
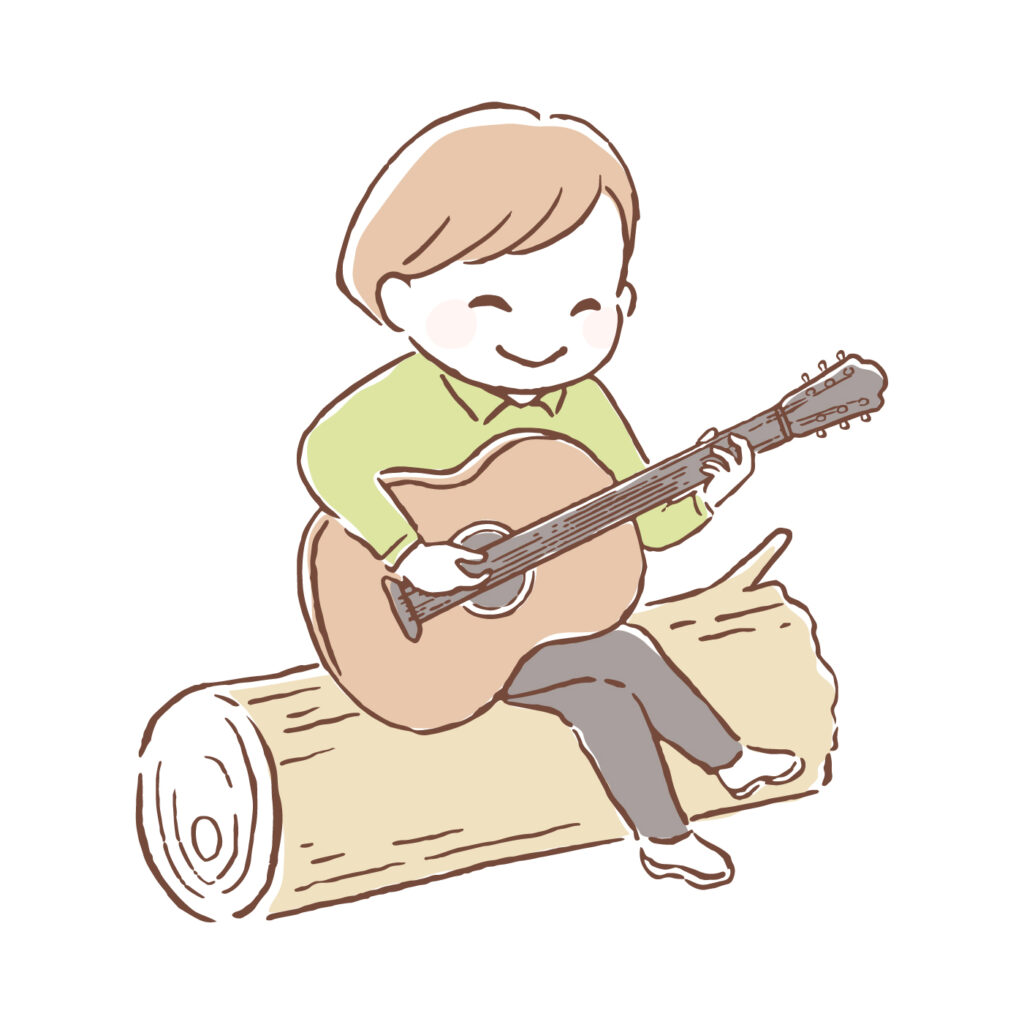
学ぶことや働くことに、年齢制限はありません。
世間体や周囲の目に左右されず、お子さまのペースを大事にしながら歩みを進めてほしいと思います。

私が大学に入学した時のように「頑張ってやってみよう!」と心から思えた時が、行動を起こす一番のタイミングだと思います。
まとめ|不登校の進路に「正解」はない
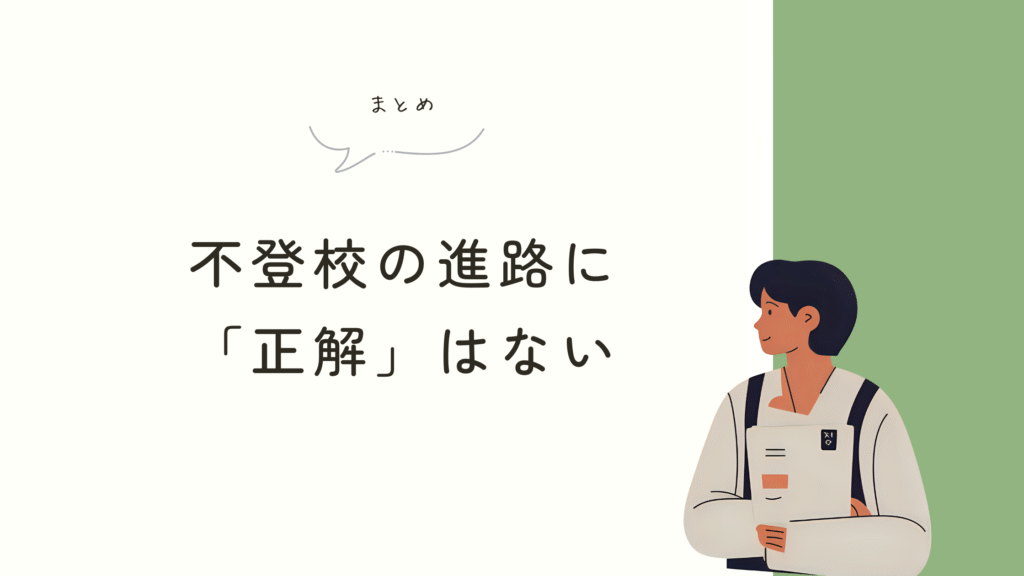
本記事では、不登校になった場合の進路について、おすすめの進路や「選び方のポイント」を経験談に基づいて紹介しました。
不登校のお子さまに限った話ではないですが、人生の歩みや生き方は人それぞれです。
100人いれば100通りの生き方がありますし、それらに正解・不正解はありません。
常識や正しさを追い求めるのではなく、お子さまが自分らしく、幸せに過ごせる生き方を選択するのが一番だと思います。
すべてのお子さまが笑顔で、自身をもって歩める道を見つけることができますよう、心から願っています。