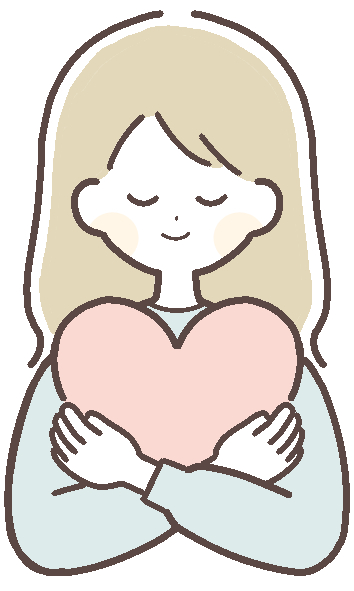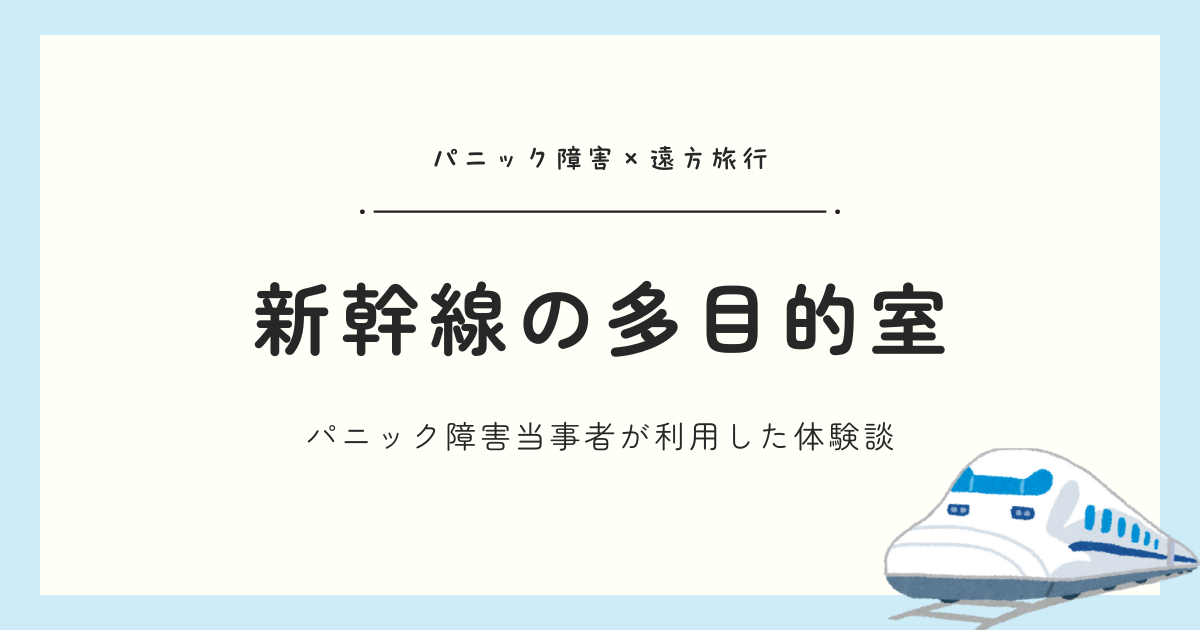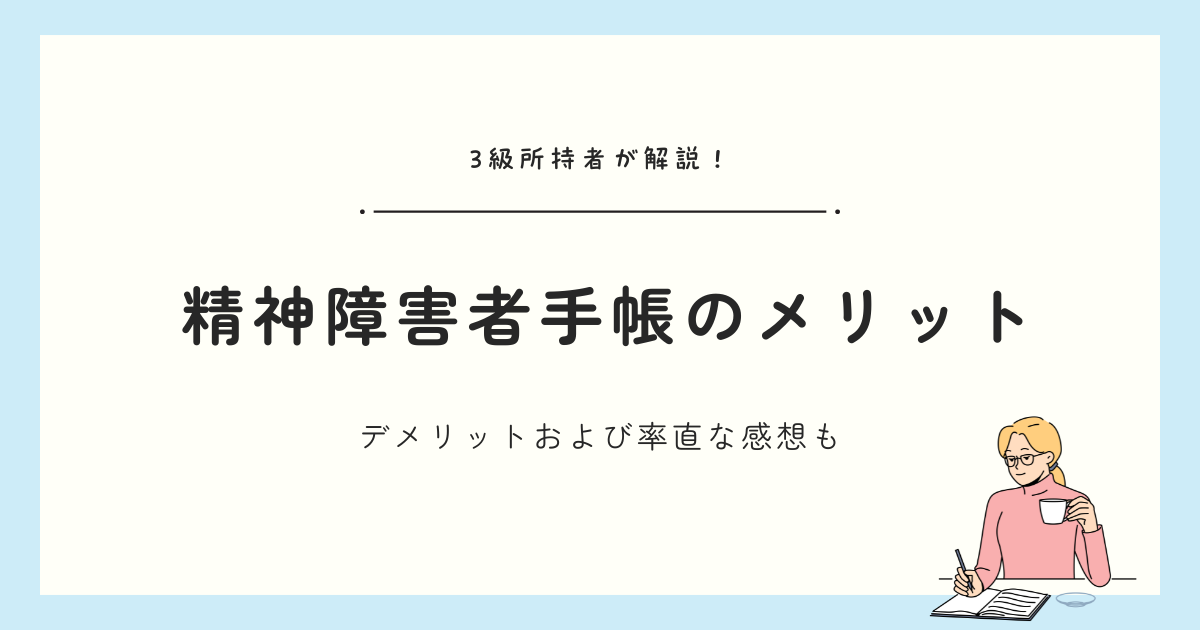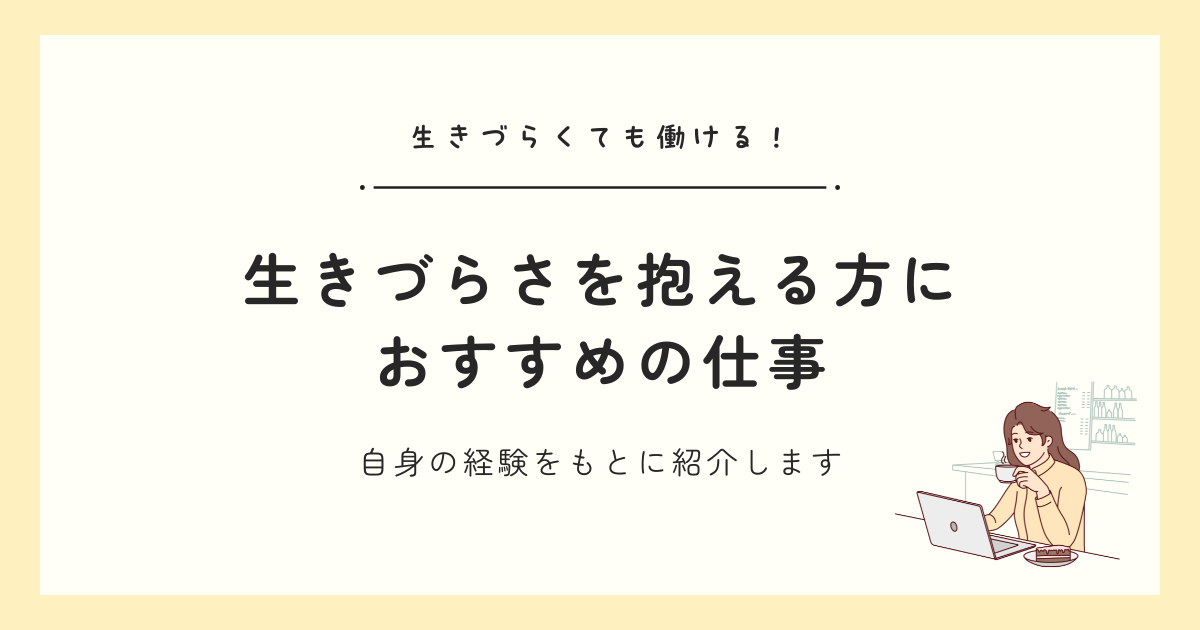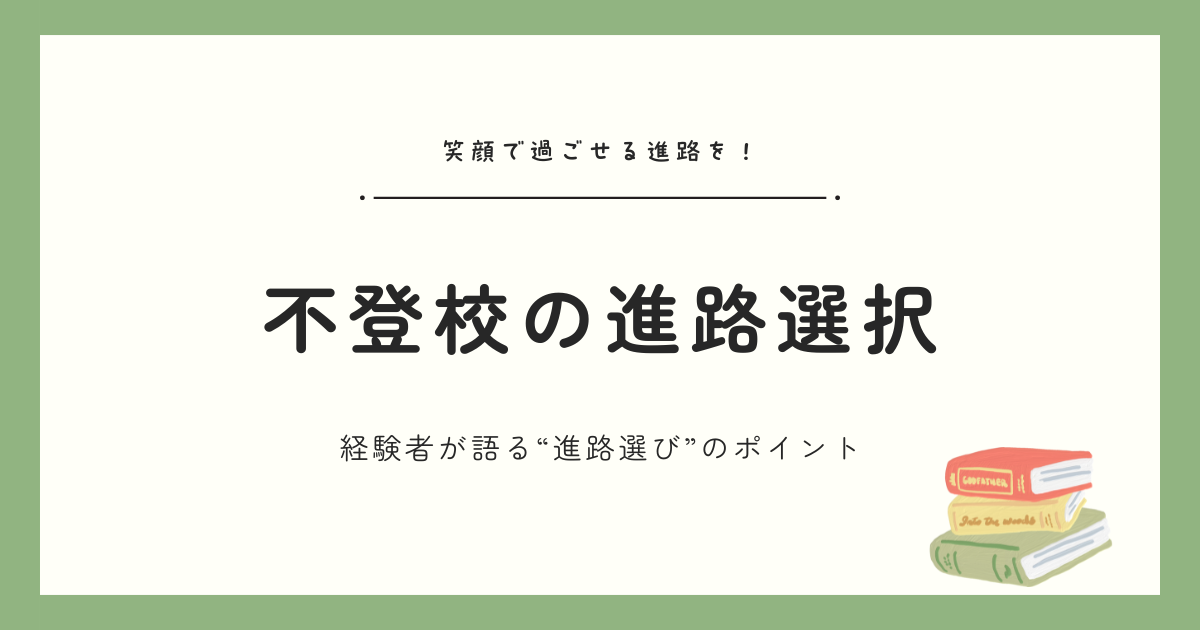精神障害者保健福祉手帳とは?等級や申請、メリットを3級所持者がやさしく解説
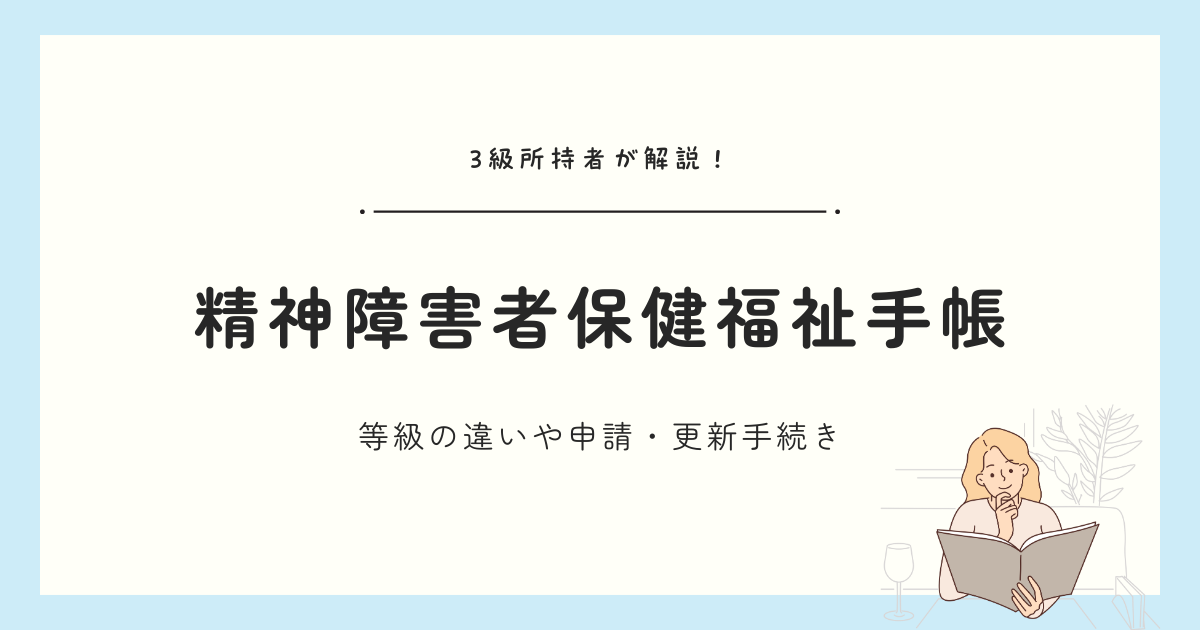
「精神障害者保健福祉手帳の等級って、なにを基準に決められているの?」
「手帳を申請したいけど、手続きの方法がよくわからない……」
84万人以上の方が所持している※①精神障害者保健福祉手帳。
しかし、申請方法や制度が少し複雑なため、その実態をよく知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、3級の手帳を所持する運営者が精神障害者保健福祉手帳の申請・更新方法について、体験談をもとにまとめてみました。
等級の違いや手帳を持つメリットなども、手帳所持者ならではの視点から紹介しています。
精神障害者手帳のことを詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。

精神障害者保健福祉手帳は「精神障害者手帳」と略されることが多いので、当ブログでもそのように表記します。
- 精神障害者手帳の詳しい情報や、基礎知識がわからない方
- 手帳を持っている人のリアルな体験談を知りたい方
※①:厚生労働省「『平成 28 年 生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査』の結果を公表します」(2019)より。
精神障害者保健福祉手帳とは
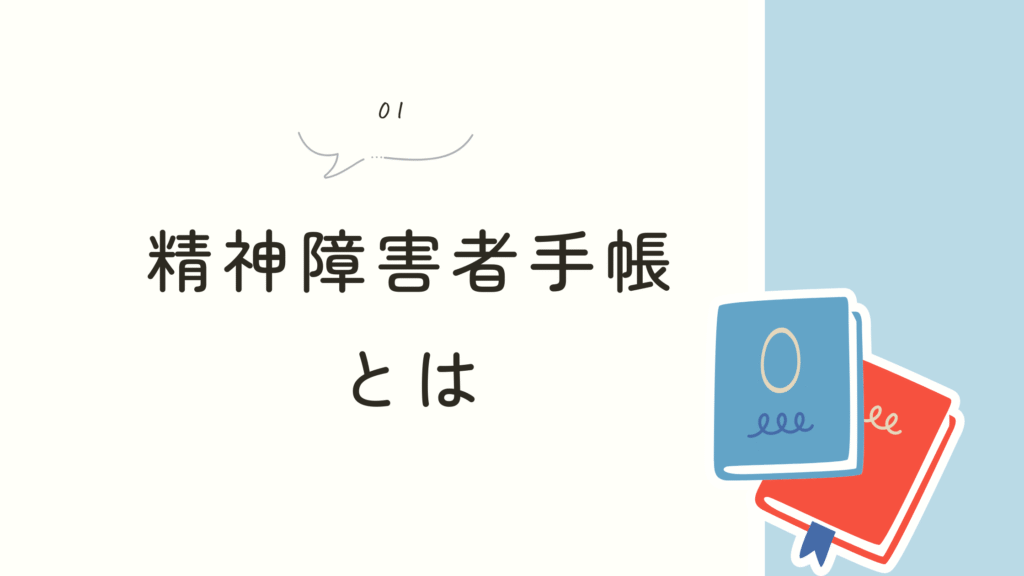
この章では手帳の概要やサービス、等級の違いなどを体験談をもとに紹介します。
「そもそも精神障害者手帳ってなに?」という疑問を持っている方は、ぜひ参考にしてみてください!
精神障害者手帳の概要
精神障害者保健福祉手帳は、うつ病やパニック障害、発達障害をはじめとした“精神障害”を抱える方を対象とした手帳です。
手帳を持つと、公共交通機関の割引や税金の控除、公営住宅の優先入居など、さまざまなサービス・サポートを受けられるようになります。
精神障害があると、当たり前の社会生活が送りづらいケースも多々あると思います。
そのような方たちが「よりスムーズな社会生活を送れるように」という目的で作られたのが、精神障害者手帳です。
手帳そのものは無料で受け取れますが、手帳を作るためには、医師の診断書や申請書などの書類が必要です。

申請方法について詳しく知りたい方は【申請手続きの体験談】の項目をご確認ください。
等級の違い
精神障害者手帳は1級から3級まで3種類の等級があり、数字が小さいほど「重度の精神障害がある」と見なされます。
専門家による審査を経て等級が決まるため、自分で選ぶことはできません。
具体的な等級の判断基準は、厚生労働省のサイトに記載のとおりです。以下に、一部抜粋します。
| 1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不要ならしめる程度のもの |
| 2級 | 精神障害であって、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 3級 | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
等級の決まり方(体験談)
私は2022年から3級の手帳を所持しています。2024年に更新手続きをおこない、新しい診断書を提出しましたが、等級の変化はありありませんでした。
そこで、あくまでも参考程度ですが、私が手帳を申請した時(2022年3月)と更新した時(2024年3月)の状態・症状を以下にまとめてました。
- 「うつ病」と診断されて1年が経過(パニック障害や社交不安障害の症状もあり)
- 希死念慮や自傷行為あり
- どんな形であれ、働くこと自体が難しい
- 公共交通機関の利用が全くできず、外出もほぼできない
- 一人で外出できる時もあるが、基本的には家族の同伴が必要
- ベッドで寝ている時間が大半
- 金銭的にも体力的にも、家族のサポートがないと生活ができない
- 通院は1か月に1回もしくは2回で、3種類の薬を服用
- 「うつ病」と診断されて3年が経過(パニック障害や社交不安障害の症状もあり)
- 希死念慮や自傷行為なし
- アルバイトはできないが、在宅ワークならできる
- 公共交通機関の利用はほぼ無理だが、条件次第では可能
- 体調が不安定な時のみ、家族の同伴が必要
- 家事や掃除などの作業ができることもあるが、少し動くだけで寝込んでしまう
- 金銭的にも体力的にも、家族のサポートがないと生活ができない
- 通院は2か月に一度で、2種類の薬を服用
正直、申請時はかなりボロボロの状態だったので、自分では「2級くらいかな?」と思っていました。
そのため、3級の手帳が届いた時は「こんなにしんどいのに一番軽度なのか……」という感想でした。
逆に、更新時はかなり状態が改善したので「却下される可能性もあるかも」と覚悟していました。
しかし、引き続き家族のサポートが必要なためか申請が却下されることはなく、3級のまま保留となりました。

これから手帳を申請される方や「どの等級で申請が通るか気になる」という方は、ひとつの目安として参考にしてください。
受けられるサービス
精神障害者手帳を取得する一番のメリットは、日常生活をスムーズに送るためのさまざまなサービスを受けられることです。
障害者手帳を持つことで受けられるサービスについて、主な内容をまとめました。
等級や住んでいる地域によって変わる部分もありますが、だいたいの内容はこんな感じです。
以下の記事では、3級の手帳を持つ私がさまざまなサービスを利用して感じた障害者手帳のメリット・デメリットをまとめています。
ご興味がある方は、こちらも合わせてご覧ください!
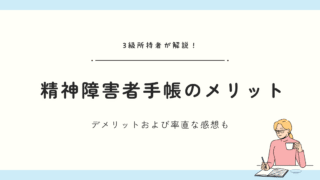
精神障害者手帳|申請の流れ
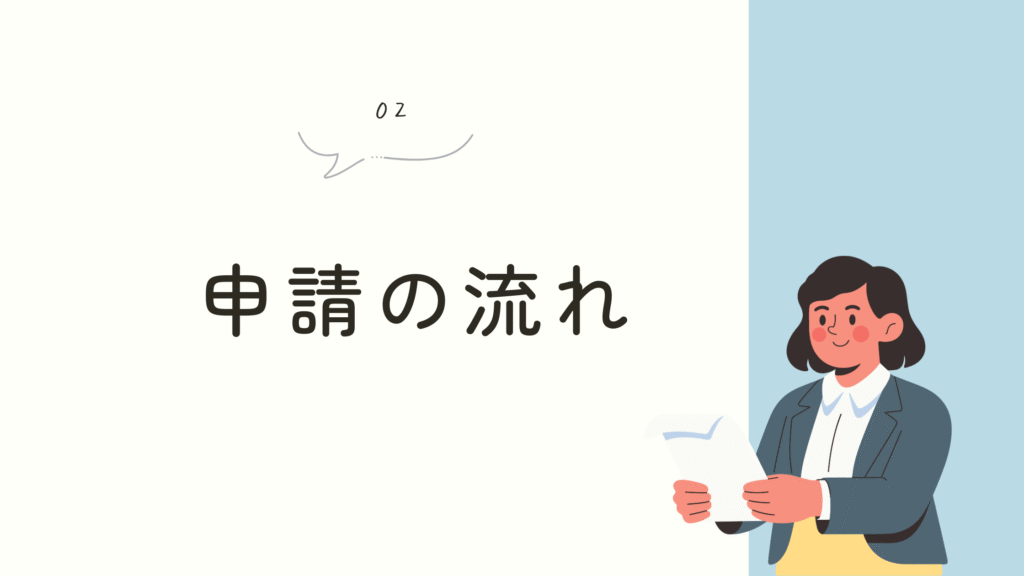
この章では、精神障害者保健福祉手帳の申請手続きについて、体験談をもとにまとめてみました。
「申請したらいつ頃自宅に届くのか?」という多くの方が抱く疑問についても、自身のエピソードを交えて紹介しています!
手帳の申請方法
精神障害者手帳を申請する場合、医師の診断書や申請書などの書類を用意し、市町村の窓口に提出するのが一般的です。
私が住む地域(京都府某市)では、以下の書類を市役所に提出することで、申請手続きができる仕組みになっています。
- 申請書
- 医師の診断書/障害年金の証書の写し
- 本人の写真(縦4cm×横3cm)
- マイナンバーカード
申請書は市役所のHPからダウンロードできたので、私は事前に自宅で印刷・記入をしたうえで、市役所の窓口に持っていきました。
もちろん、市役所の窓口で直接受け取り、その場で記入して申請をおこなうのもOKです。

私の地域は、代理での提出や郵送での提出も可能とのことでした。
外出が難しい方でも申請できる配慮は、すごくありがたいですね。
自立支援医療受給者証の同時申請
精神障害者手帳は、自立支援医療受給者証との同時申請が可能です。
指定した医療機関や薬局の医療費が1割負担になる手帳のようなものです。申請には、医師の診断書や申請書等の書類が必要です。
手帳を申請する方のほとんどは、自立支援医療を利用している方だと思います。
私も、自立支援医療と同時に申請をおこないました!

手帳と自立支援を同時に申請する場合、自立支援申請用の診断書は不要です。
申請書は両方揃える必要がありますが、診断書は手帳申請用のものだけでOKです!
手元に届いたのはいつ?
精神障害者手帳を申請するにあたり、一番気になることは「申請したらいつ頃自宅に届くのか?」という部分だと思います。
あくまでも一個人の体験談となりますが、私の場合は、申請から受け取りまでちょうど2か月かかりました。
- 2022年3月上旬に申請手続き
⇒2022年5月上旬に自宅へ到着
ちなみにこの時は、自立支援医療との同時申請でした。
申請するタイミングや地域によって多少の差はあると思うので、ひとつの目安として参考にしていただければ幸いです。
申請する時に注意したいこと
精神障害者手帳を申請する時、ひとつだけ注意しなければいけないことがあります。
医師が作成する診断書の受け取りに、かなりの時間がかかる!
私の場合、申請をお願いしてから診断書を受け取るまで、約1か月ほどの時間がかかりました。
診断書は、申請者(患者さん)の病状や状況を把握できる唯一の材料のため、多くの記入欄があります。
そのため「お願いしたらすぐに書いてもらえる」というケースは稀で、作成にはそれなりの時間がかかってしまうようです。
医師に診断書の作成を依頼する時は、時間に余裕をもってお願いするようにしましょう。

ちなみに、障害年金を受給されている方は、診断書の代わりに「証書の写し」で申請ができます!
詳しくは、かかりつけ医や市町村窓口にお問い合わせください。
更新の流れ
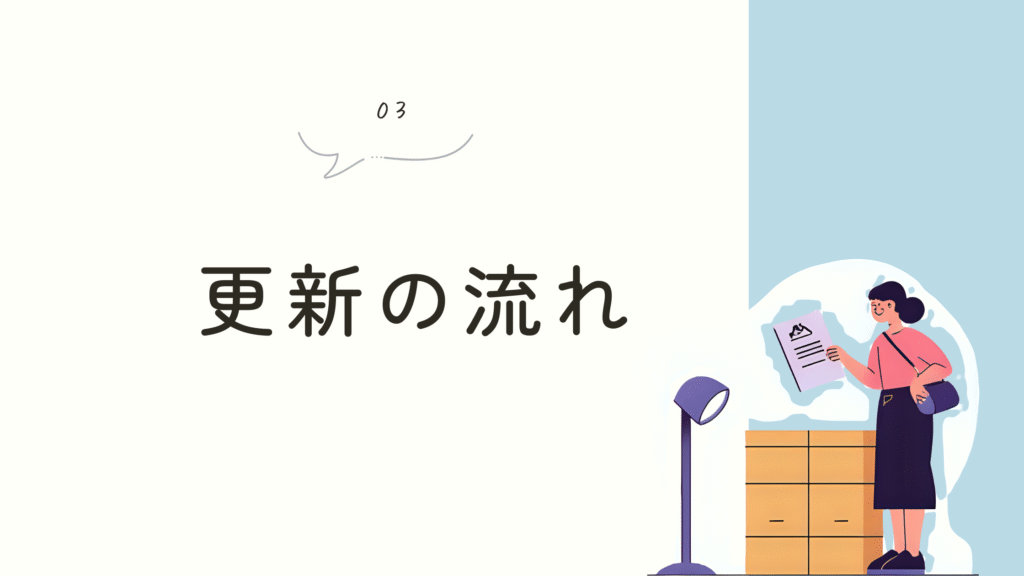
この章では、精神障害者保健福祉手帳の更新手続きについて、体験談をもとにまとめました。
更新の際に気をつけるべきポイントも紹介していますので、ぜひ参考にしてください!
手帳の更新方法
精神障害者手帳の更新手続きは、基本的には申請時と同じです。
医師の診断書や申請書などの必要書類を揃えて、市町村窓口に提出します。
参考までに、私が住む地域の「更新に必要な書類」を紹介しておきます。
- 申請書(「更新」の欄に印を入れます)
- 医師の診断書/障害年金の証書の写し
- 本人の写真(縦4cm×横3cm)
- マイナンバーカード

郵送や代理手続きが可能な場合もあることや、障害年金の証書で手続きができることなど、申請時とすべて同じでした。
手帳の更新時期
手帳の有効期限は「交付日から2年が経過する日の月末」のため、2年に1回の頻度で更新手続きをおこなう必要があります。
- 2024年3月2日が交付日の場合
⇒有効期限は、2026年3月31日まで
ちなみに「交付日」は、手元に手帳が届いた日ではなく、申請書類を市町村窓口に提出し、受付印が押された日です。
最初に申請をおこなった日がそのままずっと「交付日」として記録に残るので、更新をする度に交付日が変わるわけではありません。
更新手続きは、有効期限の3か月前から可能です。
申請時と同様、医師の診断書は受け取りまでに時間がかかるので、なるべく余裕をもって準備を進めるのがおすすめです!

交付日と有効期限は、手帳に記載されています。忘れずにチェックしておきましょう!
自立支援医療受給者証との同時更新
申請時と同様に、自立支援医療受給者証と精神障害者手帳の同時更新もできます!
ただし、手帳の更新は2年に1回の更新でOKですが、自立支援は1年ごとの更新が必要です。
そのため、手帳の更新がない年は、自立支援単独で更新手続きをしなければいけません。
手帳との同時更新を予定されている方は、更新漏れがないようご注意ください。

自立支援医療のほうも、手帳と同じく、有効期限終了の3か月前から更新が可能です。
手元に届いたのはいつ?
精神障害者手帳を更新すると、いつ頃自宅に届くのでしょうか。
参考までに、以下に私の体験談を紹介させていただきます。
- 2024年3月上旬に更新手続き
⇒2024年4月下旬に自宅へ到着
申請の時はちょうど2か月かかりましたが、それよりは少しだけ早く届きました。
こちらも申請時と同様、手続きのタイミングや地域によって差があると思うので、ひとつの目安として参考にしていただければ幸いです。

この時も、自立支援医療との同時更新でした。
更新する時に注意したいこと
精神障害者手帳の更新をおこなう際、注意しなければいけない点が2つあります。
- 更新通知が来ないこと
- 手続きのタイミングによっては、新しい手帳が届く前に有効期限が切れてしまうこと
運転免許のようにハガキなどで更新のお知らせが来ることはないので、自分でしっかりと有効期限を把握しておきましょう。
また、更新手続きのタイミング次第では、新しい手帳が届く前に有効期限が切れてしまうケースもあります。
手帳の有効期限が切れてしまうと、新しい手帳が届くまでは諸々のサービス・サポートを受けることができません。
もし更新を希望する場合は、できるだけ早めに手続きをおこなうようにしましょう!

「手元に届くまで2か月かかる」ということを考慮すると、
有効期限の2か月前には更新手続きが終わっている状態が理想的かと思います。
まとめ|手帳を使ってより良い毎日を!
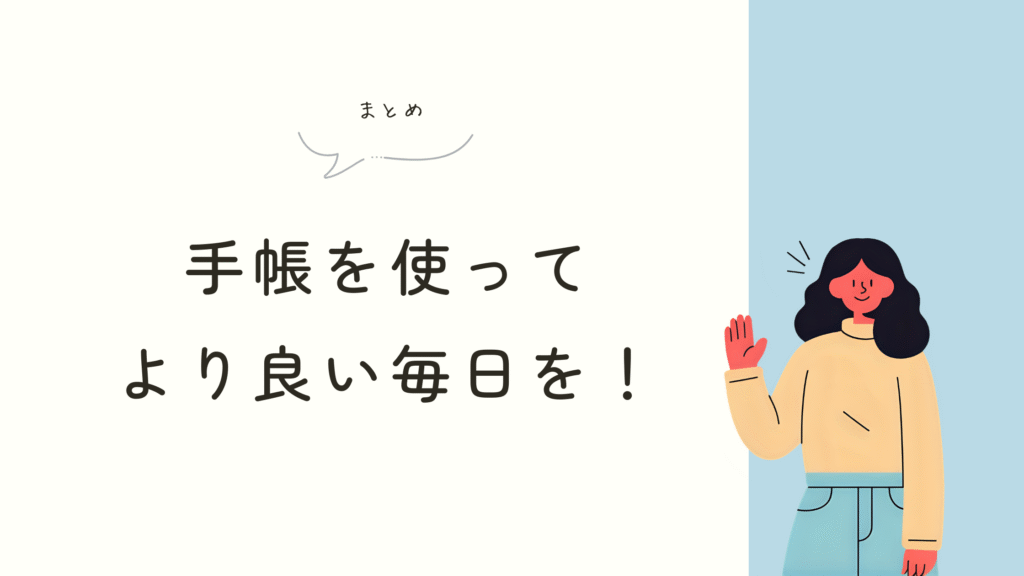
本記事では、精神障害者保健福祉手帳の等級の違い、申請・更新方法について、3級の手帳所持者が体験談をもとにまとめてみました。
精神障害者手帳の存在は、まだあまり世の中に知られていないように思います。
もっと多くの方に手帳の存在を知ってもらい、精神障害を抱える方が少しでも過ごしやすい世の中になることを願っています。